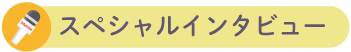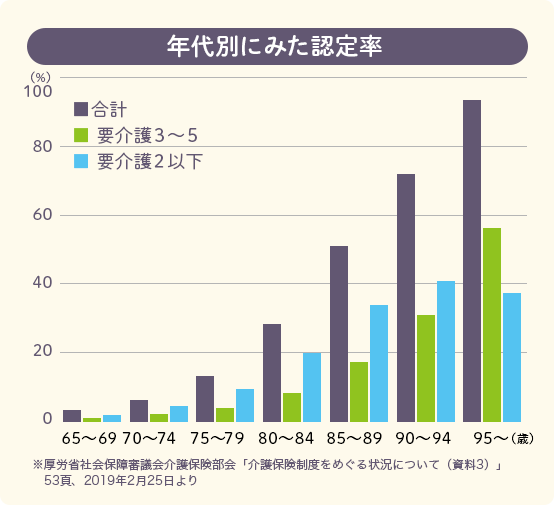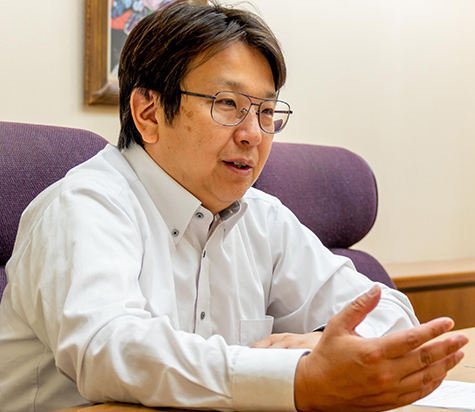「理想の介護」について考えよう
1969年生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒業。法政大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、法政大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。地方自治体にて介護職、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員として勤務。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会委員を務めた実績を持つ。著書には『在宅介護-自分で選ぶ視点』『介護破産-働きながら介護を続ける方法』『正義と福祉-競争と自由の限界 』『親の介護でパニックになる前に読む本 』『介護職がいなくなる-ケアの現場で何が起きているのか 』など。介護のエキスパートとしてメディアにも多数出演。