詳しい資料はこちら
介護保険を利用した訪問リハビリとは?
対象者やメリット・デメリット
自宅でリハビリを受けられる「訪問リハビリテーション」というサービスは、どういった方を対象にどのようなサービスを提供しているのでしょうか。
訪問リハビリテーションとは、国家資格を持つリハビリ専門員が、利用者の自宅を訪問し日常生活の動作訓練や改善などを行っていくサービスです。要介護認定を受けている方、主治医から訪問リハビリが必要だと診断を受けた方がサービスを受けられます。
この記事では、訪問リハビリテーションの概要や、対象者、受けられるサービスについて解説します。また、利用するタイミングや利用手順、訪問リハビリテーションについて知っておくべきこと、デイケアや訪問介護との違いについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
「訪問リハビリテーション」とは?
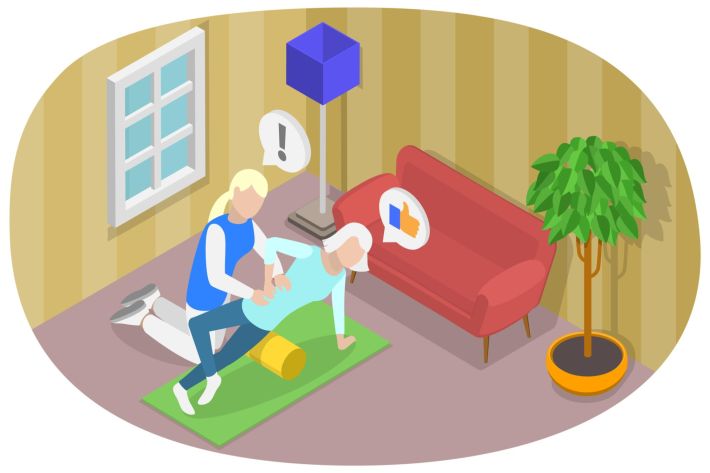
訪問リハビリテーションとは、国家資格を持つリハビリ専門員が利用者の自宅を訪問してリハビリテーションを行うサービスです。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が理学療法や作業療法などのリハビリを、健康状態を把握したうえで主治医の指示に合わせて行います。
訪問リハビリテーションでは病気やケガ、老化などによって衰えてしまった体力や身体機能の維持・回復をサポートします。日常生活における歩行やトイレ、食事などの動作訓練や改善のための取り組みもサービスの対象です。
さらに、利用者家族から相談を受けたりアドバイスをしたりと、利用者家族へのサポートも行っています。
訪問リハビリテーションでは病気やケガ、老化などによって衰えてしまった体力や身体機能の維持・回復をサポートします。日常生活における歩行やトイレ、食事などの動作訓練や改善のための取り組みもサービスの対象です。
さらに、利用者家族から相談を受けたりアドバイスをしたりと、利用者家族へのサポートも行っています。
訪問リハビリテーションを受けられる方
訪問リハビリテーションを受けられる方は以下の条件を満たした方となっています。
-
要介護認定(要介護1~5)を受けている方。40~64歳の方は「16種類の特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)」が原因で要介護認定を受けている方のみが対象
-
主治医から訪問リハビリテーションが必要と判断された方
なお、要介護認定は受けてはいないものの、主治医からリハビリテーションが必要と判断された場合は公的医療保険の適用が可能となっています。
主治医が訪問リハビリテーションを必要と判断するのは、以下のような状態や症状が見られるときです。
主治医が訪問リハビリテーションを必要と判断するのは、以下のような状態や症状が見られるときです。
-
筋力の低下により歩くことが不安になった
-
言葉がはっきりと出てこなくて会話が難しくなった
-
麻痺や拘縮(こうしゅく)がある
-
食事中にむせやすくなった
-
リハビリの方法がわからない
-
購入した福祉用具の使用方法がわからない
訪問リハビリテーションで受けられるサービス内容

訪問リハビリテーションでは以下のようなサービスを受けられます。
-
体温、血圧、脈拍、食事や排せつなどの現状確認や健康管理
-
筋トレや関節可動域訓練など身体機能の維持や改善を目的とした訓練
-
歩行や寝返り、起き上がりなどの日常生活の動作指導
-
段差の解消や手すりの設置など、日常生活における住宅改修アドバイス
-
利用者家族へ適切な福祉用具や福祉制度の助言・相談。介護における指導や助言
訪問リハビリテーションを利用するタイミング
訪問リハビリテーションは「専門家が自宅に来てくれ、リハビリを行える」という点が最大の利点となります。そのため「利用者が外に出られない」「自宅でリハビリを受けたい」という方に適したサービスです。
どのタイミングで訪問リハビリテーションを利用すれば良いのか迷っている方は、下記のタイミングで訪問リハビリテーションを利用するとよいでしょう。
どのタイミングで訪問リハビリテーションを利用すれば良いのか迷っている方は、下記のタイミングで訪問リハビリテーションを利用するとよいでしょう。
-
寝たきりや車いすのため、リハビリに通うことが困難である
-
デイサービスなど通所のサービスに通うのを嫌がるためリハビリに行けない
-
生活動線に沿った実践的な訓練を受けたいので、自宅内でリハビリをしたい
-
専門の知識がある方とマンツーマンでリハビリを受けたい
-
身体介助の方法を知りたい(家族や支援者)
また、訪問リハビリテーションを利用しながら通所リハビリテーションを利用することも可能です。「通所サービスに通うのを嫌がる」などの理由がないようなら、状態に応じて通所サービスの利用も検討するとよいでしょう。ほかの利用者との交流を図れるので、気分転換にもなります。
訪問リハビリテーションの利用手順
訪問リハビリテーションを利用する際の手順は以下のとおりです。
-
まずはケアマネジャーに相談する。ケアマネジャーから、利用可能な事業所を紹介してもらい、実際に利用する事業所を選定していく
-
主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨を伝える。診療情報提供書や訪問リハビリ指示書などといった、サービスを受けるために必要となる書類作成を依頼する(サービスを受けるためには医師の許可が必要)
-
事業所と契約を結ぶ
-
ケアマネジャーと事業所の担当者でケアプランを作成する
-
訪問リハビリテーションの利用を開始する
訪問リハビリテーションのメリット・デメリット
訪問リハビリテーションの活用では、自宅で受けられる快適さがある一方で、施設では受けない制限があることも考慮しましょう。ここからは訪問リハビリテーションのメリットとデメリットについて解説します。
メリット
訪問リハビリテーションでは、施設まで通う必要がないため、寝たきりの方などもリハビリを受けられます。また、通院時間や交通費がかからないといった面もメリットの一つでしょう。
自宅で行えるため、日常生活に沿ったリハビリをすることが可能です。そのときの体調や状況に合わせてマンツーマンでのリハビリを受けられます。
また、リハビリに同席した家族も介助方法などの相談がしやすくなります。
自宅で行えるため、日常生活に沿ったリハビリをすることが可能です。そのときの体調や状況に合わせてマンツーマンでのリハビリを受けられます。
また、リハビリに同席した家族も介助方法などの相談がしやすくなります。
デメリット
訪問リハビリテーションは、施設とは異なり使用できる機器に制限があります。大型の機器を持ち込むことも難しいでしょう。訪問先によっては十分なスペースを確保することが難しい可能性もあるため、施設で行われるリハビリと比較すると、受けられるサービスが限定的なものになる可能性もあります。
また、他人を自宅に招き入れることとなるため、自分のテリトリーに他人がいることで不安やストレスを感じる方もいるでしょう。訪問リハビリテーションを利用する前には、貴重品や、家族以外に見られたくない・触れられたくないものをあらかじめ片づけておく必要があります。
また、他人を自宅に招き入れることとなるため、自分のテリトリーに他人がいることで不安やストレスを感じる方もいるでしょう。訪問リハビリテーションを利用する前には、貴重品や、家族以外に見られたくない・触れられたくないものをあらかじめ片づけておく必要があります。
訪問リハビリテーションで知っておくべき3つのポイント
訪問リハビリテーションは、無制限に何度でも利用できるわけではありません。以下では、サービスを利用する際に知っておくと良い3つのポイントについて紹介します。
回数制限について
公的介護保険での訪問リハビリテーションには回数に制限があります。原則は週6回までです。また、1回当たり20分と定められているため、1週間で120分まで訪問リハビリテーションの実施が可能ということになります(例外として、退院から3カ月以内の場合には、週12回まで、1週間240分まで利用できます)。
なお、1回20分は、1日で利用できる時間が20分までというわけではありません。1日のリハビリで40分間(2回分)利用した場合であれば週3回まで、60分間(3回分)の場合には週2日までの利用が可能です。1日で120分実施することもできます。
なお、1回20分は、1日で利用できる時間が20分までというわけではありません。1日のリハビリで40分間(2回分)利用した場合であれば週3回まで、60分間(3回分)の場合には週2日までの利用が可能です。1日で120分実施することもできます。
費用について
1回当たりの料金は、地域や事業所によって異なります。
介護報酬は地域ごとに地域区分が設定され、市区町村ごとに「1級地」~「7級地」、1級地~7級地以外の「その他」に分類されます。この地域区分ごとに「地域加算」が適用されるため、地域により1単位当たりの料金が変動します(1単位の単価は、サービス別、地域別に10円~11.40円で設定)。
サービスごとに算定した単位数(訪問リハビリテーションの基本単価は308単位/回)に1単位の単価を乗じた額が1回あたりの料金です。その1割~3割が自己負担分となります。
例)時間が20分の場合で、1単位の単価が10円、1割負担の方の場合
308単位×10円=3,080円
3,080×1割=308円
上記より308円が自己負担分となります。
介護報酬は地域ごとに地域区分が設定され、市区町村ごとに「1級地」~「7級地」、1級地~7級地以外の「その他」に分類されます。この地域区分ごとに「地域加算」が適用されるため、地域により1単位当たりの料金が変動します(1単位の単価は、サービス別、地域別に10円~11.40円で設定)。
サービスごとに算定した単位数(訪問リハビリテーションの基本単価は308単位/回)に1単位の単価を乗じた額が1回あたりの料金です。その1割~3割が自己負担分となります。
例)時間が20分の場合で、1単位の単価が10円、1割負担の方の場合
308単位×10円=3,080円
3,080×1割=308円
上記より308円が自己負担分となります。
公的医療保険の適用について
訪問リハビリテーションでは、公的介護保険のほかに公的医療保険を利用することも可能です。ただし、原則として要介護認定を受けている方の場合には、公的介護保険が優先となります。
65歳未満、または65歳以上で要介護認定を受けていない方の場合には公的医療保険でのサービス利用となり、公的介護保険との併用はできません。また、40歳未満の方の場合には公的介護保険に加入していないため、この場合にも公的医療保険の適用となります。
65歳未満、または65歳以上で要介護認定を受けていない方の場合には公的医療保険でのサービス利用となり、公的介護保険との併用はできません。また、40歳未満の方の場合には公的介護保険に加入していないため、この場合にも公的医療保険の適用となります。
通所リハビリテーション(デイケア)や訪問看護との違い

訪問リハビリテーションと似たサービスに通所リハビリテーション(デイケア)や訪問看護があります。ここからは訪問リハビリテーションとの違いをそれぞれ解説します。
通所リハビリテーション(デイケア)
施設や病院に通ってリハビリを受けるのが通所リハビリテーションです。通所リハビリテーションは、集団で行う機能訓練を受けられたり、機能訓練を受けるための環境や設備が整っていたりする点が特徴です。また、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けられる施設もあります。
日常生活の支援、心身機能の維持回復などのサービスを行うという点はどちらも同じです。
日常生活の支援、心身機能の維持回復などのサービスを行うという点はどちらも同じです。
訪問看護
訪問看護とは看護師や保健師などの看護専門職員が利用者の自宅を訪問し、その方に応じた療養上の世話や、医師の指示のもと必要な診療の補助を行うことです。利用者の健康状態の維持や回復のサポートを目的としています。
訪問リハビリテーションと訪問看護ではリハビリの指示を出す医師が異なります。訪問リハビリテーションでは、医療機関や施設、介護医療院に所属する医師が指示を出す一方、訪問看護のリハビリでは利用者の主治医が指示を出します。
訪問リハビリテーションと訪問看護ではリハビリの指示を出す医師が異なります。訪問リハビリテーションでは、医療機関や施設、介護医療院に所属する医師が指示を出す一方、訪問看護のリハビリでは利用者の主治医が指示を出します。
サービスの内容を理解し、訪問リハビリテーションを活用しよう
訪問リハビリテーションは国家資格を持つリハビリ専門員が自宅を訪問し、リハビリを行うサービスです。要介護認定を受けている方や主治医から訪問リハビリテーションが必要と判断された方が、サービスを利用できます。
寝たきりや車いすでの生活でリハビリに通うのが困難な場合や、通所サービスを嫌がりリハビリに行けない場合などで、訪問リハビリテーションを活用するとよいでしょう。
訪問リハビリテーションは自宅でリハビリを受けられる一方で、自宅で実施するがゆえの制限もあります。また、無制限に活用できるサービスではないため、どのくらい利用できるのか、費用はどのくらいかかるのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
サービス内容をきちんと理解し、上手に訪問リハビリテーションを活用していきましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。
公開日:2025年8月7日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




