詳しい資料はこちら
認知症は何科を受診すれば良い?
本人が受診を嫌がる場合の対応とは
身近な人の気になる様子を見て、「もしかして認知症?」と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。認知症を早期に診断し治療を始めることは、症状を軽減し進行を緩やかにすることにつながります。
しかし、病院にはさまざまな診療科があるため、身近な人が認知症かもしれないと感じても何科を受診すれば良いのか迷ってしまうケースが少なくありません。
また、検査にかかる費用や受診時の伝え方など、事前に知っておきたいことはいくつかあります。
この記事では、認知症を疑う場合に何科にかかるべきかを解説します。また、認知症診断の一般的な流れや費用の目安、本人に受診を勧める際のポイント、治療法についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
認知症の受診を検討するタイミング

認知症の受診を検討するタイミングは、認知症の初期症状にあたる様子に気が付いたときです。以下では、認知症のおもな初期症状や早期診断の重要性を解説します。
認知症の初期症状
認知症の初期症状として、以下のような症状が挙げられます。
-
数分前や数時間前にあったことをすぐに忘れる
-
しまい忘れ・置き忘れが増え、いつも探し物をしている
-
同じものをいくつも購入してくる
-
身だしなみに気を遣わなくなる
-
趣味や好きなことに興味を示さなくなる
認知症の初期症状は身近な家族が気付くことが多く、上記のような症状がみられるときは受診を検討するタイミングといえるでしょう。
認知症の早期診断は重要
認知症の初期症状に気付き、早期の診断を受けることは非常に重要です。
早期に医師の診察を受けて認知症かどうかを診断されることで、気になる症状の原因が認知症以外の病気であったときも、適切な治療を受けられます。
例えば、頭部の打撲によって発症した脳内出血が認知症に似た症状を引き起こしているケースでは、早期の処置で症状を改善することも可能です。診断が遅れると適切に治療できなくなる恐れがあります。
また、受診によって認知症であることが確定した場合でも、早期の治療や介護サービスの利用につながれば、本人の将来的な生活の質は大きく向上するでしょう。
早期に医師の診察を受けて認知症かどうかを診断されることで、気になる症状の原因が認知症以外の病気であったときも、適切な治療を受けられます。
例えば、頭部の打撲によって発症した脳内出血が認知症に似た症状を引き起こしているケースでは、早期の処置で症状を改善することも可能です。診断が遅れると適切に治療できなくなる恐れがあります。
また、受診によって認知症であることが確定した場合でも、早期の治療や介護サービスの利用につながれば、本人の将来的な生活の質は大きく向上するでしょう。
認知症が疑われるときは何科にかかるべき?
身近な人について認知症が疑われる場合は、認知症の初期症状に気付いたタイミングで早期に受診することが大切です。
認知症が疑われるときに何科を受診すれば良いか、かかりつけ医がいる場合といない場合に分けて説明します。
認知症が疑われるときに何科を受診すれば良いか、かかりつけ医がいる場合といない場合に分けて説明します。
まずはかかりつけ医に相談
「認知症なのでは?」と感じたときは、まずは本人のかかりつけ医に相談するとよいでしょう。かかりつけ医とは、風邪や体調不良などの際に診察してもらったり健康について相談したりできる、身近で信頼できる医師のことです。
かかりつけ医は本人の普段の様子やこれまでの病気、身体の状態をよく知っています。認知症が疑われるときでも、普段から信頼を置いているかかりつけ医に相談すれば安心です。
診察の結果、かかりつけ医が認知症の疑いが強いと判断した場合、状況に応じた医師や病院を紹介してくれるでしょう。
かかりつけ医は本人の普段の様子やこれまでの病気、身体の状態をよく知っています。認知症が疑われるときでも、普段から信頼を置いているかかりつけ医に相談すれば安心です。
診察の結果、かかりつけ医が認知症の疑いが強いと判断した場合、状況に応じた医師や病院を紹介してくれるでしょう。
かかりつけ医がいない場合
特定のかかりつけ医がいない場合は、以下の診療科を受診するとよいでしょう。
-
脳神経内科
-
脳神経外科
-
精神科
-
心療内科
-
老年科
-
「もの忘れ外来」を開設している病院
-
認知症専門医がいる機関
-
認知症疾患医療センター
認知症の原因によって該当する診療科が異なるため、認知症の受診が可能な診療科は多岐にわたっています。本人や付き添う家族が通いやすい病院を選ぶのがおすすめです。
ただし、初診で紹介状を持たずに受診する場合は、診察までに長い時間がかかる傾向があります。スケジュールには余裕を持って受診しましょう。
以下に、各診療科や機関の特徴を詳しく紹介します。
ただし、初診で紹介状を持たずに受診する場合は、診察までに長い時間がかかる傾向があります。スケジュールには余裕を持って受診しましょう。
以下に、各診療科や機関の特徴を詳しく紹介します。
脳神経内科
脳神経内科では、脳や脊髄、神経、筋肉にかかわる病気を診察しています。身体を動かす、考える、覚えるといった機能に不調があるときに頼りになる診療科です。
認知症は脳の機能低下によって起こる疾患であるため、脳神経内科でも認知症の診察を行う医師もいます。
認知症は脳の機能低下によって起こる疾患であるため、脳神経内科でも認知症の診察を行う医師もいます。
脳神経外科
脳神経外科では、脳や脊髄の異常が原因で起こるけいれん、片まひ、認知機能の低下、意識障害などに対応します。
例えば、脳出血や脳腫瘍といった疾患が認知症のような症状を引き起こすこともあるため、状況によっては手術が必要になることもあります。このような場合には脳神経外科での検査・治療が必要です。
例えば、脳出血や脳腫瘍といった疾患が認知症のような症状を引き起こすこともあるため、状況によっては手術が必要になることもあります。このような場合には脳神経外科での検査・治療が必要です。
精神科
精神科の医師は、認知症やそれにともなう心理的な症状(BPSD)に詳しく、妄想・不安などに対し、薬による治療を行います。本人の性格や心理状態に配慮した診察・支援が受けられることが特徴です。
心療内科
心療内科はおもに心身症(ストレスが引き金となる身体的な不調)の診察を担当しますが、認知症の検査・診断に対応する病院もあります。
ただし、すべての心療内科で認知症に対応しているわけではないため、受診前に認知症に対応できる医師が所属しているかを確認することが重要です。
ただし、すべての心療内科で認知症に対応しているわけではないため、受診前に認知症に対応できる医師が所属しているかを確認することが重要です。
老年科
老年科は高齢者の健康問題に対応し、認知症の診断・治療にも精通している診療科です。
認知機能の低下のほか、身体機能の変化や複数の疾患の相互作用も考慮した診断が可能で、高齢者特有の複雑な症状に対して包括的なアプローチを行います。
認知機能の低下のほか、身体機能の変化や複数の疾患の相互作用も考慮した診断が可能で、高齢者特有の複雑な症状に対して包括的なアプローチを行います。
「もの忘れ外来」を開設している病院
「もの忘れ外来」は、物忘れや認知機能の低下が気になる方を対象とした専門窓口です。
専門医が問診と簡易検査、場合によっては画像・血液検査を行い、認知症か他疾患かを判定し、最適な治療・支援計画を提案します。
専門医が問診と簡易検査、場合によっては画像・血液検査を行い、認知症か他疾患かを判定し、最適な治療・支援計画を提案します。
認知症専門医がいる機関
認知症専門医のいる機関から選ぶのも方法の一つです。専門医は、日本認知症学会や日本老年精神医学会のホームページから検索することが可能です。
専門的な知識と経験を持つ医師による適切な診断・治療が期待できます。
専門的な知識と経験を持つ医師による適切な診断・治療が期待できます。
認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターは、認知症に関する診察や医療相談に対応する専門機関です。
都道府県知事や政令指定都市の市長が指定した病院に設置され、相談や診断から支援まで包括的な対応を行っています。
都道府県知事や政令指定都市の市長が指定した病院に設置され、相談や診断から支援まで包括的な対応を行っています。
認知症診断の流れ
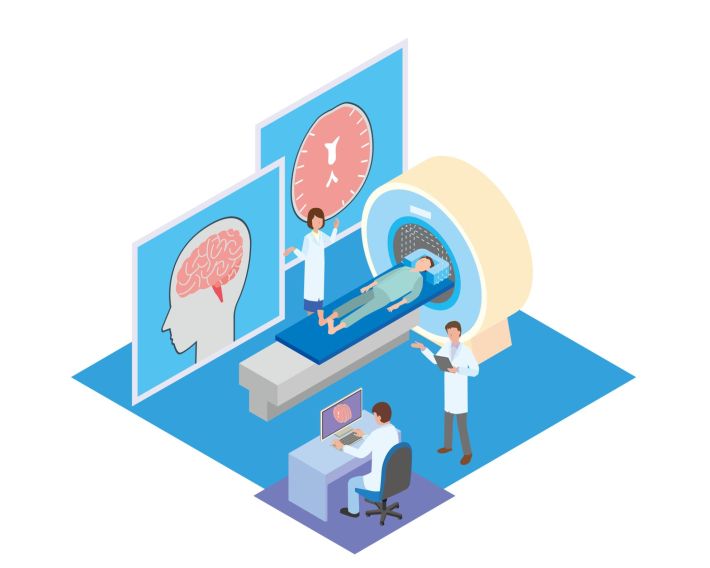
認知症かどうかを診断するための一般的な流れを解説します。総合的な診断によって、認知症かどうかだけでなく、認知症の種類や進行度を明らかにすることが可能です。
1. 診察
診察では医師が本人や家族に対し、現在の状態やこれまでにかかった病気などについて尋ねます。本人が受診に乗り気でない場合は何も答えない可能性があるため、家族が状況をある程度把握しておくことが必要です。
医師が認知症の診察で尋ねることの多い質問を以下に挙げます。
医師が認知症の診察で尋ねることの多い質問を以下に挙げます。
-
認知症が疑われる症状が出始めた時期
-
気になる症状の詳細
-
既往歴
-
飲んでいる薬
2. 身体検査
認知症の診断では認知症以外の病気である可能性の有無を調べるため、一般的な身体検査が実施されます。おもな身体検査は以下のとおりです。
-
血液検査
-
心電図検査
-
感染症検査
-
X線撮影
これらの検査によって医師は身体の全体的な健康状態を確認し、今後の医療や介護の方針を検討します。
3. 神経心理学検査
認知機能を測定するため、日時や場所の認識、簡単な計算、文字を読むなどの検査が行われます。
代表的な検査は以下の3つです。
代表的な検査は以下の3つです。
-
改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
-
ミニメンタルステート検査(MMSE:Mini Mental State Examination)
-
時計描画テスト
検査の点数が一定基準を下回った場合、「認知症の疑い」と判定されます。
ただし、本人が緊張や不安を感じているときや抵抗を覚えて協力的でないときは、検査で提示される課題に対応できないこともあるでしょう。
点数が基準よりも低いことで自動的に認知症と診断されるわけではないため、リラックスして検査に臨むことが大切です。
ただし、本人が緊張や不安を感じているときや抵抗を覚えて協力的でないときは、検査で提示される課題に対応できないこともあるでしょう。
点数が基準よりも低いことで自動的に認知症と診断されるわけではないため、リラックスして検査に臨むことが大切です。
4. 脳画像検査
認知症の検査では、画像をもとに脳の萎縮度合いや脳内の血流の低下を調べる脳画像検査も行われることがあります。おもな検査は以下の4つです。
-
CT
-
MRI
-
SPECT
-
VSRAD
CTはX線を利用したコンピュータ断層撮影です。MRIでは電磁気によって脳の状態を判定します。
またSPECTとは放射線検査薬を注射し、薬の体内動向によって脳の血流量を確認する検査です。VSRADではMRI画像を統計的に解析します。
脳血管性認知症やレビー小体型認知症など、画像検査は診断や鑑別の一助となることがあります。
またSPECTとは放射線検査薬を注射し、薬の体内動向によって脳の血流量を確認する検査です。VSRADではMRI画像を統計的に解析します。
脳血管性認知症やレビー小体型認知症など、画像検査は診断や鑑別の一助となることがあります。
認知症の検査にかかる費用の目安
認知症の検査には公的医療保険が適用されるため、患者の自己負担額は医療費の1~3割となります。血液検査や画像検査などの専門的な検査を組み合わせて行う場合、数千~2万円程度の費用がかかるのが一般的です。
検査の内容によって費用は大きく異なるため、受診を検討している病院に事前に費用の目安を確認しておくとよいでしょう。
検査の内容によって費用は大きく異なるため、受診を検討している病院に事前に費用の目安を確認しておくとよいでしょう。
認知症の治療法
認知症に対する治療法には薬物療法・非薬物療法・適切なケアの3つがあり、ポイントは3つの治療法をバランス良く行うこととされています。
薬物療法
認知症の薬物療法は以下の2種類に分けられます。
-
抗認知症薬によるもの
-
認知症の行動・心理症状を抑える薬によるもの
抗認知症薬による薬物療法は、記憶力や判断力の低下といった認知症の中核症状の進行を遅らせる目的で行われ、「コリンエステラーゼ阻害薬」などを使用します。
抗認知症薬は認知症を比較的軽度な状態に長く保つことが可能です。ただし、進行を完全に止める薬ではありません。
また、認知症の行動・心理症状を抑える薬による薬物療法では、睡眠薬や抗不安薬などが処方されます。抑うつや不眠、不穏など、認知症の行動・心理症状から生じる生活の悪循環を和らげることが目的です。
抗認知症薬は認知症を比較的軽度な状態に長く保つことが可能です。ただし、進行を完全に止める薬ではありません。
また、認知症の行動・心理症状を抑える薬による薬物療法では、睡眠薬や抗不安薬などが処方されます。抑うつや不眠、不穏など、認知症の行動・心理症状から生じる生活の悪循環を和らげることが目的です。
非薬物療法
認知症の非薬物療法は、認知症を患っている方の生活の質を高める効果を期待できます。例えば、読書・ゲームといった知的活動や趣味活動、回想法などは、認知症の代表的な非薬物療法です。
認知症の症状によって生じる不安や焦りに苦しんでいる場合でも、好きな活動に集中すれば本人が自分らしく過ごせます。
認知症の非薬物療法にはさまざまな種類があるため、本人にあったものに取り組むことがポイントです。
認知症の症状によって生じる不安や焦りに苦しんでいる場合でも、好きな活動に集中すれば本人が自分らしく過ごせます。
認知症の非薬物療法にはさまざまな種類があるため、本人にあったものに取り組むことがポイントです。
適切な介護
薬物療法や非薬物療法で認知症の進行を緩やかにしている間に、本人と家族に適した介護サービスを導入することも大切です。環境を適切に調整することで、本人や家族の生活の質をよりよく保てます。
認知症を患っているという状況にゆっくりと慣れ、適切な介護の体制を整える時間を確保するために、薬物療法や非薬物療法を実施するとよいでしょう。
認知症を患っているという状況にゆっくりと慣れ、適切な介護の体制を整える時間を確保するために、薬物療法や非薬物療法を実施するとよいでしょう。
本人に受診を勧めるときと受診時のポイント

認知症の疑いがある場合、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。しかし、本人が抵抗を示すこともあり、無理に連れて行こうとするとかえって逆効果になることもあります。
ここでは、受診時に心がけたいポイントを6つ紹介します。
ここでは、受診時に心がけたいポイントを6つ紹介します。
うそをついて無理やり連れて行くことは避ける
本人が受診を嫌がるからといって、病院に行く理由を偽って無理に連れて行くのは避けるべきです。
「健康診断だから」「別の病気の検査だから」などと偽って受診させると、本人が医療機関で事実を知ったときに傷付き、信頼関係が壊れてしまいます。
一度失った信頼を回復するのは簡単ではなく、その後の治療や通院にも大きな支障をきたす恐れがあります。正直な気持ちで接し、心から心配していることを伝えることが大切です。
「健康診断だから」「別の病気の検査だから」などと偽って受診させると、本人が医療機関で事実を知ったときに傷付き、信頼関係が壊れてしまいます。
一度失った信頼を回復するのは簡単ではなく、その後の治療や通院にも大きな支障をきたす恐れがあります。正直な気持ちで接し、心から心配していることを伝えることが大切です。
本人が受診を嫌がるときは伝え方を工夫する
本人が受診を拒否する場合、無理やり連れて行くと不安をあおり逆効果となってしまいます。
認知症という言葉はできるだけ使わず、「念のために行こう」「予防のために早めに受診する人が多い」などと伝えるとよいでしょう。
また、受診を勧める場合には、家族や親族のなかでも近しすぎず適切な距離感のある方が本人に伝えるという方法も有効です。
かかりつけ医がいる場合は事前に連携し、医師の口から受診を勧めてもらうと素直に受け入れやすくなります。
どうしても本人が受診を拒むときは、医療機関に相談し訪問診療(往診)を依頼するのも一つの方法です。
認知症という言葉はできるだけ使わず、「念のために行こう」「予防のために早めに受診する人が多い」などと伝えるとよいでしょう。
また、受診を勧める場合には、家族や親族のなかでも近しすぎず適切な距離感のある方が本人に伝えるという方法も有効です。
かかりつけ医がいる場合は事前に連携し、医師の口から受診を勧めてもらうと素直に受け入れやすくなります。
どうしても本人が受診を拒むときは、医療機関に相談し訪問診療(往診)を依頼するのも一つの方法です。
受診の前に伝えたい情報を整理する
実際に受診する段階になると本人だけでなく家族も緊張して、認知症が疑われる症状や困りごとを医師にうまく伝えられないことがあります。
事前に症状や既往歴の情報を書き出すなど、情報を整理しておくとスムーズに受診することが可能です。
また、症状や既往歴などの具体的な情報だけでなく、家族として不安なことや医師に相談したいことを書きとどめておくのもよいでしょう。
事前に症状や既往歴の情報を書き出すなど、情報を整理しておくとスムーズに受診することが可能です。
また、症状や既往歴などの具体的な情報だけでなく、家族として不安なことや医師に相談したいことを書きとどめておくのもよいでしょう。
診断結果はできるだけ誰かと一緒に聞く
受診の結果「認知症」と診断された場合は、本人・家族ともに精神的なショックのために医師からの説明や重要な情報を聞き逃してしまう恐れがあります。
認知症かどうかの診断結果はできるだけ一人ではなく、ほかの家族や信頼できる人と聞きましょう。
診断結果を聞く場への同席が難しい場合でも、結果を聞いたあとすぐに誰かと連絡できる体制を整えておくことをおすすめします。
認知症かどうかの診断結果はできるだけ一人ではなく、ほかの家族や信頼できる人と聞きましょう。
診断結果を聞く場への同席が難しい場合でも、結果を聞いたあとすぐに誰かと連絡できる体制を整えておくことをおすすめします。
本人への告知は慎重に判断する
結果を聞く場に受診者本人がいない場合、認知症の診断結果を本人に伝えるかどうかは、性格や判断力を考慮しながら家族で慎重に判断することが必要です。
早期に伝えることで治療方針や将来について本人の意向を確認できるメリットがある一方、精神的に大きなショックを受けてしまう可能性があります。
告知する場合は、病気に対する理解を深めてもらいながら、今後の見通しや支援体制について丁寧に説明し、不安を和らげるサポートを心がけましょう。
早期に伝えることで治療方針や将来について本人の意向を確認できるメリットがある一方、精神的に大きなショックを受けてしまう可能性があります。
告知する場合は、病気に対する理解を深めてもらいながら、今後の見通しや支援体制について丁寧に説明し、不安を和らげるサポートを心がけましょう。
認知症と診断された場合は公的機関に相談する
認知症と診断された本人や家族は、事実を受け入れられなかったりショックのためふさぎこんでしまったりすることもあります。まずは精神的なケアが重要です。
気持ちが落ち着いたあとには、本人が今後どのように過ごしたいか、また将来に備えて何をしておくべきかなどを確認する必要があります。疑問や悩みごとがある場合は、地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。
気持ちが落ち着いたあとには、本人が今後どのように過ごしたいか、また将来に備えて何をしておくべきかなどを確認する必要があります。疑問や悩みごとがある場合は、地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。
認知症で何科にかかるか迷うときは、まずかかりつけ医に相談を
認知症の早期診断・早期治療は、本人や家族の将来的な生活の質をより良くすることにつながります。
認知症の初期症状にあたる様子に気付いたときは、受診を検討するタイミングです。まずは、本人の普段の状態をよく知る、かかりつけ医に相談しましょう。
認知症の診断検査には公的医療保険が適用され、自己負担額は1~3割となります。血液検査や画像検査を含めても、数千~2万円程度が一般的な費用の目安です。
本人が受診を嫌がる場合は無理に連れて行こうとせず、伝え方を工夫したり、かかりつけ医や医療機関と連携したりすることが大切です。本人の気持ちに寄り添いながら、必要な検査や支援につなげていきましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
菊池 大和[医師]

医療法人ONEきくち総合診療クリニック理事長・院長。地域密着の総合診療かかりつけ医として、内科から整形外科、アレルギー科や心療内科など、ほぼすべての診療科目を扱っている。日本の医療体制や課題についての書籍出版もしており、活動が評価され2024年11月にTIMEアジア版に掲載される。
資格:日本慢性期医療協会総合診療認定医・日本医師会認定健康スポーツ医・認知症サポート医・身体障害者福祉法指定医(呼吸器)・厚生労働省初期臨床研修指導医・神奈川県難病指定医 など
資格:日本慢性期医療協会総合診療認定医・日本医師会認定健康スポーツ医・認知症サポート医・身体障害者福祉法指定医(呼吸器)・厚生労働省初期臨床研修指導医・神奈川県難病指定医 など
公開日:2025年8月7日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




