詳しい資料はこちら
「要支援」認定と介護予防サービス
介護や支援が必要なご家族がいる場合、
介護保険制度の要介護もしくは要支援の認定を受けることで、
介護サービスや介護予防サービスの利用が可能になります。
認定には、どの程度の介護が必要かによって
要支援1 から要介護5 までの7 段階あり、
その段階に応じて利用可能なサービスや給付額が変わってきます。
ここでは、軽度介護状態である要支援1と要支援2について詳しく解説します。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
要支援1・2とは?
認定には、介護や支援を必要としない「自立」、介護は必要ないものの日常生活を送るにあたって手助けを必要とする「要支援」、そして介護を必要とする「要介護」があり、さらにその程度によって、要支援は2 段階、要介護は5 段階に分けられます。
要支援1・2の状態の目安

-
日常生活の一部に見守りや手助けが必要
-
立ち上がりなどに何らかの支えを必要とすることがある

-
食事や排せつなど、時々介助が必要
-
立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い
※上記の状態はあくまで目安であり、実際に認定を受けた人の状態と一致しないことがあります。
要支援で利用できる介護予防サービス
要支援認定を受けた人は、訪問型サービスや通所型サービス、福祉用具のレンタルなど、さまざまな介護予防サービスを利用できます。要支援で利用できるサービスの具体例の一部をご紹介します。
※表中に金額の記載があるものは、利用者負担1 割での金額の目安です。金額は地域やサービス内容によって異なり、また記載した料金以外にも食費や日常生活費などがかかる場合があります。(金額はエス・エム・エス調べ)
訪問してもらうサービス

介護予防・日常生活支援総合事業
/訪問型サービス
ホームヘルパーが自宅を訪問し、支援や見守りを行います。民間事業者や住民ボランティアによる生活支援や外出時の移動支援、専門職による体力や日常生活動作の改善に向けた相談などがあります。
週1回の利用で
1回につき1,200円程度

介護予防訪問
リハビリテーション
医師の指示により理学療法士や作業療法士が訪問し、筋力や体力の維持、歩行の練習など、日常生活動作の低下防止のためのリハビリテーションを行います。
1回の利用(20分以上)
で300円程度
「要支援」であっても
様々な介護予防サービスを利用できます。
施設に通って利用できるサービスや
福祉用具レンタルのサービス等について見ていきましょう。
福祉用具レンタルのサービス等について見ていきましょう。
施設に通うサービス

介護予防・日常生活支援総合事業
/通所型サービス
デイサービスなどで、食事や入浴などの日常生活支援や機能訓練やレクリエーションなどを行います。また、民間業者によるデイサービス、住民主体のコミュニティサロンや運動(体操教室やウォーキング)・文化活動、口腔・栄養教室、交流の場の利用などがあります。
1ヵ月あたり
要支援1で1,600円程度
要支援2で3,300円程度

介護予防通所
リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで、リハビリテーションや食事・入浴などの日常生活上の支援を行い、自立した生活が送れるように支援を行います。
日常生活上の支援などの
サービスの場合、1ヵ月あたり
要支援1で1,700円程度、
要支援2で3,600円程度
施設に短期間滞在するサービス

介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
家族が一時的に在宅で介護することが困難な状況になった場合や、介護の負担を軽減するために、施設等に短期間滞在し、在宅生活を続けるための日常生活の支援や機能訓練等を行います。
併設型・多床室の場合、1日あたり要支援1で400円程度、要支援2で500円程度
その他のサービス

介護予防福祉用具の
貸与(レンタル)
車椅子や介護ベッド、歩行器など、できる限り自宅で過ごせるように福祉用具を借りることができます。
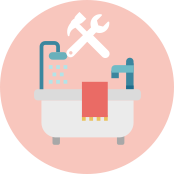
介護予防福祉用具
購入費の支給
レンタルには適さない、入浴用椅子やポータブルトイレなどの入浴や排せつに用いる福祉用具を指定事業所から購入した場合に、介護予防福祉用具購入費が支給されます。具体的には、浴室内での転倒予防の手すり、浴槽用手すり、浴槽のふちに設置することで浴槽の出入りを容易にする台、入浴を容易にするための浴槽内すのこなどがあります。

介護予防住宅改修費
の支給
現在住んでいる住宅において、手すりの取り付け、敷居などの段差の解消、スロープの設置、滑りにくい床材への変更、引き戸への変更などの支給対象となる改修工事を行った場合に、介護予防住宅改修費が支給されます。間取りや家族の意見を取り入れながら、利用者が住み慣れた家で生活できるように改修することが大切です。
「住んでいる地域で具体的にどのようなサービスがあるのか」
「どのようなサービスを受けたら良いのか」などの不明な点がある場合は、
お住まいの地区を担当している地域包括支援センターに相談しましょう。
「どのようなサービスを受けたら良いのか」などの不明な点がある場合は、
お住まいの地区を担当している地域包括支援センターに相談しましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




