詳しい資料はこちら
介護における食事の重要性
基本知識・作る際のポイント・食材の選び方
高齢者のなかには、病気などの理由により食事に配慮が必要な方もいます。そのような場合は介護食を提供することになりますが、提供の経験がない方にとっては、何の食材をどのように提供すれば良いのかわからないこともあるでしょう。
介護食を提供する際は、介護される方の状態に合ったものを提供する必要があります。そのためにも、介護食への理解を深めることが大切です。
この記事では、介護食の基本知識や、作る際のポイント、食材の選び方などを紹介します。
詳しい資料はこちら
「介護食」とは?

介護食の目的は、要介護者の健康と生活の質を維持することであり、栄養不足や食事摂取の困難を解消することを目指しています。
介護食の調理にあたっては、食材の選択や特別な調理方法による、栄養バランスや嚥下の安全性への考慮が重要です。
介護食が必要な理由
まず、加齢とともに歯の本数が減少し、義歯の使用が増えることで、咀嚼力が低下する傾向があります。これにより、硬いものや大きな食材をかみ砕くことが難しくなるため、食事に対する意欲も低下しがちです。
また、飲み込む力(嚥下機能)も衰え、食べ物が気管に入りやすくなることで、誤嚥や窒息のリスクが高まります。
食事中にむせる、飲み込むのに時間がかかるといった変化が見られるようになり、誤嚥性肺炎などの重篤な病気につながる恐れもあるでしょう。誤嚥性肺炎は高齢者にとって命にかかわる危険性があり、特に注意が必要です。
こうしたリスクを回避し、安全に食事を楽しめるようにするためには、食事をする方に合わせた食事に切り替えることが重要です。食材の硬さや大きさ、とろみの活用などを調整することで、嚥下機能に合わせた食事環境を整えられます。
また、専門家による嚥下機能の評価に基づき、適切な食事形態や介助方法を取り入れることが事故の予防にもつながります。窒息事故を防ぐためにも、食事形態に配慮した介護食の導入は不可欠です。
介護食のおもな形状5種類と特徴
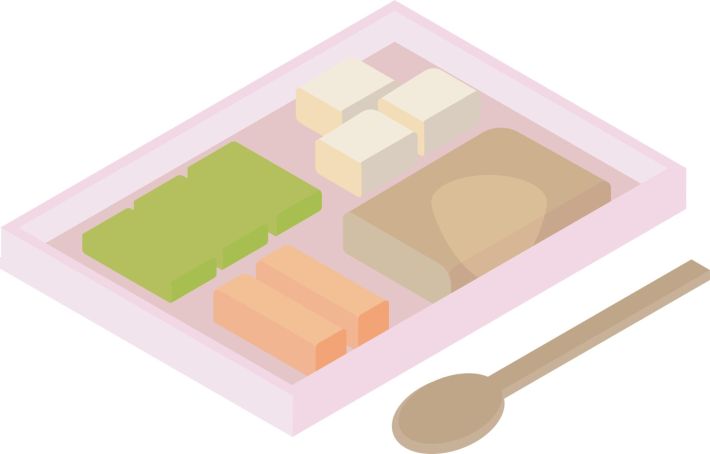
きざみ食
軟菜食(ソフト食)
ムース食
ゼリー食
つるりとした口当たりやのどごしの滑らかさがあり、形状があることから、流動食と比べて視覚的に食欲もわきやすいでしょう。
ミキサー食
一方で、食感や見た目の問題から、満足感や食事の楽しみが低下する可能性があるため、食べる方の心理的な側面にも注意が必要です。
市販の介護食|2種類の規格

-
日本介護食品協議会が制定した自主規格「ユニバーサルデザインフード」
-
農林水産省が整備した介護食の枠組み「スマイルケア食」
日本介護食品協議会が制定した自主規格「ユニバーサルデザインフード」
|
区分 |
かむ力の目安 |
飲み込む力の目安 |
|
容易にかめる |
硬いものや大きいものはやや食べづらい |
普通に飲み込める |
|
歯茎でつぶせる |
硬いものや大きいものは食べづらい |
ものによっては飲み込みづらいことがある |
|
舌でつぶせる |
細かくてやわらかければ食べられる |
水やお茶が飲み込みづらいことがある |
|
かまなくて良い |
固形物は小さくても食べづらい |
水やお茶が飲み込みづらい |
農林水産省が整備した介護食の枠組み「スマイルケア食」
|
識別マーク |
対象者 |
内容 |
|
青マーク |
かむことや飲み込むことに問題はないが、健康維持上栄養補給を必要とする方向け |
|
|
黄マーク |
かむことに問題がある方向け |
5:容易にかめる食品 4:歯茎でつぶせる食品 3:舌でつぶせる食品 2:かまなくて良い食品 |
|
赤マーク |
飲み込むことに問題がある方向け |
2:少し咀嚼して飲み込める性状のもの 1:口のなかで少しつぶして飲み込める性状のもの 0:そのまま飲み込める性状のもの |
介護食作りの4つのポイント
食材は適切に調理する
包丁の入れ方や油分・水分の加減、とろみ付けなどの工夫を施し、食べる力をサポートしましょう。
おいしそうな見た目にする
スムーズに栄養を摂ってもらうためにも、できるだけおいしそうに見せ、食欲を引き出すよう工夫しましょう。例えば、ブレンダーにかけるときは食材同士を混ぜない、彩りや型抜きを工夫する、メニュー表を添える、食器や盛り付けにこだわるなどの方法が考えられます。
味付けと香りを工夫する
ただ、単純に塩味を減らすだけでは、味気ない食事になってしまいます。対策として、出汁を上手に利用する、香辛料の使い方を工夫するなど、旨味や香りでおいしさを維持することがおすすめです。
飽きないメニューにする
例えば、ご飯、主菜、副菜、汁物などで、バリエーションとメリハリをつけたり、レトルト・作り置きをうまく使い、より少ない手間で献立の幅を広げるよう工夫したりするのもよいでしょう。
介護食を作る際の食材の選び方
高齢者が食べやすい食材
-
脂ののった魚や肉まぐろやぶりのような脂ののった魚や、脂身のある薄切り肉は、かむ力が弱い方でも食べやすく、栄養価も豊富です。
-
豆腐やわらかい食感の豆腐は、タンパク質やカルシウムを含み、カロリーが控えめでありながら栄養豊富です。木綿豆腐は絹ごし豆腐と比べてやや水分量が少なく、口に残りやすいことから、そのままではなく豆腐ハンバーグのような調理に使うとよいでしょう。
-
バナナ熟れたバナナはやわらかくて消化も良く、高齢の方にとって食べやすい果物です。果物をメニューに取り入れることで、飽きさせない工夫にもなります。
-
納豆納豆はやわらかい食感で、良質なタンパク質や食物繊維を含みます。咀嚼や嚥下に不安がある場合は、包丁の背でたたくなど、加工するとよいでしょう。つるつるしてかみにくい場合は、ほかの食材と混ぜておやきにするのもおすすめです。
-
とろろ昆布とろろ昆布は食べやすく、のどごしも滑らかです。口のなかでほかの食べ物のまとまりを補助してくれる効果もあります。味噌汁などの汁物に入れるのも、口当たりが滑らかになっておすすめです。
-
オクラぬめり成分のあるオクラは、食べやすい食材です。調理する際、種は取り除きましょう。
高齢者が食べにくい食材
一方、ごぼうなどの繊維の多い野菜、いかやたこなどのかみにくいもの、かまぼこのような弾力があるものは、介護食の食材に基本的に向きません。これらの不向きな食材は無理に使わず、別のもので代替しましょう。
介護食の作り置きはできる?
ただし、一度にたくさん作りすぎると劣化や食中毒の原因になるため、作り置きの量は最大で2食分程度を目安にし、1食分ずつ小分けに保存しましょう。高齢者は若者と比べて免疫力が落ちている可能性があるため、衛生面には細心の注意を払う必要があります。冷凍や加熱によって死滅しない細菌も存在するため、調理や保存の段階からしっかり管理するのが鉄則です。
介護食を支えるサービスと制度
以下では、介護食に関連する便利なサービスや公的制度を紹介します。
宅配介護食サービス
献立は管理栄養士が監修しているケースが多く、栄養バランスがしっかりと考えられている点も魅力です。
また、食事形態を選べるサービスもあり、かむ力や飲み込む力に応じて「きざみ食」「ムース食」「ミキサー食」などから選択できます。
公的介護保険で受けられる食事支援
自治体によっては、自立支援や在宅生活の継続を目的とした独自の食事支援制度を設けています。その場合、条件を満たせば一部助成を受けて配食サービスを利用できます。
こうした制度の有無や利用条件については、各自治体の窓口やケアマネジャーに相談すると、詳しい情報を得ることができるでしょう。
地域包括支援センターや栄養士への相談も視野に
地域によっては、管理栄養士による個別相談や栄養指導、調理講座などを実施しており、介護者にとって大きな支えとなるサービスが充実しています。
さらに、地域の介護予防事業に参加することで、栄養や健康に関する知識が深まり、介護食の工夫や日々の食生活の改善にもつながります。
専門家のアドバイスを取り入れ、より安心・安全な介護環境を整えましょう。
介護食のポイントを知って食事体験を充実させよう
介護における食事は、単なる栄養補給にとどまらず、心と体の健康を支える大切な要素です。
高齢者の咀嚼・嚥下機能の低下に応じた介護食の提供は、誤嚥や窒息のリスクを防ぎ、安全で楽しい食事時間を実現するために欠かせません。
市販の介護食や宅配サービス、公的支援制度などを上手に活用することで、介護者の負担を減らしながら、高齢者本人にとっても満足度の高い食生活を送れるようになります。
健康の維持と食べることの楽しみを守るために、介護食に関する知識を深め、適切な選択と工夫を心がけましょう。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

公開日:2025年9月10日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




