詳しい資料はこちら
介護保険負担限度額認定証とは・取得条件や申請手続き
老後の生活において、介護保険施設の利用の際などに費用負担の軽減をしたいと考えている方もいるでしょう。その際に役立つのが、介護保険負担限度額認定制度です。
介護保険負担限度額認定制度によって費用負担の軽減を実現するためには、所定の手続きを行い、介護保険負担限度額認定証を取得する必要があります。ただし、取得には収入・資産状況など条件が設けられている点に注意が必要です。
この記事では、介護保険負担限度額認定証の概要や取得条件、手続き方法などを解説します。
詳しい資料はこちら
介護保険負担限度額認定証の概要
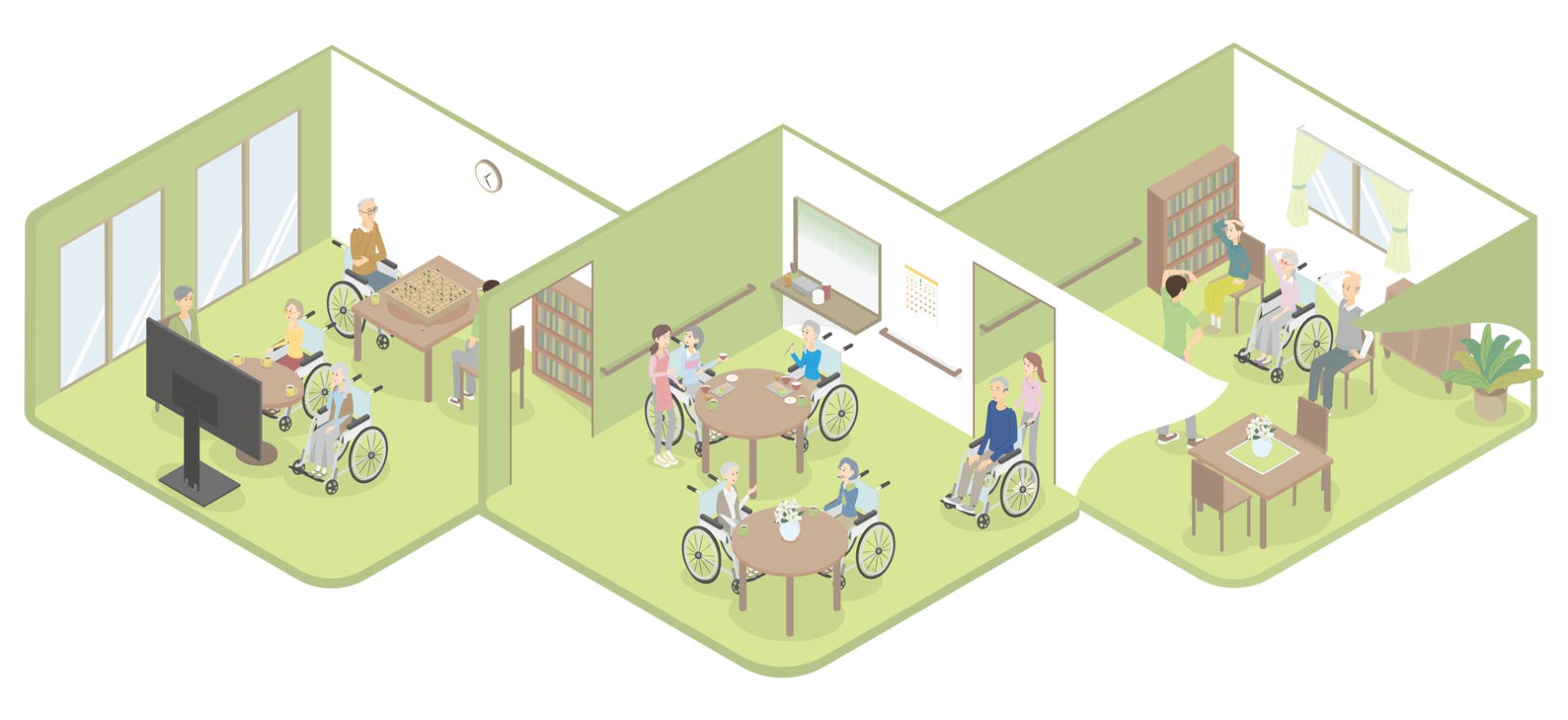
ここでは、介護保険負担限度額認定制度についての説明、また、介護保険負担限度額認定証の概要を解説します。
負担限度額認定制度とは
負担限度額認定制度は一定の条件を満たしている人に適用され、対象者には負担限度額認定証が交付されます。交付後は自己負担上限額が設定され、負担する費用が軽減されます。
「介護保険負担限度額認定証」は制度の対象者に交付される
● 介護サービス費
● 居住費
● 食費
● 日常生活費
これらのうち、介護サービス費は公的介護保険が利用できるため、自己負担は1~3割で済みます。しかし、それ以外の費用に関してはすべて自己負担となってしまいます。
そこで、介護保険施設へ入居した場合の居住費と食費の負担を軽減するための制度が、介護保険負担限度額認定制度です。
介護保険負担限度額認定証は、介護保険負担限度額認定制度の認定を受けた方に発行される書類のことです。この認定証を交付されることで、介護保険施設の利用にかかる居住費や食費の負担を減らせます。
介護保険負担限度額認定証が使える介護保険施設
-
特養(特別養護老人ホーム)
-
老健(介護老人保健施設)
-
介護医療院
-
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
-
短期入所生活介護
-
短期入所療養介護
介護保険負担限度額認定証の申請・取得条件
さらに、この認定は本人の収入状況や預貯金によって「第1段階」「第2段階」「第3段階(1)」「第3段階(2)」「第4段階」の5段階に分けられます。
|
段階 |
本人の収入状況 |
預貯金等の基準額 |
|
第1段階 |
老齢福祉年金や生活保護を受給している |
夫婦:2,000万円以下 単身:1,000万円以下 |
|
第2段階 |
年金収入等が80万円以下 |
夫婦:1,650万円以下 単身:650万円以下 |
|
第3段階(1) |
年金収入等が80万円超120万円以下 |
夫婦:1,550万円以下 単身:550万円以下 |
|
第3段階(2) |
年金収入等が120万円超 |
夫婦:1,500万円以下 単身:500万円以下 |
|
第4段階 |
上記以外 |
上記以外 |
参考:出雲市公式ホームページ
【所得の条件】世帯全員が住民税非課税であること
「世帯全員が住民税非課税ということは、住民票上の世帯を分ければ良いのでは」と思う方もいるかもしれません。しかし、夫婦で世帯を分けている場合でも、本人と配偶者の両方が住民税非課税でないと条件を満たしたことにはなりません。
【預貯金の条件】預貯金等が基準額以下であること
|
本人の収入状況 |
預貯金等の基準額 |
|
老齢福祉年金や生活保護を受給している |
夫婦:2,000万円以下 単身:1,000万円以下 |
|
年金収入等が80万円以下 |
夫婦:1,650万円以下 単身:650万円以下 |
|
年金収入等が80万円超120万円以下 |
夫婦:1,550万円以下 単身:550万円以下 |
|
年金収入等が120万円超 |
夫婦:1,500万円以下 単身:500万円以下 |
参考:出雲市公式ホームページ
-
株式や債券などの有価証券
-
金・銀などの貴金属
-
投資信託
-
現金(タンス預金)
介護保険負担限度額認定は5段階
なお、2024年(令和6年)8月1日から介護保険施設などにおける居住費の負担限度額が変更されたため、以下では現行の負担限度額を記載しています。
|
段階 |
居住費の負担限度額(ユニット型個室) |
居住費の負担限度額(多床室) |
食費の負担限度額(ショートステイを除く) |
|
第1段階 |
880円/日 |
0円/日 |
300円/日 |
|
第2段階 |
880円/日 |
430円/日 |
390円/日 |
|
第3段階(1) |
1,370円/日 |
430円/日 |
650円/日 |
|
第3段階(2) |
1,370円/日 |
430円/日 |
1,360円/日 |
|
第4段階 |
2,066円/日 |
437円/日(※) |
1,445円/日 |
※特別養護老人ホームまたは短期入所生活介護を利用する場合は915円/日
参考:出雲市公式ホームページ
第4段階の特例措置の対象になるのは、以下の条件をすべて満たしている場合です。
-
属する世帯の構成員数が2人以上である
-
介護保険料を滞納していない
-
世帯における現金および預貯金などが450万円以下(債券や有価証券などを含む)
-
家屋や日常生活に必要な資産を除き不要な資産を所有していない
-
介護保険施設に入所または入院しており第4段階の食費や居住費を負担
-
世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が80万円以下
介護保険負担限度額認定証を申請する方法
認定証の申請先
申請するために必要な書類
-
介護保険負担限度額認定申請書
-
同意書(金融機関等に預貯金等の報告を求めることに同意する書類)
-
預貯金等を証明するための書類
自治体によって必要書類が異なる場合もあるため、詳しくはお住まいの自治体のホームページを確認することをおすすめします。
なお、ショートステイを利用する際の申請では、「介護保険施設の所在地」および「名称」の記載は不要です。被保険者本人の氏名を記入し、押印した書類を提出してください。
第1・第2・第3段階に該当している場合は、申請後に介護保険負担限度額認定証が交付されます。施設を利用する際、事前に提示しなければ減額されないため注意が必要です。
認定証の交付
介護保険負担限度額認定証の注意点
有効期間があるため更新を忘れずに
なお、前年から収入状況などに変化があった場合、負担限度額の段階が変動する可能性があります。結果が届いたら、新しい負担段階をよく確認しましょう。
虚偽の申告はNG
「預貯金通帳の残高が少ない部分をコピーして提出すればよいのでは」と考える方もいるかもしれませんが、自治体には金融機関に対して申請者の残高照会を行う権限があるため、虚偽の申告が明らかになる可能性が高いです。
虚偽の申告をして不正に認定を受けた場合、それまでに受けた給付額を返還することはもちろん、最大2倍の加算金を支払わなければなりません。所得や預貯金等の金額は正確に申告しましょう。
介護保険負担限度額認定を受けられそうにない場合の選択肢

では、高齢者施設にはどのような種類があるかご存じでしょうか。具体的には、以下のような施設が挙げられます。
|
介護付き有料老人ホーム |
定額で介護サービスを受けられる施設。要介護5までを入居対象としており、入居後に要介護度が高くなっても転居の必要がないケースが多い。 |
|
住宅型有料老人ホーム |
入居者同士コミュニケーションを取りながら共同生活を送る施設。レクリエーションなどのイベントが多いこともあり、一人暮らしによる不安を抱くことなく生活できる。 |
|
サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住) |
老人ホームではなく、シニア向けの賃貸住宅。自宅で暮らしているかのような自由度があり、見守りサービスも受けられる。施設内はバリアフリーのため、一般的な賃貸住宅を借りるよりも安全性が高い。 |
|
グループホーム |
認知症の人を専門に受け入れている入居施設。認知症ケアの専門スタッフによるケアを受けることが可能で、症状進行の緩和を目的としたレクリエーションなどを体験できる。 |
以上を踏まえると、老後の生活への備えは必須といえるでしょう。公的介護保険で足りない部分の備えは、民間介護保険でカバーすることもおすすめです。
介護保険負担限度額認定証を利用して負担を減らそう
介護保険負担限度額認定証とは、介護保険負担限度額認定制度を受けられる人に発行される書類のことです。介護保険負担限度額認定証を取得することで、介護保険施設を利用する際の居住費や食費の負担が軽減されます。
認定証の申請には収入状況や預貯金等の条件があるため、ご自身が条件を満たしているかを確認したうえで手続きを行いましょう。
また、限度額認定証には有効期限があることや、認定を受けるために虚偽の申告をすることは厳禁であることなどに注意が必要です。
認定を受けられないと予想される場合には、老後の備えとして民間介護保険への加入も検討すると安心でしょう。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

公開日:2025年1月17日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




