詳しい資料はこちら
地域包括支援センターとは?
役割と相談できる内容・利用方法
地域包括支援センターは、高齢者の生活に関する総合相談窓口です。
名前を聞いたことはあっても、「何をする場所だろう?」「どのようなことを相談できるの?」と具体的な利用方法を知らない方も多いのではないでしょうか。
当記事では、地域包括支援センターの役割やサポートをする専門家を紹介します。併せて、地域包括支援センターに相談できることや利用方法も詳しく解説しますので、介護予防や介護サービスに関心のある方は、ぜひ参考にしてください。
詳しい資料はこちら
「地域包括支援センター」とは?

現在、地域包括支援センターは全国に5,451カ所(支所を含めると7,362カ所)設置されており(令和6年4月末現在)、相談は無料です。
なお、地域包括支援センターの名称は各市区町村で異なる場合があります。例えば、東京都の場合、江東区では「長寿サポートセンター」、北区では「高齢者あんしんセンター」と呼ばれています。
地域包括支援センターの4つの役割
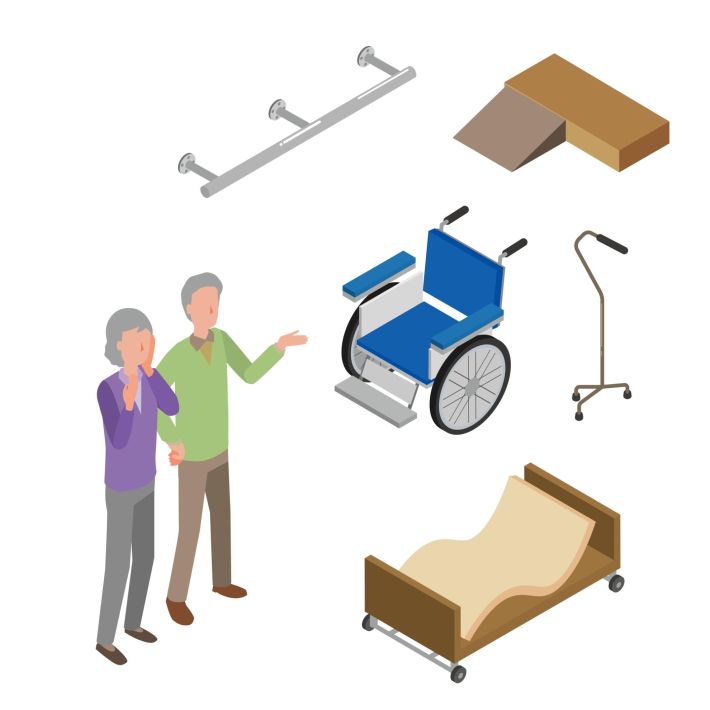
-
総合相談支援
-
権利擁護
-
包括的・継続的ケアマネジメント
-
介護予防ケアマネジメント
1.総合相談支援
ほかにも、要介護認定の申請や介護サービスの手続きなどのサポートや、支援を必要とする高齢者のもとを訪問する「アウトリーチ」も地域包括支援センターの役割です。
2.権利擁護
また、成年後見人制度の紹介など、判断能力や体力が低下した高齢者も安心して暮らせるようサポートしています。
3.包括的・継続的ケアマネジメント
高齢者への支援を充実させるためには、関係機関との協力体制を強化することやケアマネジャーへの支援体制づくりが大切です。
4.介護予防ケアマネジメント
具体的には、要支援1・2と認定された方を対象とした、介護予防ケアプランの作成支援・介護予防サービスの案内などです。また、今後介護や支援が必要になる可能性が高い方には、健康教室の実施などもしています。
地域包括支援センターに在籍する専門家
保健師
●ケアプランの作成
●相談業務
●健康管理や保健指導
●介護予防に役立つ情報の提供
●健康づくり教室などの開催
要支援1・2に認定された方の介護予防のケアプラン作成は保健師にとって大切な業務です。高齢者本人や家族からの要望を踏まえて、適切なサービスを受けられるようにプランを作成します。
また、保健師は看護師資格も保有しており、医療知識を必要とする相談でも活躍しています。
主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)
●ケアマネジャーの指導・相談
●ケアプラン作成の支援
●支援が難しい事例への助言
●地域ケア会議の開催
ケアマネジャーの相談先になったり、地域の関係機関との連携を支援したりと、地域で活躍するケアマネジャーがより活動しやすいようサポートを行っています。
社会福祉士
●高齢者の生活に関する相談・対応
●高齢者虐待に関する相談・対応
●消費者被害に関する相談・対応
●成年後見人制度の利用援助
必要に応じて、公的制度や地域にある団体、サービスなど、関係各所と連携しながら高齢者の暮らしを支えています。
地域包括支援センターで相談できること

【地域包括支援センターに寄せられた相談と対応事例
|
相談内容 |
対応 |
|
高齢による足腰の衰えで、最近家事をするのが難しくなった |
職員が自宅訪問し、訪問介護の生活援助を提案した |
|
父親が入院しており、一人暮らしなので退院後の生活が心配 |
相談員がケアマネジャーを紹介すると同時に、介護サービスを利用するための申請も進めた |
|
家族の物忘れの症状がひどくなったが、病院の受診を拒まれて困っている |
相談員が本人と面会。医療機関やデイサービス職員とも連携し、通院やデイサービスの利用までをサポートした |
|
近所で一人暮らしをする高齢の親族が心配 |
職員が自宅を訪問。地域住民や医療・介護職と連携して、定期的な見守りや受診の支援を手配した |
|
高齢者が虐待を受けている可能性があるがどうしたらよいか |
職員が自宅訪問し虐待があったことを確認。介護負担によるストレスが要因と判断し、介護施設への入居を提案。必要な手続きをサポートした |
地域包括支援センターの利用方法
利用対象者
●対象地域に住む65歳以上の高齢者
●高齢者の家族や親族
●高齢者支援にかかわっている人(介護スタッフなど)
地域包括支援センターは、対象地域に住む65歳以上の方であれば、要介護認定の有無などの制限なく利用できます。なお、高齢者の家族が利用する場合は、高齢者本人が住む地域の地域包括支援センターを利用する必要がありますので、注意が必要です。
利用の流れ
-
自分が居住する地域の地域包括支援センターを調べる
-
来所または電話で相談する
-
家族や本人と担当者が面談する(来所もしくは自宅訪問)
-
相談内容に応じて必要なサービスや事業所の紹介を受ける
電話連絡をすると、対応した職員がヒアリングして担当する専門家を決定します。その後、本人や家族との面談を経て、必要なサービスや事業所の紹介などを受けられます。
地域包括支援センターを活用し、住み慣れた家で安心して暮らそう
地域包括支援センターは、高齢者が安心して暮らせるよう、あらゆる困りごとに関する相談を受け付けている総合相談窓口です。主任ケアマネジャーや保健師、社会福祉士などの専門家が、悩みに対する解決方法の提案や必要なサービスの紹介をしてくれます。
利用対象者は65歳以上の方とその家族や親族、高齢者支援にかかわる人です。困りごとがある方は、地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

公開日:2025年4月8日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




