詳しい資料はこちら
公的介護保険の給付制限とは?
制限がかかる理由と措置を受けた際の対処方法
介護保険料は、将来介護サービスを受けるために欠かさず納めるべき費用です。一方で、支払いを忘れたり、経済的な事情で滞納してしまったりすると「サービスが使えなくなるのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
実際に、介護保険料を滞納すると介護サービスの利用時に給付制限がかかり、一時的に介護サービスの費用を全額自己負担しなくてはならない場合があります。結果として、家計や生活に大きな影響が出ることもあります。
本記事では、公的介護保険の給付制限の内容や制限によって困ること、制限措置を受けた場合の対処法、予防策について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
公的介護保険の「給付制限」

公的介護保険の「給付制限」とは、介護保険料を一定期間以上滞納した場合に、通常の給付を受けられなくなる措置です。介護サービス利用時は一時的にサービス費用を全額自己負担するほか、給付の減額や差し止めなどの制限がかかる場合があります。これらの措置は、滞納期限の長さに応じて段階的に適用されます。
給付制限が設けられている理由は、公的介護保険を公平に運営するためです。公的介護保険は、加入者全員が保険料を出し合って支え合う「相互扶助」で成り立っています。誰かが滞納すると、その負担がほかの加入者におよぶおそれがあり、制度全体の信頼性にも影響します。給付制限は、制度を健全に保つための重要な措置といえます。
給付制限が設けられている理由は、公的介護保険を公平に運営するためです。公的介護保険は、加入者全員が保険料を出し合って支え合う「相互扶助」で成り立っています。誰かが滞納すると、その負担がほかの加入者におよぶおそれがあり、制度全体の信頼性にも影響します。給付制限は、制度を健全に保つための重要な措置といえます。
介護保険料の納め方

介護保険料は、年齢や年金支給額などによって「特別徴収」または「普通徴収」で納付します。ここでは、それぞれの納付方法について解説します。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の納め方
65歳以上の方は公的介護保険制度の第1号被保険者に区分されます。保険料の納付方法は2種類です。
特別徴収
特別徴収とは、公的年金から介護保険料が自動的に差し引かれる仕組みのことです。納付書による支払い手続きが不要なため、納め忘れの心配がありません。
対象となるのは、年金を受給している65歳以上で、年金支給額が年額18万円以上の方です。偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年金支給時に、2カ月分ずつ介護保険料が差し引かれます。
ただし、年度途中で65歳を迎えた方や、年金額が条件を満たさない方などは、一時的に普通徴収へ切り替わることがあります。
対象となるのは、年金を受給している65歳以上で、年金支給額が年額18万円以上の方です。偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年金支給時に、2カ月分ずつ介護保険料が差し引かれます。
ただし、年度途中で65歳を迎えた方や、年金額が条件を満たさない方などは、一時的に普通徴収へ切り替わることがあります。
普通徴収
普通徴収とは、市区町村から送付される納付書を使って、ご自身で介護保険料を納める仕組みです。金融機関やコンビニエンスストアなどで支払えるほか、口座振替を利用することもできます。
対象となるのは、年金支給額が年額18万円未満の方や、年度途中で65歳になった方などです。年間で複数回に分けて支払いますが、自治体によって支払い回数や納付書の発送時期、支払期日は異なります。
なお、口座振替の対象は普通徴収の方のみで、特別徴収(年金天引き)の方は手続き不要です。
対象となるのは、年金支給額が年額18万円未満の方や、年度途中で65歳になった方などです。年間で複数回に分けて支払いますが、自治体によって支払い回数や納付書の発送時期、支払期日は異なります。
なお、口座振替の対象は普通徴収の方のみで、特別徴収(年金天引き)の方は手続き不要です。
第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料の納め方
40歳~64歳までの第2号被保険者は、加入している国民健康保険や健康保険組合の保険料と合わせて介護保険料が徴収されます。
65歳を迎えた際に一時的に普通徴収となるため、納め忘れることがないように注意しましょう。
65歳を迎えた際に一時的に普通徴収となるため、納め忘れることがないように注意しましょう。
給付制限の内容は3種類
介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて段階的な制限が設けられます。ここでは、滞納期間ごとに適用される3つの措置を解説します。
なお、以下は一般的な内容であり、自治体によって運用が異なる場合があります。不明点は事前に確認しましょう。
なお、以下は一般的な内容であり、自治体によって運用が異なる場合があります。不明点は事前に確認しましょう。
納付期限から1年以上滞納|償還払い
介護保険料を1年以上滞納した場合、給付方法が「償還払い」に切り替えられます。
償還払いとは、一時的に介護サービスの費用を全額自己負担(10割)し、後日申請により保険給付分として9~7割が払い戻される仕組みです。
払い戻しを受けるには、介護サービス利用時の領収書などを添えて、自治体の介護保険担当窓口で手続きを行う必要があります。払い戻しは受けられますが、一時的な負担が大きく、経済的影響が出やすい措置です。
償還払いとは、一時的に介護サービスの費用を全額自己負担(10割)し、後日申請により保険給付分として9~7割が払い戻される仕組みです。
払い戻しを受けるには、介護サービス利用時の領収書などを添えて、自治体の介護保険担当窓口で手続きを行う必要があります。払い戻しは受けられますが、一時的な負担が大きく、経済的影響が出やすい措置です。
納付期限から1年6カ月以上滞納|給付の差し止め
介護保険料を1年6カ月以上滞納した場合、償還払いに加えて「給付の差し止め」が行われる場合があります。
これは、介護保険給付の一部または全部を一時的に停止する措置です。差し止めにより保険料の滞納分が充当されるため、払い戻しの申請をしても、本来の償還分の全額は受け取れません。
これは、介護保険給付の一部または全部を一時的に停止する措置です。差し止めにより保険料の滞納分が充当されるため、払い戻しの申請をしても、本来の償還分の全額は受け取れません。
納付期限から2年以上滞納|給付の減額・自己負担増加
介護保険料の滞納が2年以上続くと、自己負担割合が通常より引き上げられる「給付の減額」措置が行われます。
具体的には、自己負担が3割(所得が一定以上の人は最大4割)となる措置です。また、「高額介護(予防)サービス費」といった一部サービスの支給を受けられなくなります。長期滞納による給付制限は生活への影響が大きく、早めの納付や自治体への相談が重要です。
具体的には、自己負担が3割(所得が一定以上の人は最大4割)となる措置です。また、「高額介護(予防)サービス費」といった一部サービスの支給を受けられなくなります。長期滞納による給付制限は生活への影響が大きく、早めの納付や自治体への相談が重要です。
公的介護保険の給付制限を受けると困ることとは?
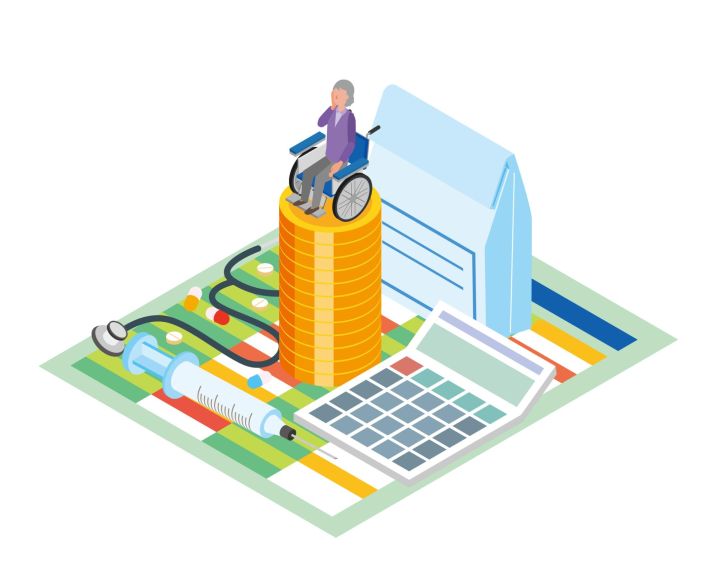
給付制限が適用されると、利用者や家族にさまざまな負担が生じます。経済的な影響だけでなく、手続き上の手間や制度の制限によって、日常生活に支障をきたすこともあります。
ここでは、給付制限によって生じるおもな問題を解説します。
ここでは、給付制限によって生じるおもな問題を解説します。
サービス代が一時的に全額自己負担になる
介護保険料の滞納期間が1年を超えると「償還払い」が適用され、介護サービスの費用を一時的に全額自己負担(10割)する必要があります。
通常であれば1~3割の自己負担で済むため、一時的とはいえ家計への影響は大きいでしょう。保険料を追納するなどし、短期間で制限が解除された場合でも、介護サービスを継続的に利用している世帯では資金繰りが厳しくなることがあります。
通常であれば1~3割の自己負担で済むため、一時的とはいえ家計への影響は大きいでしょう。保険料を追納するなどし、短期間で制限が解除された場合でも、介護サービスを継続的に利用している世帯では資金繰りが厳しくなることがあります。
償還払いの事務負担がかかる
償還払いの措置を受けた場合、給付分の払い戻しを受けるには、介護サービス利用後に申請手続きを行う必要があります。
手続きの際は、領収書やサービス提供証明書、ケアプラン、給付管理票などの複数の書類をそろえて、自治体の介護保険担当窓口に提出しなければなりません。こうした準備や管理には手間がかかり、申請内容に不備があると払い戻しが遅れたり却下されたりする場合もあります。
経済面だけでなく、事務的な負担が増す点も給付制限の大きなデメリットです。
手続きの際は、領収書やサービス提供証明書、ケアプラン、給付管理票などの複数の書類をそろえて、自治体の介護保険担当窓口に提出しなければなりません。こうした準備や管理には手間がかかり、申請内容に不備があると払い戻しが遅れたり却下されたりする場合もあります。
経済面だけでなく、事務的な負担が増す点も給付制限の大きなデメリットです。
2年を超えると自己負担割合が増える
介護保険料の滞納が2年以上続くと、自己負担割合が引き上げられる措置が取られます。
加えて、「高額介護(予防)サービス費」などの支給を受けられなくなるため、実質的な支出額が大幅に増える点も見逃せません。
こうした負担が長期化すると、介護サービスの継続利用自体が難しくなるおそれがあります。
加えて、「高額介護(予防)サービス費」などの支給を受けられなくなるため、実質的な支出額が大幅に増える点も見逃せません。
こうした負担が長期化すると、介護サービスの継続利用自体が難しくなるおそれがあります。
公的介護保険の給付制限措置を受けた場合の対処法
給付制限を解除するには、滞納を解消するか、正式な手続きが必要です。制限を受けたままにしておくと、自己負担が増えるほか、必要なサービスが受けられなくなるおそれがあります。
ここでは、給付制限を解除するためのおもな対処法を紹介します。
ここでは、給付制限を解除するためのおもな対処法を紹介します。
滞納保険料を完納する
介護保険料を滞納している場合は、未納分をすべて納めることが基本です。
滞納期間が2年未満であれば、完納によって原則として給付制限は解除されます。また、納付が進み未納額が大幅に減少した場合でも、自治体の判断で制限が解除されるケースがあります。
災害や病気、失業などのやむを得ない事情で納付が難しい場合は、政令に基づく特例により解除されることもあります。まずは、自治体の介護保険担当窓口に相談し、自身の状況に応じた対応を確認しましょう。
滞納期間が2年未満であれば、完納によって原則として給付制限は解除されます。また、納付が進み未納額が大幅に減少した場合でも、自治体の判断で制限が解除されるケースがあります。
災害や病気、失業などのやむを得ない事情で納付が難しい場合は、政令に基づく特例により解除されることもあります。まずは、自治体の介護保険担当窓口に相談し、自身の状況に応じた対応を確認しましょう。
措置解除申請を行う
やむを得ない理由で介護保険料を滞納した場合は、「給付制限措置解除申請」によって制限を解除できる可能性があります。
申請は自治体の介護保険担当窓口で行い、「給付制限措置解除申請書」を提出する必要があります。審査の結果、要件を満たせば給付制限が解除される仕組みです。
自治体によっては納付状況を示す書類(領収書や納付証明書など)の提出が求められる場合もあります。事前に確認してから手続きを進めましょう。
申請は自治体の介護保険担当窓口で行い、「給付制限措置解除申請書」を提出する必要があります。審査の結果、要件を満たせば給付制限が解除される仕組みです。
自治体によっては納付状況を示す書類(領収書や納付証明書など)の提出が求められる場合もあります。事前に確認してから手続きを進めましょう。
介護保険料を滞納しないための予防策
介護保険料を滞納すると、将来的に介護サービスの給付制限を受けるおそれがあります。こうした影響を回避するには、日頃から無理なく支払える仕組みを整えておくことが大切です。
ここでは、介護保険料を滞納しないための予防策を2つ紹介します。
ここでは、介護保険料を滞納しないための予防策を2つ紹介します。
口座引き落としを設定する
支払い忘れや納付書の紛失を防ぐには、口座引き落としの登録が効果的です。自動的に保険料が引き落とされるため、納め忘れの心配がなく、安定して支払いを続けられます。また、引き落とし日を把握しておくことで、計画的に資金管理をしやすくなる点もメリットです。
金融機関窓口やコンビニエンスストアでの納付も可能ですが、多くの自治体では口座引き落としを推奨しています。
手続きは自治体の窓口や金融機関で行えるほか、Webや郵送での申し込みに対応している自治体もあります。窓口で行う場合は、預金通帳と届出印、被保険者番号がわかる書類などが必要となるため、事前に準備しておきましょう。
金融機関窓口やコンビニエンスストアでの納付も可能ですが、多くの自治体では口座引き落としを推奨しています。
手続きは自治体の窓口や金融機関で行えるほか、Webや郵送での申し込みに対応している自治体もあります。窓口で行う場合は、預金通帳と届出印、被保険者番号がわかる書類などが必要となるため、事前に準備しておきましょう。
支払い困難時は早めに相談する
経済的な事情で支払いが難しい場合でも、滞納のまま放置せず、早めに自治体へ相談することが大切です。相談の結果によっては、分割納付(分納)や徴収猶予、減免制度などが適用されることがあります。
滞納期間が短いうちに相談することで、給付制限措置自体を回避できる可能性もあるでしょう。一方で、給付制限を受けてからでは、手続きや審査に時間がかかり、介護サービスの利用にも影響するおそれがあります。支払いに不安を感じた時点で、速やかに自治体へ相談しましょう。
滞納期間が短いうちに相談することで、給付制限措置自体を回避できる可能性もあるでしょう。一方で、給付制限を受けてからでは、手続きや審査に時間がかかり、介護サービスの利用にも影響するおそれがあります。支払いに不安を感じた時点で、速やかに自治体へ相談しましょう。
介護保険料を忘れず納付し、困難時は早めに窓口に相談しよう
介護保険料を滞納すると、「償還払い」や「給付の差し止め」、「自己負担割合の増加」などの給付制限が段階的に適用される場合があります。これは、制度を公平に維持するための仕組みですが、利用者にとっては経済的な負担が大きく、生活に影響するおそれもあります。
滞納を防ぐには、口座引き落としの登録や早めの相談が大切です。支払いが難しくなった場合でも、放置せず自治体へ相談すれば、分納や減免などの救済制度を受けられる可能性があります。
介護保険料を計画的に納め、安心して介護サービスを利用するためにも、困ったときは早めの相談を心がけましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
CFP 齋藤 彩

急性期総合病院において薬剤師として勤める中、がん患者さんから「治療費が高くてこれ以上治療を継続できない」と相談を受けたことを機にお金の勉強を開始。ひとりの人を健康とお金の両面からサポートすることを目標にファイナンシャルプランナーとなることを決意。現在は個人の相談業務・執筆活動を行っている。
資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)
資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)
公開日:2025年11月12日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




