スマホ認知症とは?
原因やおもな症状・危険性・対処法
スマートフォンが生活に欠かせない時代になっているなか、「スマホ認知症」と呼ばれる症状に悩む人が増えています。
スマホ認知症はスマートフォンの使用により脳が疲労し、認知症と似た症状が出ている状態です。物忘れや集中力、記憶力の低下などの症状が出てしまい、そのまま放置していると日常生活で大きな影響が出る可能性があります。
スマホ認知症にならないためには、スマートフォンの使用方法を見直すなどの対応が必要です。スマホ認知症についての知識を深め、症状が現れないように生活習慣を改善しましょう。
当記事ではスマホ認知症の概要や原因、おもな症状、危険性、スマホ認知症にならないために気を付けたいポイントを解説します。
20代・30代も注意すべき「スマホ認知症」
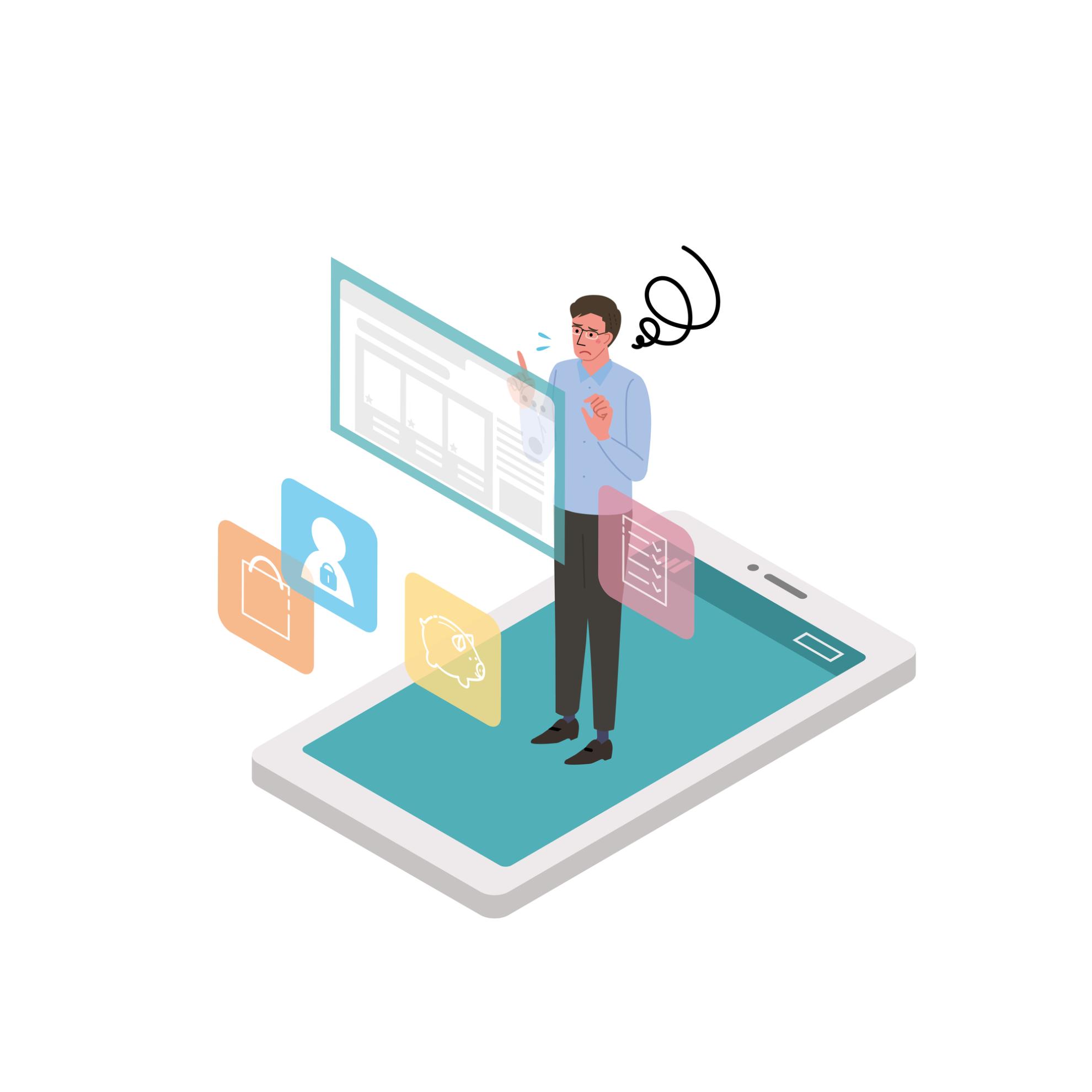
脳の認知機能が下がって社会生活に支障が出ている症状が「認知症」です。そして、スマートフォンの使用により日々膨大に入ってくるようになった情報の整理に脳が疲労し、認知症と似たような状態に陥るのが「スマホ認知症」です。
スマホ認知症は医学的に認められた正式な病名ではありませんが、スマートフォンを頻繁に使用する方は、気を付けたほうがよいでしょう。
なお、認知症有病者の多くは高齢者ですが、スマホ認知症は20代や30代などの若い世代でも発症する可能性があります。生活に大きな支障が出る前に、適切な対応を知っておきましょう。
スマホ認知症は医学的に認められた正式な病名ではありませんが、スマートフォンを頻繁に使用する方は、気を付けたほうがよいでしょう。
なお、認知症有病者の多くは高齢者ですが、スマホ認知症は20代や30代などの若い世代でも発症する可能性があります。生活に大きな支障が出る前に、適切な対応を知っておきましょう。
スマホ認知症の原因
スマホ認知症のおもな原因は、特に目的もなくスマートフォンを見続ける「だらだらスマホ」や、スマートフォンを使いながら何か別のことをする「ながらスマホ」による脳疲労です。
脳は入力・整理・取り出しの3つの工程で情報を処理しています。ところが、スマートフォンによって膨大な情報が脳に入り続けると、脳の前頭葉が疲れてしまい、情報が整理されない状態に陥ります。結果として、脳の情報処理能力が低下し、認知症と同様の症状が出るのです。
また、就寝前にスマートフォンを使用することで睡眠の質が悪化するなど、生活リズムの乱れもスマホ認知症の原因とされています。
脳は入力・整理・取り出しの3つの工程で情報を処理しています。ところが、スマートフォンによって膨大な情報が脳に入り続けると、脳の前頭葉が疲れてしまい、情報が整理されない状態に陥ります。結果として、脳の情報処理能力が低下し、認知症と同様の症状が出るのです。
また、就寝前にスマートフォンを使用することで睡眠の質が悪化するなど、生活リズムの乱れもスマホ認知症の原因とされています。
スマホ認知症のおもな症状
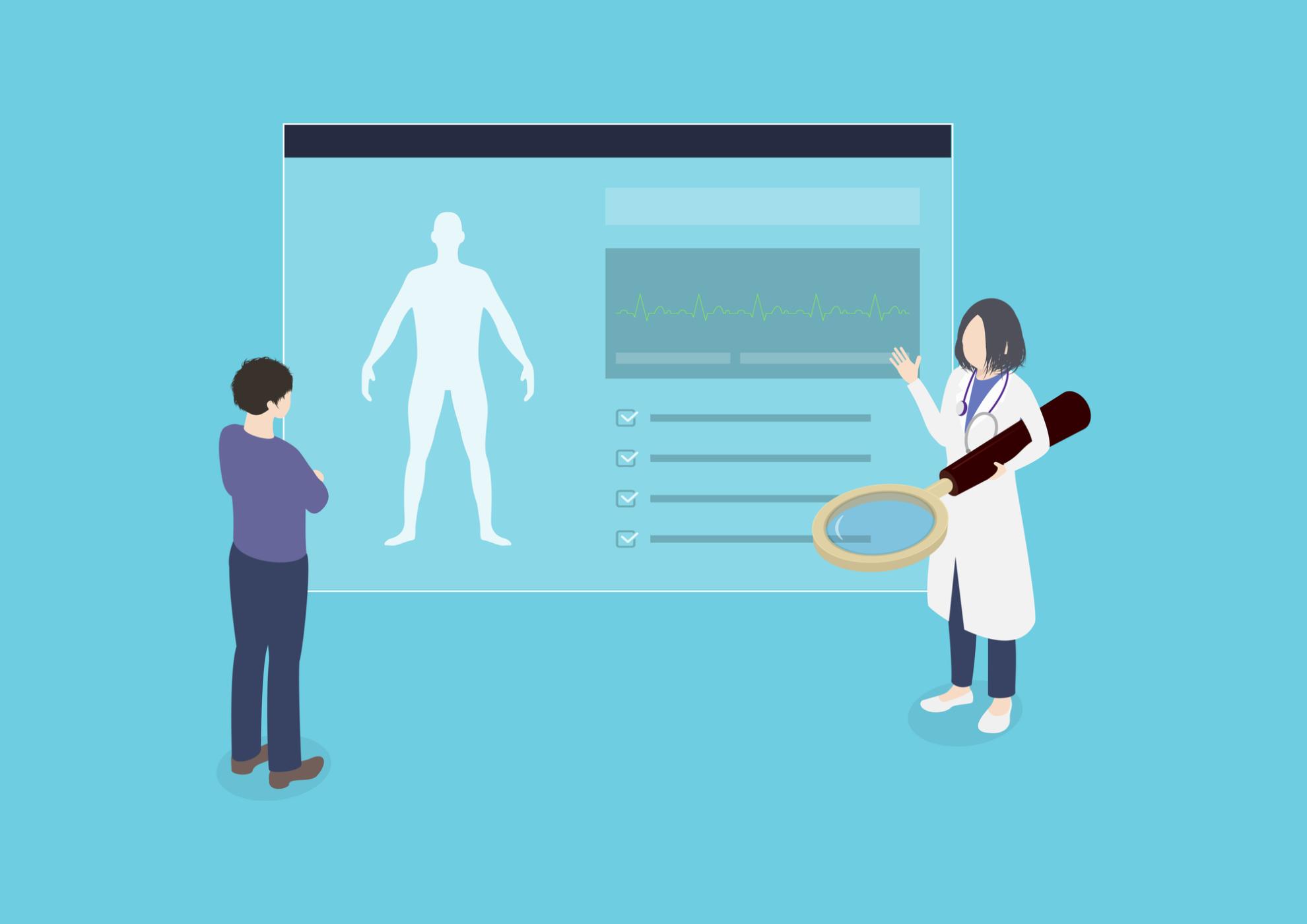
スマホ認知症ではおもに以下のような症状が現れます。心あたりのある症状がないかチェックしてみましょう。
-
コミュニケーション能力の低下
-
記憶力の低下
-
注意散漫・集中力の低下
-
創造力の低下
-
実行力の低下
-
情緒不安定・体調不良
コミュニケーション能力の低下
伝えたいことをうまく言語化できない、気の利いた受け答えができない、受け取った言葉を理解するのに時間がかかるなどの症状が現れます。
また、スマートフォンの使用により対人コミュニケーションの機会が減少していると、身ぶりや手ぶりといった非言語のコミュニケーション能力も低下しがちです。
また、スマートフォンの使用により対人コミュニケーションの機会が減少していると、身ぶりや手ぶりといった非言語のコミュニケーション能力も低下しがちです。
記憶力の低下
記憶力が低下し、物忘れが頻繁に発生します。新しいことを覚えられないだけでなく、昔のことを思い出せなくなり、生活や仕事に支障が出ます。
人の名前が思い出せない、漢字が思い出せない、思い出すのに時間がかかるようになったなど、物忘れがひどくなったと感じたら、スマートフォンの使用頻度や方法を見直してみるのもよいでしょう。
人の名前が思い出せない、漢字が思い出せない、思い出すのに時間がかかるようになったなど、物忘れがひどくなったと感じたら、スマートフォンの使用頻度や方法を見直してみるのもよいでしょう。
注意散漫・集中力の低下
一つのことに集中できない、集中力が続かないといった症状が現れます。深く考えられず仕事や勉強、日常生活に支障をきたし、想定したような結果を得られないほか、単純作業をしていてもミスが発生しやすくなります。
ミスが重なるとモチベーションも低下してしまい、さまざまなことにやる気が起きなくなるでしょう。また、注意力散漫と集中力の低下は細かいミスを引き起こすだけでなく、大きな事故にも発展する可能性があります。
ミスが重なるとモチベーションも低下してしまい、さまざまなことにやる気が起きなくなるでしょう。また、注意力散漫と集中力の低下は細かいミスを引き起こすだけでなく、大きな事故にも発展する可能性があります。
創造力の低下
ひらめきやアイデアが生まれず、簡単な作業で手間取ったり、効率良く作業を進められなくなったりします。できる限り脳を使わずに済ますために楽をしようとし、工夫したりチャレンジしたりすることを避ける傾向も出ます。
実行力の低下
計画どおりに作業を進められない、段取りを考えられないといった症状も現れます。例えば、これまで1時間でできていた作業に数時間かかるようになり、結果が出せなくなるといったことが起こります。
また、スマホ認知症はスマホ依存との関係も深く、スマホ依存によってやる気が起きないといった症状が現れます。一日中スマートフォンのことを考えてしまい、スマートフォンが手元にないと落ち着かず、いつまでもスマートフォンを見ていたいと考えるようになってしまうのです。
また、スマホ認知症はスマホ依存との関係も深く、スマホ依存によってやる気が起きないといった症状が現れます。一日中スマートフォンのことを考えてしまい、スマートフォンが手元にないと落ち着かず、いつまでもスマートフォンを見ていたいと考えるようになってしまうのです。
情緒不安定・体調不良
前頭葉は感情をつかさどる器官でもあるため、前頭葉が疲労すると感情をコントロールするのが難しくなります。わけもなくイライラしたり、怒りっぽくなったり、涙もろくなったりするなどの症状が出ます。
スマートフォンの使用過多により生活リズムが乱れ、体調を崩しやすくなるのもスマホ認知症の症状の一つです。昼間に眠くなったり夜になかなか眠れなかったりといった症状が現れ、さらなる疾患へと発展する可能性もあります。
スマートフォンの使用過多により生活リズムが乱れ、体調を崩しやすくなるのもスマホ認知症の症状の一つです。昼間に眠くなったり夜になかなか眠れなかったりといった症状が現れ、さらなる疾患へと発展する可能性もあります。
スマホ認知症の危険性
スマホ認知症は日常生活に影響を与えるだけでなく、睡眠負債を招いたり、将来の認知症リスクを高めたりといった危険性も持っています。症状が悪化する前に、早めに対策をとりましょう。
睡眠障害や睡眠負債を招くおそれがある
スマートフォンから発せられるブルーライトを、寝る前や夜間に浴びると睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、脳が夜を昼と勘違いしてしまい、体内時計のリズムが乱れます。
生活リズムが乱れて睡眠の量や質が低下すると、不眠症などの睡眠障害になる可能性が高まります。慢性的な睡眠不足が続くと、睡眠負債になる可能性もあり、精神的・肉体的な不調をきたしてしまうかもしれません。
【睡眠負債が引き起こす症状】
生活リズムが乱れて睡眠の量や質が低下すると、不眠症などの睡眠障害になる可能性が高まります。慢性的な睡眠不足が続くと、睡眠負債になる可能性もあり、精神的・肉体的な不調をきたしてしまうかもしれません。
【睡眠負債が引き起こす症状】
-
免疫力の低下
-
肥満
-
情緒不安定
-
抑うつ状態 など
将来の認知症リスクが高まる
スマホ認知症は睡眠負債だけでなくうつ病も合併しやすく、これらの病気は将来的な認知症のリスクを高めます。スマホ認知症を早期に改善することが将来の認知症リスクの抑制につながります。
認知症は根本的な治療が難しく、現代の医療技術では完治しません。一部の症状の進行を遅らせることはできても、元の生活に完全に戻ることはできないのです。
しかし、スマホ認知症は認知症のような症状が出ているだけで、改善の余地があります。スマホ認知症の危険性に気付き、可能な限り早く生活習慣を改善していく必要があるといえるでしょう。
認知症は根本的な治療が難しく、現代の医療技術では完治しません。一部の症状の進行を遅らせることはできても、元の生活に完全に戻ることはできないのです。
しかし、スマホ認知症は認知症のような症状が出ているだけで、改善の余地があります。スマホ認知症の危険性に気付き、可能な限り早く生活習慣を改善していく必要があるといえるでしょう。
スマホ認知症かチェックしてみよう
ここまでスマホ認知症の症状や危険性について解説してきましたが、スマホ認知症かどうか判断するにはどうすれば良いのでしょうか。
スマホ認知症の可能性がある症状の簡単なチェックリストを紹介します。ご自身に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
スマホ認知症の可能性がある症状の簡単なチェックリストを紹介します。ご自身に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
-
就寝前にスマートフォンを使い、眠れないことがある
-
外出先だけでなく家のなかでもスマートフォンを肌身離さず持ち歩いている
-
スマートフォンの通知が気になって落ち着かない
-
会話中に言葉が出てこないことがある
-
新しいことを覚えたり、昔のことを思い出したりするのが難しくなった
-
漢字が書けない、簡単な計算を間違えることが増えた
-
情緒不安定だと感じる
-
以前より集中力が続かなくなった
以上の項目に当てはまるものが多い方は注意が必要です。ただし、このチェックリストはあくまで簡易なものであるため、気になる症状がある方や、より詳しく知りたい方は専門機関を受診ください。
スマホ認知症にならないために!予防法5つ

スマホ認知症を予防するために気を付けたいポイントを5つ解説します。スマートフォンとの付き合い方を見直して、スマホ認知症になるリスクを減らしましょう。
-
スマートフォンの使用時間を見直す
-
スマートフォンに頼りすぎない
-
デジタルデトックスを行う
-
直接的なコミュニケーションを重視する
-
良質な睡眠をとる
スマートフォンの使用時間を見直す
スマートフォンと適度に付き合うために、まずは、スマートフォンをどれくらい使用しているか把握し、不必要な使用がないか見直しましょう。長時間は使用していないと感じていても、実際に時間を計測すると、想像以上にスマートフォンを使いすぎているかもしれません。
スマートフォンの使用時間に問題があれば、スマートフォンを使用するルールを設定し、使用時間を制限しましょう。
スマートフォンは1日○時間まで、連絡以外でスマートフォンを使わない、寝る前はスマートフォンを使わないなど、具体的にルールを決めておくと使用を制限しやすくなります。スマートフォンに備わっているアプリの時間制限機能なども使うとよいでしょう。
ただし、使用時間を急に厳しく制限してしまうと、余計なストレスがかかったり、目標を達成できずルールがおざなりになったりする可能性があります。無理なく習慣を変えるために段階的に生活を改善させましょう。
スマートフォンの使用時間に問題があれば、スマートフォンを使用するルールを設定し、使用時間を制限しましょう。
スマートフォンは1日○時間まで、連絡以外でスマートフォンを使わない、寝る前はスマートフォンを使わないなど、具体的にルールを決めておくと使用を制限しやすくなります。スマートフォンに備わっているアプリの時間制限機能なども使うとよいでしょう。
ただし、使用時間を急に厳しく制限してしまうと、余計なストレスがかかったり、目標を達成できずルールがおざなりになったりする可能性があります。無理なく習慣を変えるために段階的に生活を改善させましょう。
スマートフォンに頼りすぎない
スマートフォンがあると、思い出せないことや知りたいことをすぐに検索してしまいがちです。
思い出すことや自分で考えることも脳にとっては重要な作業であり、脳の活性化にもつながります。調べたいことがあってもすぐにスマートフォンで検索するのを控え、本で調べる、人に聞くなど、スマートフォンで調べる以外の解決策をとってみましょう。
思い出すことや自分で考えることも脳にとっては重要な作業であり、脳の活性化にもつながります。調べたいことがあってもすぐにスマートフォンで検索するのを控え、本で調べる、人に聞くなど、スマートフォンで調べる以外の解決策をとってみましょう。
デジタルデトックスを行う
スマートフォンの使用を制限していても、ついつい時間を守れないこともあるでしょう。そのような場合は、スマートフォンを持たずに過ごしたり、電波の届かない場所で過ごしたりするなどして、一定期間スマートフォンとの接触を断つのもおすすめです。
スマートフォンなどのデジタル機器から離れて、心身の疲労を回復することを「デジタルデトックス」と呼びます。デジタルデトックスをすることで、脳疲労の回復だけでなく、睡眠や仕事、勉強の質の向上も期待できます。
ただし、デジタルデトックス中は外部との連絡手段が限られてしまいます。家族など周囲の人に協力してもらい、何かあれば直接伝えてもらうなどの対策をとりましょう。身近に協力者がいない場合は、デジタルデトックスを行うイベントやツアーを実施している企業もあるので、それらに参加するのも一手です。
スマートフォンなどのデジタル機器から離れて、心身の疲労を回復することを「デジタルデトックス」と呼びます。デジタルデトックスをすることで、脳疲労の回復だけでなく、睡眠や仕事、勉強の質の向上も期待できます。
ただし、デジタルデトックス中は外部との連絡手段が限られてしまいます。家族など周囲の人に協力してもらい、何かあれば直接伝えてもらうなどの対策をとりましょう。身近に協力者がいない場合は、デジタルデトックスを行うイベントやツアーを実施している企業もあるので、それらに参加するのも一手です。
直接的なコミュニケーションを重視する
人との対話は脳の活性化を促します。直接的なコミュニケーションでは、話す内容を考える、相手の話を聞いて理解する、相手の表情を読む、気持ちを理解するといったさまざまな面で脳が働いています。
スマートフォンで連絡するだけではなく、直接人と会って話す機会も増やしましょう。
スマートフォンで連絡するだけではなく、直接人と会って話す機会も増やしましょう。
良質な睡眠をとる
良質な睡眠は脳の機能を回復させるために欠かせません。睡眠の質を上げる方法は以下のようなものがあります。とり入れやすいものから実践してみましょう。
-
生活スケジュールを見直す
-
適度な運動を行う
-
朝は太陽の光を浴びる
-
食事は1日3回、栄養バランスを考えてとる
-
睡眠に適した環境をつくる
-
入浴は就寝2~3時間前には済ませる
-
寝る前にスマートフォンやパソコンを使わない
スマートフォンの使用方法を見直してスマホ認知症を予防しよう
スマホ認知症は、スマートフォンの使用で生じる脳疲労を原因としています。記憶力や集中力、実行力、コミュニケーション能力の低下など、スマホ認知症の症状は幅広く、そのどれもが生活に悪影響をもたらします。
さらに、スマホ認知症は睡眠不足や睡眠負債、うつ病とも関係しており、将来的な認知症のリスクを高めます。
スマートフォンは生活に欠かせませんが、付き合い方を誤るとだれでもスマホ認知症になる可能性があります。今回紹介したスマホ認知症のチェックリストや予防法を参考に、日々の生活を見直し、改善していきましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
別府 拓紀[医師]

産業医科大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院、市中病院、企業の専属産業医などを経て、現在は市中病院で地域の精神科医療に従事している。
資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など
資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など
公開日:2024年12月13日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




