詳しい資料はこちら
親や配偶者の介護で家族ができることは?
注意点と介護の負担を軽減する方法
親や配偶者が要介護状態になったとき、「自分に何ができるのだろう」と悩む方は少なくありません。
介護では、食事や入浴などの直接的な介助以外にも、日常生活の手伝いや通院の付き添いといったサポートも必要です。気持ちに寄り添うコミュニケーションなど、家族だからこそできる支え方もあります。
ただし、在宅介護は負担が大きくなりやすいため、介護サービスなどを活用して無理なく続けられる環境を整えることが大切です。
本記事では、介護で家族ができること・できないことや注意点、そして負担を軽減するための方法を紹介します。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
介護で家族ができること

要介護状態になると、自力で日常生活を送ることが難しくなり、さまざまなサポートが必要になります。はじめに、家族ができるサポートを具体的に見ていきましょう。
食事・入浴介助など直接的な介助
入浴、排せつなどの直接的な介助は、家族でも行えます。
入浴や着替えを手伝う際には、安全性やプライバシーに配慮して行いましょう。滑りにくいマットや手すりの設置など、安心できる環境を整えることが大切です。
食事介助では、やわらかく噛みやすい食材を使ったり、誤嚥を防ぐためにとろみを付けたりと、その人の食べる力に合わせた工夫が有効です。
排せつ介助ではトイレへの誘導やおむつ交換、寝たきりであれば褥瘡(じょくそう)を防ぐための定期的な体位変換も必要になります。
服用している薬がある場合は、「お薬カレンダー」を活用すると飲み忘れや重複といったミスを減らせるでしょう。
ただし、どの程度介助が必要になるかは要介護者の状態によって異なります。慣れない段階で介助を無理に行うと事故やケガにつながるおそれもあるため、注意が必要です。
入浴や着替えを手伝う際には、安全性やプライバシーに配慮して行いましょう。滑りにくいマットや手すりの設置など、安心できる環境を整えることが大切です。
食事介助では、やわらかく噛みやすい食材を使ったり、誤嚥を防ぐためにとろみを付けたりと、その人の食べる力に合わせた工夫が有効です。
排せつ介助ではトイレへの誘導やおむつ交換、寝たきりであれば褥瘡(じょくそう)を防ぐための定期的な体位変換も必要になります。
服用している薬がある場合は、「お薬カレンダー」を活用すると飲み忘れや重複といったミスを減らせるでしょう。
ただし、どの程度介助が必要になるかは要介護者の状態によって異なります。慣れない段階で介助を無理に行うと事故やケガにつながるおそれもあるため、注意が必要です。
日常生活を支える手伝い
買い物や料理、洗濯、掃除、ゴミ出しなど、家事のサポートも介護の一部です。特に外出をともなう買い物は、足腰の弱った高齢者には大きな負担となります。
こうした日常生活を家族がサポートすることで、安心して在宅生活を続けられるでしょう。
こうした日常生活を家族がサポートすることで、安心して在宅生活を続けられるでしょう。
外出時の付き添い・見守り
要介護者の状態によっては、バランスを崩しやすく転倒やケガのリスクが高くなります。また外出中に急な体調変化が起こることもあるでしょう。外出や通院の際には、家族の付き添いがあると安心です。
自宅内では、手すりの設置や段差解消など住環境の整備も欠かせません。最近では見守りサービスの利用や見守りカメラの導入も増えていますが、本人が「監視されている」と感じてストレスになることもあります。導入時は本人の意向を尊重しましょう。
自宅内では、手すりの設置や段差解消など住環境の整備も欠かせません。最近では見守りサービスの利用や見守りカメラの導入も増えていますが、本人が「監視されている」と感じてストレスになることもあります。導入時は本人の意向を尊重しましょう。
事務手続き・調整
介護では、要介護認定の申請やケアマネジャーとの打ち合わせ、サービス利用時の契約・調整など、事務手続きも多く発生します。
また、医師や看護師、介護スタッフとの情報共有も必要になるでしょう。
これらを正確に行わないと、必要なサービスを受けられなかったり、費用が増えてしまったりする場合があります。
また、医師や看護師、介護スタッフとの情報共有も必要になるでしょう。
これらを正確に行わないと、必要なサービスを受けられなかったり、費用が増えてしまったりする場合があります。
心に寄り添うコミュニケーション
介護が必要な状態になると、要介護者が不安や孤独を抱えてしまうことも少なくありません。
家族が話を聞いたり、励ましたりすることで気持ちが和らぐこともあります。一緒に趣味を楽しむ、散歩に出掛けるなど、ささやかな時間が心の支えになるでしょう。
家族が話を聞いたり、励ましたりすることで気持ちが和らぐこともあります。一緒に趣味を楽しむ、散歩に出掛けるなど、ささやかな時間が心の支えになるでしょう。
介護で家族ができないことと注意したいこと

家族であっても、介護においてやってはいけない行為もあります。適切な介護を続けるために、注意すべきポイントを確認しておきましょう。
医療行為は専門職のみ行える
注射や点滴などの医療行為は、医師や看護師などの専門職でなければ行えません。
医療行為は専門知識や経験、資格が必要です。家族が独自の判断で行うと、ケガや事故につながる危険があるため、必ず専門職に任せるようにしましょう。
ただし、「痰の吸引」といったその行為なしでは日常生活を送れないような一部の医療的ケアについては、条件を満たせば家族が行える場合もあります。
医療行為は専門知識や経験、資格が必要です。家族が独自の判断で行うと、ケガや事故につながる危険があるため、必ず専門職に任せるようにしましょう。
ただし、「痰の吸引」といったその行為なしでは日常生活を送れないような一部の医療的ケアについては、条件を満たせば家族が行える場合もあります。
尊厳を無視した介護はしない
介護される本人の意思を尊重することは何よりも大切です。
家族側の「やってあげている」という意識が強すぎると、本人の自尊心を傷つけてしまうことがあります。
また、過干渉や子ども扱いは避け、できることは本人に任せる姿勢も忘れないようにしましょう。
家族側の「やってあげている」という意識が強すぎると、本人の自尊心を傷つけてしまうことがあります。
また、過干渉や子ども扱いは避け、できることは本人に任せる姿勢も忘れないようにしましょう。
一人で抱え込まないようにする
「親の介護は自分がやらなければ」という責任感から、無理をしてしまう方もいます。
しかし、睡眠不足や過労、ストレスが続くと、介護者が健康を損ねてしまい、介護自体が難しくなるおそれがあります。一人で限界まで我慢せず、早めに周囲のサポートを求めることが大切です。
しかし、睡眠不足や過労、ストレスが続くと、介護者が健康を損ねてしまい、介護自体が難しくなるおそれがあります。一人で限界まで我慢せず、早めに周囲のサポートを求めることが大切です。
介護の負担を軽減する方法
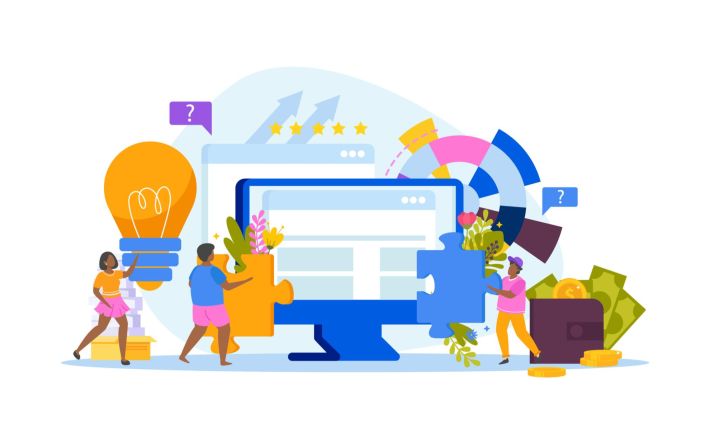
介護は「家族だけが頑張るもの」ではありません。必要な支援を受けながら、続けられる形を見つけることが大切です。
ここでは、介護の負担を減らすための具体的な方法を紹介します。
ここでは、介護の負担を減らすための具体的な方法を紹介します。
まずは相談してみる
各市町村には介護の相談窓口が設置されています。介護で悩んだら、まずは相談窓口を訪れてみましょう。
例えば、「地域包括支援センター」では、保健師や社会福祉士、ケアマネジャーが連携して支援を行っています。介護・医療・福祉の面から総合的にアドバイスを受けられ、必要な制度やサービスを紹介してもらえるでしょう。
「どこに相談すればいいのかわからない」という段階でも問題ありません。まずは一歩踏み出すことが大切です。
例えば、「地域包括支援センター」では、保健師や社会福祉士、ケアマネジャーが連携して支援を行っています。介護・医療・福祉の面から総合的にアドバイスを受けられ、必要な制度やサービスを紹介してもらえるでしょう。
「どこに相談すればいいのかわからない」という段階でも問題ありません。まずは一歩踏み出すことが大切です。
介護サービスを積極的に利用する
要介護認定を受けると、介護の必要性に応じて介護サービスを利用できます。
訪問介護・看護で日常生活のサポートや療養上の世話を受けたり、デイサービスのレクリエーションで他の利用者と交流の時間を持ったりすることも可能です。また、ショートステイを利用すれば、介護者が一時的に休息を取ることもできます。
「助けを求めても良い」と意識を切り替えることが、無理なく介護を続けるためのコツです。
介護サービスの種類・概要は下記記事で解説しています。併せてご覧ください。
介護サービスの種類とは?3つの分類と各サービスの特徴
訪問介護・看護で日常生活のサポートや療養上の世話を受けたり、デイサービスのレクリエーションで他の利用者と交流の時間を持ったりすることも可能です。また、ショートステイを利用すれば、介護者が一時的に休息を取ることもできます。
「助けを求めても良い」と意識を切り替えることが、無理なく介護を続けるためのコツです。
介護サービスの種類・概要は下記記事で解説しています。併せてご覧ください。
介護サービスの種類とは?3つの分類と各サービスの特徴
家族間で役割を分担する
家族が複数人いる場合は話し合い、介護の負担が偏らないように役割を分担しましょう。
仕事の都合や住まいの距離などを考慮しながら、「自分にできること・できないこと」を整理することが大切です。
例えば、「兄は金銭管理」「妹は通院の付き添い」「子どもたちは買い物や掃除」など、明確に分担するとスムーズです。
仕事の都合や住まいの距離などを考慮しながら、「自分にできること・できないこと」を整理することが大切です。
例えば、「兄は金銭管理」「妹は通院の付き添い」「子どもたちは買い物や掃除」など、明確に分担するとスムーズです。
介護費用を軽減できる制度を活用する
介護では、経済的な負担も大きな課題です。上手に制度を活用して費用負担を軽減しましょう。
例えば、介護サービスの自己負担割合は所得に応じて1~3割となっています。さらに所得に応じてひと月当たりの自己負担限度額が定められており、上限を超えた分は高額介護サービス費制度によって払い戻される仕組みです。
また、高額医療・高額介護合算療養費制度を利用すれば、一年間の医療費と介護費の合計が自己負担限度額を超えた場合に超過分が払い戻されます。
上記以外にも、民間の介護保険に加入しておくことで、将来的な経済的負担を軽減できるでしょう。
介護費用を抑える方法は、下記記事でも解説しています。
介護費用を抑える方法は?7つの税金控除と負担軽減の制度・補助金
例えば、介護サービスの自己負担割合は所得に応じて1~3割となっています。さらに所得に応じてひと月当たりの自己負担限度額が定められており、上限を超えた分は高額介護サービス費制度によって払い戻される仕組みです。
また、高額医療・高額介護合算療養費制度を利用すれば、一年間の医療費と介護費の合計が自己負担限度額を超えた場合に超過分が払い戻されます。
上記以外にも、民間の介護保険に加入しておくことで、将来的な経済的負担を軽減できるでしょう。
介護費用を抑える方法は、下記記事でも解説しています。
介護費用を抑える方法は?7つの税金控除と負担軽減の制度・補助金
家族ができること・できないことを理解し、無理のない介護を
家族で行う介護には「できること」と「できないこと」があります。
大切なことは、すべてを完璧にやろうとせず、専門職や制度の力を借りながら、家族にとって無理のない形を選ぶことです。
「支え合いながら続ける介護」が、本人にも家族にも優しい介護といえるでしょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。
公開日:2025年11月12日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




