詳しい資料はこちら
訪問入浴介護サービスとは?
利用条件やメリット・デメリットも紹介
「介護対象者が自力で入浴できないため入浴サポートをしたいけれど、なかなか難しい」という方も多いのではないでしょうか。
公的介護保険が提供する「訪問入浴介護サービス」は、寝たきりや歩行が難しい方でも自宅で入浴ができるサービスです。
ただし、訪問入浴介護サービスを利用するには要介護1以上の認定を受けているなどの条件を満たす必要があります。
本記事では訪問入浴介護サービスの概要や利用がおすすめな方、利用条件、メリット・デメリットを中心に、利用時のトラブル事例も併せて解説します。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
「訪問入浴介護サービス」とは

訪問入浴介護サービスは、寝たきりや歩行が難しい方でも自宅で安心して入浴できるサービスです。
専用の訪問入浴車で自宅に訪問し、看護資格を有するスタッフ1名以上と介護スタッフ2名の3名以上で対応します。横になったまま入浴できるほか、体調が不安な方には清拭・足浴・洗髪など、状況に応じた方法で清潔を保つことが可能です。
入浴前後には看護スタッフが体温や血圧など体調確認を行うため、安心して利用できるでしょう。入浴をすることで、身体を清潔に保ちながら、心身のリフレッシュ効果も期待できます。
専用の訪問入浴車で自宅に訪問し、看護資格を有するスタッフ1名以上と介護スタッフ2名の3名以上で対応します。横になったまま入浴できるほか、体調が不安な方には清拭・足浴・洗髪など、状況に応じた方法で清潔を保つことが可能です。
入浴前後には看護スタッフが体温や血圧など体調確認を行うため、安心して利用できるでしょう。入浴をすることで、身体を清潔に保ちながら、心身のリフレッシュ効果も期待できます。
訪問入浴介護サービスの利用がおすすめな方
自宅での入浴介助は、体力的にも精神的にも家族の負担が大きく、不慣れな介助では転倒など思わぬ事故のリスクもあります。
安全で快適な入浴時間を確保するためにも、訪問入浴介護サービスの利用を検討してみましょう。
例えば、次のような方に利用がおすすめです。
安全で快適な入浴時間を確保するためにも、訪問入浴介護サービスの利用を検討してみましょう。
例えば、次のような方に利用がおすすめです。
-
寝たきりや自力での入浴が難しい方
-
デイサービスなどの通所が難しい方
-
浴室の環境が悪く安全な入浴が難しい方
-
持病や体調変化などがあり、看護スタッフの見守りが必要な方 など
訪問入浴介護サービスを上手に活用することで、介護する家族の負担も軽減できます。無理なく在宅介護を続けるためにも、利用を検討したいサービスです。
訪問入浴介護サービスの利用条件
訪問入浴介護サービスを利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。以下では、サービスを受けるための条件を解説します。
訪問入浴介護サービスを利用するための2つの条件
訪問入浴介護サービスは、誰でも利用できるサービスではありません。サービスを利用するためには、2つの条件を満たす必要があります。
-
要介護1~5の認定を受けている
-
主治医から入浴の許可を受けている
条件を満たしたうえで、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しケアプランの作成が完了したら、サービスの契約が可能です。
要支援者も条件付きで訪問入浴介護を受けられる
基本的に、訪問入浴介護サービスの利用には要介護1以上であることが必要ですが、「自宅に浴室がない」「感染症などの理由で施設での入浴ができない」など事情がある場合は、要支援1~2の方も利用が可能です。
ただし、要介護者の訪問入浴介護サービスとは異なり、要支援者が受けるサービスは「介護予防訪問入浴介護」です。内容は訪問入浴介護サービスとほぼ同じですが、可能な限りサービス利用者本人に行ってもらうことを重視しているため、従事するスタッフの人数が少なくなるケースがあります。一方で、訪問入浴介護サービスと比べると費用は抑えられるでしょう。
ただし、要介護者の訪問入浴介護サービスとは異なり、要支援者が受けるサービスは「介護予防訪問入浴介護」です。内容は訪問入浴介護サービスとほぼ同じですが、可能な限りサービス利用者本人に行ってもらうことを重視しているため、従事するスタッフの人数が少なくなるケースがあります。一方で、訪問入浴介護サービスと比べると費用は抑えられるでしょう。
「種類支給限度基準額」によって利用回数に制限があることも
訪問入浴介護サービスには、地域の住民が公平に利用できるように、1カ月当たりの利用回数に上限が設けられている場合があり、この上限は「種類支給限度基準額」と呼ばれます。
サービスを提供するための体制や人員に限りがあるため、上限を設けないと一部の利用者にサービスが集中し、ほかの方が利用できなくなる可能性があるためです。
なお、利用できる回数の上限や制限の有無は地域によって異なるため、事前に市区町村にある公的介護保険の窓口で確認しておくと安心です。
サービスを提供するための体制や人員に限りがあるため、上限を設けないと一部の利用者にサービスが集中し、ほかの方が利用できなくなる可能性があるためです。
なお、利用できる回数の上限や制限の有無は地域によって異なるため、事前に市区町村にある公的介護保険の窓口で確認しておくと安心です。
訪問入浴介護サービスの流れと所要時間
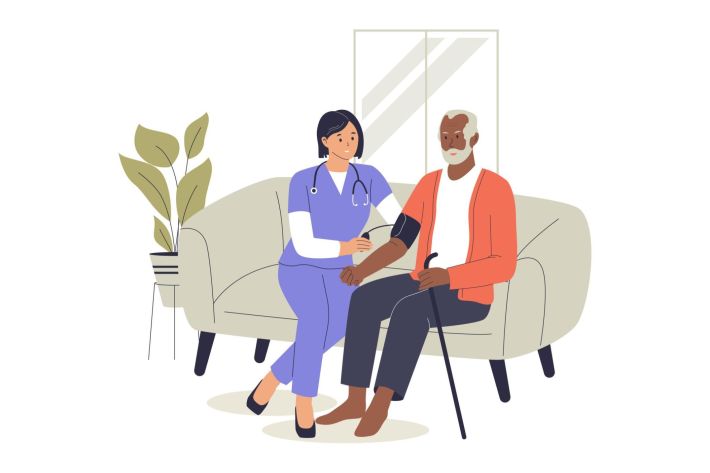
次に、サービスを利用した際の当日の流れと、所要時間を解説します。
当日の流れ
一般的なサービス当日の流れは、次のようになります。
① 入浴前の健康状態チェック
サービス利用者が問題なく入浴できるかどうか確認するため、看護スタッフが血圧・脈拍・体温などを計測します。
体調が優れない場合、部分浴や清拭に変更したり、必要であれば主治医や医療機関への連絡をしたりするなどの対応が取られます。
体調が優れない場合、部分浴や清拭に変更したり、必要であれば主治医や医療機関への連絡をしたりするなどの対応が取られます。
② 入浴の準備
チェックの結果、健康状態に問題がなければ浴槽にお湯を張り、脱衣の準備を進めます。
③ 入浴・上がり湯
ベッドから浴槽に移動します。入浴は本人の希望に合わせ、スタッフが洗髪や洗身をします。その後、仕上げにシャワーでお湯をかけ、浴槽からベッドへと移ります。
④ 着衣と健康状態チェック
着衣を行い、入浴後の健康チェックをします。看護スタッフが血圧や脈拍・体温などの計測と体調の変化や異常がないかの確認をし、必要があれば軟膏の塗布などのケアを行います。
⑤ 片づけ
看護スタッフによる着衣や健康状態チェックと同時進行で、介護スタッフなどが浴槽や物品を片づけます。
サービス利用にかかる所要時間
サービス利用にかかる所要時間は事業所によって異なります。一般的には、準備から片づけまでを50分前後で実施することが多いでしょう。
時間配分の目安としては、入浴の準備までで20分前後、入浴で10分前後、入浴後から片づけまでで20分前後です。利用者の状態や処置内容によって時間は前後するため、サービス利用時には時間に余裕をもっておくとよいでしょう。
時間配分の目安としては、入浴の準備までで20分前後、入浴で10分前後、入浴後から片づけまでで20分前後です。利用者の状態や処置内容によって時間は前後するため、サービス利用時には時間に余裕をもっておくとよいでしょう。
訪問入浴介護サービスの費用相場
訪問入浴介護サービスにおける費用は、対象となる利用者が要介護者か、要支援者かで異なります。また、全身浴か、部分浴(清拭)か、とサービスの内容によっても料金が変わります。
1割負担時の費用相場はこちらです。
1割負担時の費用相場はこちらです。
|
|
要介護1~5 |
要支援1~2 |
|
全身浴 |
1,266円 |
856円 |
|
部分浴 |
1,139円 |
770円 |
|
清拭 |
1,139円 |
770円 |
ほかにも地域加算や介護職員処遇改善加算など、事業所によっては各種加算があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。また、初めて訪問入浴介護サービスを利用した日は初回加算が発生します。
訪問入浴介護サービス利用のメリット5つ
ここからは、訪問入浴介護サービスを利用することで得られるメリットを5つ、紹介します。
身体を清潔に保てる
長期間入浴をしないと、皮膚に汚れや細菌がついた状態が続いてしまい、床ずれや感染症などを引き起こすリスクが上がります。
訪問入浴介護サービスを利用すれば、寝たきりなど要介護度の高い人であっても入浴が可能となるため、身体を清潔に保てるでしょう。
訪問入浴介護サービスを利用すれば、寝たきりなど要介護度の高い人であっても入浴が可能となるため、身体を清潔に保てるでしょう。
身体機能の維持・向上ができる
入浴により全身を温めることで、血行促進や、新陳代謝の向上が期待できます。血行が良くなると、身体の機能が活発になり、便秘や床ずれなどの予防や解消につながるでしょう。ほかにも関節痛やむくみなどの軽減も見込めます。
リラックス効果がある
入浴することでリラックス効果が得られやすくなり、身体の緊張をゆるめ、ストレス軽減が期待できます。加えて、質の良い睡眠につながりやすくなります。
利用者や家族の負担が軽減できる
要介護者を家族が自宅で入浴介助することは、大きな身体的負担がともないます。入浴介助のノウハウのない家族が介助を行うと転倒などのリスクもあります。
訪問入浴サービスでは、入浴介助に慣れているスタッフが作業を行うため、要介護者にとってもより安全に入浴できるでしょう。介護を行う家族の心身や時間の負担軽減にもつながります。
訪問入浴サービスでは、入浴介助に慣れているスタッフが作業を行うため、要介護者にとってもより安全に入浴できるでしょう。介護を行う家族の心身や時間の負担軽減にもつながります。
公的介護保険が適用される
訪問入浴介護サービスは、公的介護保険が適用されるため自己負担を抑えながら利用することが可能です。基本的に自己負担は1割となりますが、一定の所得がある人の場合、所得に応じて2~3割負担になります。
訪問入浴介護サービスのデメリット3つ

訪問入浴介護サービスにはさまざまなメリットがありますが、デメリットもいくつかあります。
訪問介護に比べ高額である
訪問入浴介護サービスのほかにも、自宅を訪問して入浴介助を行うサービスとして「訪問介護」があります。訪問介護では自宅の浴槽を使用し、介護スタッフ1名で見守りから入浴介助までを行います。
これに対し、訪問入浴介護サービスでは一般的に看護スタッフ1名、介護スタッフ2名の3名体制で対応するため、訪問介護の入浴介助に比べると利用費用が高くなります。
費用面が負担になる場合には、民間の介護保険で経済的負担に備えておくのも選択肢の一つです。
FP(ファイナンシャルプランナー)100人に民間の介護保険の魅力を尋ねたところ、「一時金や年金など、給付方法を選択できる」「現金給付であり、使い道が選択できる」などの回答が多く寄せられました。
これに対し、訪問入浴介護サービスでは一般的に看護スタッフ1名、介護スタッフ2名の3名体制で対応するため、訪問介護の入浴介助に比べると利用費用が高くなります。
費用面が負担になる場合には、民間の介護保険で経済的負担に備えておくのも選択肢の一つです。
FP(ファイナンシャルプランナー)100人に民間の介護保険の魅力を尋ねたところ、「一時金や年金など、給付方法を選択できる」「現金給付であり、使い道が選択できる」などの回答が多く寄せられました。
FP100人の回答詳細
※複数回答あり
※複数回答あり
必要に応じて受け取った一時金や年金を使用できるため、訪問入浴介護サービス利用時の負担軽減に活用できるでしょう。
看護スタッフによる医療行為は受けられない
「訪問入浴介護サービスでは看護スタッフも訪問してくれるから、医療行為も行ってくれるのでは」と考える方もいるでしょう。
しかし、訪問入浴自体が在宅サービスの一つであり、看護スタッフは医療行為に関する医師の指示を受けていないため、入浴支援と直接関係のない摘便や痰の吸引、褥瘡(じょくそう)ケアなどを行うことはできません。
訪問入浴の看護スタッフが行えることはバイタルチェックや湿布、軟膏を処置することなどにとどまります。
医療行為が必要な場合は、別途訪問看護サービスの利用が必要です。
しかし、訪問入浴自体が在宅サービスの一つであり、看護スタッフは医療行為に関する医師の指示を受けていないため、入浴支援と直接関係のない摘便や痰の吸引、褥瘡(じょくそう)ケアなどを行うことはできません。
訪問入浴の看護スタッフが行えることはバイタルチェックや湿布、軟膏を処置することなどにとどまります。
医療行為が必要な場合は、別途訪問看護サービスの利用が必要です。
訪問入浴車の駐車スペースが必要
訪問入浴ではボイラーを搭載し、専用の浴槽を積んだ入浴車で行くため、自宅に近い場所に駐車スペースが必要となります。自宅近くに駐車スペースがないとサービスを受けられない可能性もあるため注意が必要です。
駐車スペースがない場合は駐車許可証を発行するといった対応法もあります。事前にケアマネジャーに相談し、検討するとよいでしょう。
駐車スペースがない場合は駐車許可証を発行するといった対応法もあります。事前にケアマネジャーに相談し、検討するとよいでしょう。
訪問入浴介護サービスのトラブル事例と対処法
訪問入浴介護サービスでは、安心して入浴できる環境が整えられていますが、利用時にトラブルが起こる場合もあります。事前に事例を知り、備えておくことが大切です。
利用者が入浴を拒否する
羞恥心や認知症の影響で、サービスを受ける直前に入浴を拒否するケースがあります。家族以外の複数のスタッフに裸を見られることへのストレスが原因となることも少なくありません。
こうした場合、同性介護者の指名が可能かどうかを事前に事業者へ確認しておくと、ストレスの軽減につながります。
また、転倒経験や浴槽での不快な体験から入浴に対してトラウマ(心的外傷)を抱えている方もいます。無理に入浴を促すのではなく、本人の気持ちを尊重しながら、不安に思う内容や理由を丁寧に聞き取り、一緒に解決方法を考える姿勢が大切です。
シャワー浴や清拭から始めるなど、段階的な対応もよいでしょう。利用者と日頃からコミュニケーションを取り、安心してサービスを受けられる環境づくりが重要です。
こうした場合、同性介護者の指名が可能かどうかを事前に事業者へ確認しておくと、ストレスの軽減につながります。
また、転倒経験や浴槽での不快な体験から入浴に対してトラウマ(心的外傷)を抱えている方もいます。無理に入浴を促すのではなく、本人の気持ちを尊重しながら、不安に思う内容や理由を丁寧に聞き取り、一緒に解決方法を考える姿勢が大切です。
シャワー浴や清拭から始めるなど、段階的な対応もよいでしょう。利用者と日頃からコミュニケーションを取り、安心してサービスを受けられる環境づくりが重要です。
利用者の体調が変化する
訪問入浴介護サービスの利用者は、高齢者や障害のある方が多いため、入浴中に体調が急変し、事故につながる恐れがあります。
入浴前後に看護スタッフが体温・血圧などの確認や体調の聞き取りを行いますが、利用者自身が体調の変化を感じていても、うまく伝えられないことがあります。そのため、様子の変化に家族が気付いたときは、スタッフへ伝えることが大切です。
清拭に切り替えるなど、体調に応じた柔軟な対応が取りやすくなるため、安全な入浴につながるでしょう。
入浴前後に看護スタッフが体温・血圧などの確認や体調の聞き取りを行いますが、利用者自身が体調の変化を感じていても、うまく伝えられないことがあります。そのため、様子の変化に家族が気付いたときは、スタッフへ伝えることが大切です。
清拭に切り替えるなど、体調に応じた柔軟な対応が取りやすくなるため、安全な入浴につながるでしょう。
無理なく在宅介護を続けるために訪問入浴介護サービスの検討を
訪問入浴介護サービスは、看護スタッフや介護スタッフが専用の訪問入浴車で自宅を訪問し、入浴をサポートしてくれるサービスです。
入浴の前後には血圧や体温など体調の確認も行うため、安心して利用できますが、訪問介護の入浴介助に比べると費用は高めです。
費用負担が心配な場合には、民間の介護保険で備えておくのも一つの方法です。
民間の介護保険なら、支払事由に該当した場合は用途自由な一時金や年金を受け取れるため、訪問入浴介護サービスを含め、介護の経済的負担に備えられるでしょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。
公開日:2025年8月7日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




