詳しい資料はこちら
地域密着型サービスとは?
サービスの対象者・種類・利用の流れ
「親の介護が必要になったとき、できれば住み慣れた地域で安心して暮らせるようにしてあげたい」と考えていても、どのようなサービスがあるのかわからず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような場面に備えて知っておきたいのが「地域密着型サービス」です。
本記事では、地域密着型サービスの特徴や対象者、サービスの種類、利用の流れについてわかりやすく解説します。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
地域密着型サービスとは

地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域でできる限り長く暮らし続けられるよう支援する介護サービスです。地域の高齢者の実情に合ったサービス提供を目的として、2006年4月の公的介護保険制度改正により創設されました。
一般的な介護サービスは都道府県が指定・監督を行いますが、地域密着型サービスは市区町村がその役割を担います。小規模な事業所が多く、個別対応や顔なじみの関係性を重視したケアが特徴です。
一般的な介護サービスは都道府県が指定・監督を行いますが、地域密着型サービスは市区町村がその役割を担います。小規模な事業所が多く、個別対応や顔なじみの関係性を重視したケアが特徴です。
地域密着型サービスが必要とされるようになった背景
重度の要介護状態になっても自分らしく暮らせる環境を整えるためには、医療・介護・住まいなどを一体的に提供する体制が不可欠です。高齢化の進行には地域差があるため、それぞれの地域に合った支援体制づくりが求められています。
こうした背景のもと、地域の実情に応じたサービス提供を目指して、市区町村が主体となる地域密着型サービスが導入されました。市区町村はサービス事業者の指定や監督を通じて、地域に根差した介護支援を進めます。
こうした背景のもと、地域の実情に応じたサービス提供を目指して、市区町村が主体となる地域密着型サービスが導入されました。市区町村はサービス事業者の指定や監督を通じて、地域に根差した介護支援を進めます。
地域密着型サービスの対象者
地域密着型サービスを利用するには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
-
サービス事業所と同じ市区町村に住民票があること
-
65歳以上であること、または40~64歳で特定疾病があること
-
要介護認定を受けていること
原則として、住民票がサービス事業所のある市区町村にあることが求められ、利用時には住民票の確認が行われます。ただし、市区町村間で協議が行われ、相互に同意が得られた場合に限り、ほかの市区町村のサービスを利用できる例外もあります。
なお、公的介護保険制度では、介護が必要な度合いに応じて「要支援1・2」「要介護1~5」に区分されており、地域密着型サービスの対象となるのは「要介護1以上」の方です。要介護度に応じて、利用できるサービスの内容も異なります。
なお、公的介護保険制度では、介護が必要な度合いに応じて「要支援1・2」「要介護1~5」に区分されており、地域密着型サービスの対象となるのは「要介護1以上」の方です。要介護度に応じて、利用できるサービスの内容も異なります。
要介護状態
(認定の目安)とは?
要支援2・要介護1
-
家事の一部や入浴などに見守りや手助けを必要とすることがある
-
立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とすることがある
次に該当する場合は「要支援2」となります
・適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持・改善が見込まれる
要介護2
-
食事や排泄などに手助けを必要とすることがある
-
物忘れなど認知機能の一部に低下がみられることがある
要介護3
-
食事や排泄などに介助を必要とする
-
認知機能の低下がみられ、それに伴ういくつかの行動・心理症状*がみられることがある
要介護4
-
食事や排泄などに全面的な介助を必要とする
-
全般的な認知機能の低下がみられ、それに伴う多くの行動・心理症状*がみられる
要介護5
-
日常生活を遂行する能力が著しく低下し、全面的な介助を必要とする
-
意思の疎通ができないことが多い
*行動・心理症状とは、暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと
※要介護度別の状態はあくまで目安であり、実際に認定を受けた人の状態がこの表に示した状態と一致しないことがあります。
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2024年10月改訂版)をもとに作成
要支援の方は地域密着型サービスの対象外となりますが、「地域密着型介護予防サービス」が別途利用できます。
地域密着型サービスと居宅サービスの違い
介護サービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分類されます。このうち居宅サービスと地域密着型サービスは、どちらも住み慣れた場所での生活を支えることを目的としていますが、提供の仕組みや対象に違いがあります。
居宅サービスは、利用者がどの市区町村に住んでいても利用可能で、複数のサービスを組み合わせて受けることが一般的です。
一方、地域密着型サービスは、原則として施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。同じ事業者による一貫したケアが受けられ、顔なじみのスタッフによる継続的な支援が期待できます。また、小規模な事業所が多い地域密着型サービスは、利用者の状況や希望に細やかに対応しやすいという特徴もあります。
以下の記事では介護サービス全体の種類や特徴を詳しく紹介しているため、サービス選びの参考にぜひご覧ください。
関連記事:介護サービスの種類とは?3つの分類と各サービスの特徴
居宅サービスは、利用者がどの市区町村に住んでいても利用可能で、複数のサービスを組み合わせて受けることが一般的です。
一方、地域密着型サービスは、原則として施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。同じ事業者による一貫したケアが受けられ、顔なじみのスタッフによる継続的な支援が期待できます。また、小規模な事業所が多い地域密着型サービスは、利用者の状況や希望に細やかに対応しやすいという特徴もあります。
以下の記事では介護サービス全体の種類や特徴を詳しく紹介しているため、サービス選びの参考にぜひご覧ください。
関連記事:介護サービスの種類とは?3つの分類と各サービスの特徴
地域密着型サービスの種類
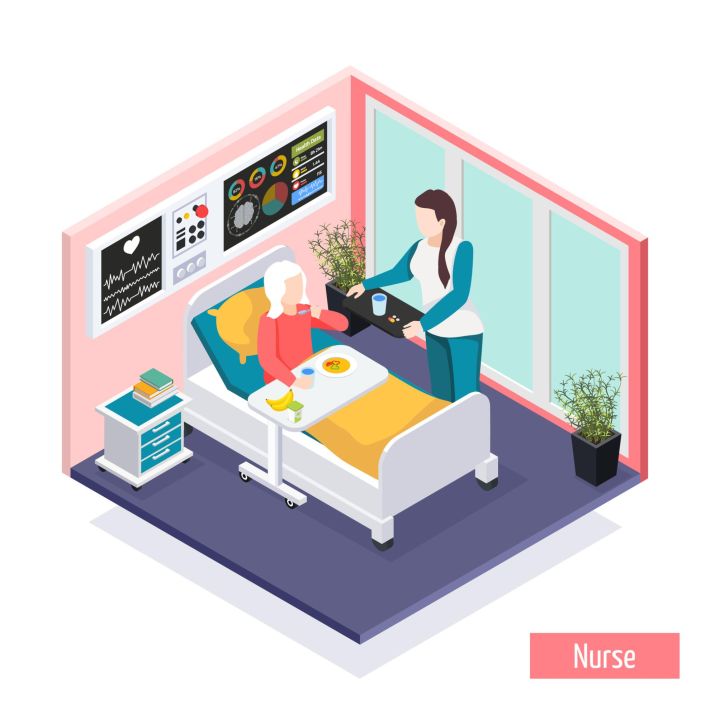
地域密着型サービスには、利用者の状態や希望に応じて選べる10種類のサービスがあります。以下ではそれぞれの特徴を紹介します。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、介護が必要な方が自宅での暮らしを続けられるよう支援するサービスです。
通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせて利用でき、1つの事業所が継続して支援を行うため、顔なじみのスタッフによる一貫したケアが受けられる点が特徴です。
通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせて利用でき、1つの事業所が継続して支援を行うため、顔なじみのスタッフによる一貫したケアが受けられる点が特徴です。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」を加えた複合型のサービスです。看護師が配置されているため、医療的ケアが必要な方にも対応できます。
介護と医療の両面から支援が受けられる点が大きな特徴です。
介護と医療の両面から支援が受けられる点が大きな特徴です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な訪問介護に加え、緊急時には24時間365日いつでも対応できる体制が整っています。訪問介護と訪問看護が密に連携し、安否確認から医療的ケアまで柔軟に対応することが可能です。
一人暮らしや認知症の方、要介護度の高い方でも自宅での生活を継続しやすくなるでしょう。
一人暮らしや認知症の方、要介護度の高い方でも自宅での生活を継続しやすくなるでしょう。
夜間対応型訪問介護
夜間(午後6時~午前8時)にホームヘルパー(訪問介護員)が訪問し、安否確認や排せつ介助などを行うサービスです。
定期訪問のほか、随時対応サービスも利用可能です。例えば夜間に体調が急変した際には、オペレーターを通じてホームヘルパーが駆けつけ、必要に応じて救急車の手配なども行います。
一人暮らしの高齢者や、夜間に家族の支援を受けにくい方でも、自宅での生活を続けられる仕組みです。
定期訪問のほか、随時対応サービスも利用可能です。例えば夜間に体調が急変した際には、オペレーターを通じてホームヘルパーが駆けつけ、必要に応じて救急車の手配なども行います。
一人暮らしの高齢者や、夜間に家族の支援を受けにくい方でも、自宅での生活を続けられる仕組みです。
地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模なデイサービスで、食事・入浴・排せつなどの日常生活支援や機能訓練、レクリエーションなどを日帰りで利用できます。
少人数での運営のため、スタッフの目が行き届きやすく、利用者同士やスタッフとの関係を築きやすい点が特徴です。家庭的な雰囲気のなかで、利用者の希望に沿った柔軟な対応ができる環境が整っています。
少人数での運営のため、スタッフの目が行き届きやすく、利用者同士やスタッフとの関係を築きやすい点が特徴です。家庭的な雰囲気のなかで、利用者の希望に沿った柔軟な対応ができる環境が整っています。
療養通所介護
医療依存度の高い方を対象とした「医療型デイサービス」です。重度の要介護者や難病・末期がん患者などが対象で、看護師による医療的ケアや送迎付き添いも可能です。
定員は1日5名以下と少人数で、訪問看護などとの連携により専門性の高い支援を提供します。
定員は1日5名以下と少人数で、訪問看護などとの連携により専門性の高い支援を提供します。
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者を対象とした小規模なデイサービスで、専門的なケアのもと、落ち着いた環境で日中を過ごせるよう支援します。
一般のデイサービスの環境ではなじめなかった場合でも、認知症に関する専門知識を持つスタッフが丁寧に対応するため、利用しやすいでしょう。
設置形態は「併設型」「単独型」「共用型」の3種類があり、地域や施設によって運営の形が異なります。
一般のデイサービスの環境ではなじめなかった場合でも、認知症に関する専門知識を持つスタッフが丁寧に対応するため、利用しやすいでしょう。
設置形態は「併設型」「単独型」「共用型」の3種類があり、地域や施設によって運営の形が異なります。
認知症対応型共同生活介護
一般的に「グループホーム」と呼ばれる認知症対応型共同生活介護は、認知症の高齢者が5~9人の少人数で共同生活を送りながら、介護や支援を受ける施設サービスです。認知症ケアに特化した専門スタッフが常駐し、利用者は家庭的な環境のなかで掃除や料理などを分担して生活します。
対象は要支援2以上の認知症の方で、原則として施設と同じ市区町村に住民票があることが必要です。
認知症対応型共同生活介護は以下の記事で詳しく解説しているため、併せて参考にしてください。
関連記事:グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?入所条件・費用・選び方
対象は要支援2以上の認知症の方で、原則として施設と同じ市区町村に住民票があることが必要です。
認知症対応型共同生活介護は以下の記事で詳しく解説しているため、併せて参考にしてください。
関連記事:グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?入所条件・費用・選び方
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員29人以下の小規模な特別養護老人ホーム(特養)で、食事・入浴・排せつなどの日常生活支援のほか、機能訓練や健康管理などのサービスを提供します。サービス内容は通常の特養と同様ですが、利用できる方は施設と同じ市区町村に住む要介護者に限られます。
施設形態には、本体施設と連携して運営される「サテライト型」、サービス事業所に併設されている「併設型」、単独で運営される「単独型」があります。
施設形態には、本体施設と連携して運営される「サテライト型」、サービス事業所に併設されている「併設型」、単独で運営される「単独型」があります。
地域密着型特定施設入居者生活介護
都道府県により指定を受けた小規模な有料老人ホームなどのことで、入居者に対して食事・入浴・排せつなどの介護や生活支援、機能訓練などのサービスを提供します。定員は29人以下に限定されています。
対象施設は、有料老人ホームのほか、サービス付き高齢者向け住宅(一部のみ)、養護老人ホーム、ケアハウスです。
対象施設は、有料老人ホームのほか、サービス付き高齢者向け住宅(一部のみ)、養護老人ホーム、ケアハウスです。
地域密着型サービスのメリットとデメリット

地域密着型サービスには、安心感や柔軟な対応などの利点がある一方で、利用の際に注意すべき点もあります。ここでは代表的なメリットとデメリットを紹介します。
地域密着型サービスのメリット
地域密着型サービスの大きな利点は、住み慣れた地域で継続的に介護を受けられることです。特に環境の変化に敏感な認知症の方にとって、生活環境が変わらないことは安心感につながります。
また、小規模な施設や事業所ではスタッフと利用者が自然と顔なじみになりやすく、信頼関係を築いたうえでのきめ細かなケアが可能です。
さらに、地域の実情や利用者ごとの希望に合わせて、柔軟に対応できる点も魅力で、従来の介護サービスでは対応しきれなかった個別の要望にも応えやすくなっています。
また、小規模な施設や事業所ではスタッフと利用者が自然と顔なじみになりやすく、信頼関係を築いたうえでのきめ細かなケアが可能です。
さらに、地域の実情や利用者ごとの希望に合わせて、柔軟に対応できる点も魅力で、従来の介護サービスでは対応しきれなかった個別の要望にも応えやすくなっています。
地域密着型サービスのデメリット
地域密着型サービスでは、利用するサービス事業所のケアマネジャーがケアプラン作成を担当します。そのため、これまで関わってきたケアマネジャーとの関係が途切れてしまい、不安を感じる利用者もいるかもしれません。
また、各施設には定員があるため、タイミングによっては希望するサービスをすぐに利用できない場合もあります。加えて、スタッフの働きやすさといった運営面の課題も指摘されており、今後の改善が期待されています。
また、各施設には定員があるため、タイミングによっては希望するサービスをすぐに利用できない場合もあります。加えて、スタッフの働きやすさといった運営面の課題も指摘されており、今後の改善が期待されています。
地域密着型サービスの利用の流れ
地域密着型サービスは、次の流れで利用します。
-
要介護認定を受ける
-
地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談
-
利用したい事業所を選び、空き状況を確認
-
事業所と契約
-
ケアプランの作成
-
サービス利用開始
要介護認定を受けていない場合は、申請手続きから始める必要があります。
認定を受けた後は、お住いの地域の地域包括支援センターに相談しましょう。要介護1以上の方や、すでに認定を受けて介護サービスを利用中の方は、担当のケアマネジャーに相談して、具体的な手続きを進めます。
利用を希望する地域密着型サービスの事業所を調べ、空き状況を確認したうえで契約を結び、サービスの詳細を決定します。
なお、小規模多機能型やグループホームを利用する場合は、利用する事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを新たに担当します。
ケアプランが整ったら、スケジュールに沿ってサービスを利用していきます。
要介護認定の申請から利用開始までの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:公的介護保険とは?公的介護保険申請から利用開始まで
認定を受けた後は、お住いの地域の地域包括支援センターに相談しましょう。要介護1以上の方や、すでに認定を受けて介護サービスを利用中の方は、担当のケアマネジャーに相談して、具体的な手続きを進めます。
利用を希望する地域密着型サービスの事業所を調べ、空き状況を確認したうえで契約を結び、サービスの詳細を決定します。
なお、小規模多機能型やグループホームを利用する場合は、利用する事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを新たに担当します。
ケアプランが整ったら、スケジュールに沿ってサービスを利用していきます。
要介護認定の申請から利用開始までの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:公的介護保険とは?公的介護保険申請から利用開始まで
地域密着型サービスの概要を理解し、将来の介護に備えよう
地域密着型サービスは、介護が必要な状況になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援する仕組みです。
サービスの対象者や種類、利用の流れをあらかじめ理解しておくことで、介護が必要になったときに慌てず対応できます。将来の備えとして、事前に制度の仕組みを知っておくことが大切です。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。
公開日:2025年5月14日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




