詳しい資料はこちら
介護保険料の徴収はいつから?
支払時期・方法と金額の目安
「介護保険料はいつから支払うの?」「保険料の目安は?」と疑問を持つ方もいると思います。
介護保険制度は、介護を社会全体で支えることを目的とする制度で、40歳以上の方は加入義務があります。介護保険料も生涯にわたって納めなければなりません。
介護保険料の金額は年齢や加入している公的医療保険、収入などによって異なるため、理解を深めることが重要です。
本記事では、介護保険料の支払開始時期や支払方法、金額の目安、介護サービスの適用年齢、条件について解説します。
詳しい資料はこちら
介護保険料の支払い開始時期は?
介護保険料は「40歳に達した月」から生涯にわたり支払う
-
誕生日が8月1日の場合:資格取得日は7月31日となり、7月分から介護保険料が徴収される
-
誕生日が8月2日の場合:資格取得日は8月1日となり、8月分から介護保険料が徴収される
介護保険料の支払いがないケース
ただし、生活保護受給者は介護保険料の支払いが不要です。また、被扶養者の場合も、配偶者などが加入している公的医療保険の保険料に、被扶養者の介護保険料も含まれるため個別に支払う必要がありません。
そのほか、次の場合は、市区町村に認められると減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
-
災害で大きな被害を受けた
-
収入が低く生活が困窮している
-
長期入院や失業などで収入が著しく減少した など
介護保険料の支払いが難しい場合の対処法については、以下の記事でも解説しています。参考にしてください。
介護保険料の支払方法は?
支払方法は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」によって異なる
|
|
第1号被保険者(65歳以上) |
第2号被保険者(40歳~64歳) |
|
対象者 |
65歳以上の方 |
40歳~64歳で、おもに下記の公的医療保険加入者 l 健康保険組合 l 全国健康保険協会 l 国民健康保険 |
|
受給要件 |
要介護状態または要支援状態 |
要介護状態または要支援状態が老化に起因する特定疾病の場合 |
|
保険料の 徴収方法 |
l 65歳になった月から徴収開始 l 市町村と特別区が徴収し、原則年金からの天引き |
l 40歳になった月から徴収開始 l 医療保険料と一体的に徴収 |
第1号被保険者(65歳以上)の場合
第1号被保険者の介護保険料は、市町村と特別区が徴収し、原則年金からの天引きです。ただし、年金受給額が年18万円未満の場合は、口座振替や納付書にて支払います。
介護保険料は、各自治体が条例で定めた「基準額」をもとに、本人や世帯の所得に応じて設定されています。
第2号被保険者(40歳~64歳)の場合
一方、国民健康保険に加入している方の介護保険料は、国民健康保険の保険料と合わせて徴収されます。納付義務者は世帯主で、介護保険料は被保険者の前年の所得額や世帯の被保険者数、資産額などによって異なります。
介護保険料の月額の目安
ここでは65歳以上の第1号被保険者、会社員の第2号被保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ))、自営業の第2号被保険者(国民健康保険)に分けて、それぞれの介護保険料の目安を具体的に解説します。
65歳以上の第1号被保険者
この基準額は、地域の高齢化状況や介護サービスの利用状況に応じて自治体ごとに設定されるため、地域によって異なる点が特徴です。
厚生労働省によると、令和6~8年度の基準額の全国平均は月額6,225円です。
正確な金額は、住んでいる市区町村のホームページなどを確認しましょう。
第1号被保険者の介護保険料の計算方法については、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。
第2号被保険者(会社員で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入)
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
令和7年度(4月納付分から)の介護保険料率は1.59%であり、標準報酬月額ごとの介護保険料の月額は次のとおりです。
|
標準報酬月額 (4~6月の3ヵ月の平均) |
介護保険料(全額) |
本人負担分(半額) |
|
30万円 |
4,770円 |
2,385円 |
|
41万円 |
6,519円 |
3,260円 |
|
50万円 |
7,950円 |
3,975円 |
※1円未満は1円に切り上げ
第2号被保険者(自営業で国民健康保険に加入)
例えば、東京都世田谷区における加入者1人分の介護保険料(月額)の目安は次のとおりです。
|
前年の合計所得金額 |
介護保険料 |
|
360万円 |
7,327円 |
|
480万円 |
9,577円 |
|
600万円 |
11,827円 |
自治体によって介護保険料の計算方法は異なる点に注意しましょう。
介護保険料を滞納するとどうなる?

ここからは、介護保険料を滞納した場合の措置について解説します。
納付期限から1年未満の場合
1年以上滞納の場合
後日、給付の申請をすると、本来の自己負担額を除く費用が払い戻されます(償還払い)が、償還分が戻ってくるまでには時間がかかります。
期日までに介護保険料の支払いが難しい場合は、以下の記事で対処法を解説しています。参考にしてください。
1年6ヵ月以上滞納の場合
ただし、給付の申請をしたとしても、保険給付額の一部または全額が一時的に差し止められ、そこから滞納している介護保険料に充てる場合があります。
2年以上滞納の場合
介護サービスはいつから利用できる?
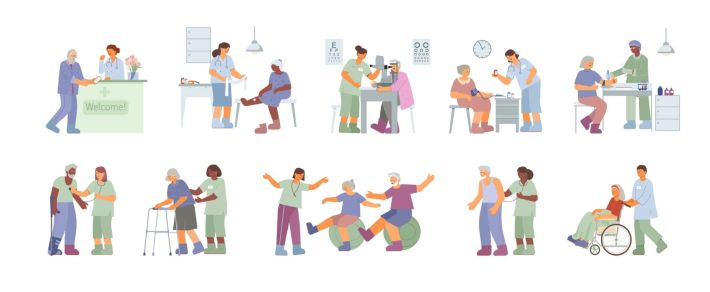
第1号被保険者(65歳以上)は「要支援・要介護認定を受けたあと」
要介護認定には、要支援は1~2、要介護は1~5の7つの段階があり、要介護(要支援)の認定を受けると、居宅介護支援事業所や施設などに所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、要介護度に応じた介護サービスを受けられるようになります。第1号被保険者の介護サービスの利用では、要支援や要介護の要因は問われません。
第2号被保険者(40歳~64歳)は「要件を満たす方のみ」
-
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
-
関節リウマチ
-
筋萎縮性側索硬化症
-
後縦靱帯骨化症
-
骨折をともなう骨粗鬆症
-
初老期における認知症
-
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
-
脊髄小脳変性症
-
脊柱管狭窄症
-
早老症
-
多系統萎縮症
-
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
-
脳血管疾患
-
閉塞性動脈硬化症
-
慢性閉塞性肺疾患
-
両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
公的介護保険だけで介護費用は賄える?
介護サービスには支給限度額がある
自己負担割合は、本人の合計所得金額や、単身世帯または2人以上の世帯の年金収入とその他の所得金額の合計額によって異なります。
介護サービスは、要支援・要介護の度合いに応じて支給限度額が定められ、介護サービス費の利用限度額を超えた分は、全額自己負担しなければなりません。よって、公的介護保険だけで介護費用をすべて賄うのは難しい場合があります。
なお、所得の低い方や、1ヵ月の介護サービスの利用料が高額になった方は、「高額介護サービス費」や、1年間に公的医療保険・介護保険の双方で高額の自己負担が生じた場合に定められた限度額を超過した分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」などの負担軽減措置が適用されます。
介護施設なら介護サービス以外の自己負担額も考慮
介護期間の長期化や、要介護の度合いが進むと、自己負担額やその他の費用負担が大きくなると考えられます。
民間の介護保険2つの特徴
LIFULL介護によると、全国の有料老人ホームの入居費用相場の約半数は200万円を超えており、まとまった資金が必要になる場合があります。
全国の有料老人ホームの
入居時費用相場約半数が
※株式会社LIFULL senior 老人ホーム検索サイト
「LIFULL 介護」より 2024年10月31日時点の都道府県単位での平均入居別費用相場から当社にて試算(平均入居別費用相場が「不明」の9県を除く)
※費用は目安であり、地域・施設により異なります。
|
要介護度 |
利用限度額(月額) |
|
要支援1 |
50,320円 |
|
要支援2 |
105,310円 |
|
要介護1 |
167,650円 |
|
要介護2 |
197,050円 |
|
要介護3 |
270,480円 |
|
要介護4 |
309,380円 |
|
要介護5 |
362,170円 |
民間の介護保険には、公的介護保険制度にはない以下のような特徴があります。
-
現金で給付を受けられる
-
給付金の使い道は自由
介護保険料は忘れずに納付することが大切
介護保険料は「40歳の誕生日前日を含む月」から支払いが始まり、生涯にわたり払い続けるものです。支払方法や保険料は、被保険者の年齢や所得などの条件によって異なります。
支払いを忘れると延滞金が発生したり、将来介護サービスを利用する際に思うように利用できなかったりする場合もあるため、忘れずに支払いましょう。
公的介護保険だけでは介護費用を補うのに不安がある場合は、民間の介護保険も検討してみてください。現金給付で使い道も問われないため、有料老人ホームの入居費用や限度額を超えたサービス利用料など、公的介護保険でカバーしきれない部分の備えにも活用できます。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

公開日:2025年8月7日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




