詳しい資料はこちら
老老介護の現状は?
共倒れを防ぐ4つの解決策
近年、老老介護による共倒れや介護放棄が社会問題となっています。
老老介護は、介護者と要介護者がどちらも65歳以上の状態です。65歳以上の子どもが親を介護したり、65歳以上の高齢夫婦で配偶者の介護をしたりするという状況は、お互いに体力的・身体的な負担が増加するリスクがあります。しかし、介護サービスや見守りサービスなど、老老介護を支える仕組みもあり、ご家族に合ったサービスの利用によって負担を軽減することが可能です。
本記事では、老老介護の現状と課題、事前の対策や解決策を解説します。また、介護の経済的な負担を軽減できる、民間介護保険の利用についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
老老介護は増加傾向にある

はじめに、老老介護の概要と現状を見ていきましょう。
「老老介護」とは
老老介護とは、介護者と要介護者がどちらも65歳以上の高齢者である状態で、特に75歳を超えている方同士の介護を「超老老介護」と呼びます。夫婦や親子、きょうだい間など関係性はさまざまですが、老老介護は介護者・要介護者ともに心身の負担が大きく、社会問題となっています。
また、老老介護に似た言葉として「認認介護」があり、介護者と要介護者がともに認知症である状態を指します。
また、老老介護に似た言葉として「認認介護」があり、介護者と要介護者がともに認知症である状態を指します。
要介護者と介護者の年齢別割合
厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、「要介護者等」と「同居のおもな介護者」の年齢の組み合わせは以下のとおりです。
● 60歳以上同士:77.1%
● 65歳以上同士:63.5%
● 75歳以上同士:35.7%
いずれの年齢の組み合わせも増加傾向にあります。また、同調査では「要介護者等」と「おもな介護者」は45.9%が同居しており、おもな介護者の続柄は、配偶者が22.9%で最も多く、次いで子が16.2%でした。
● 60歳以上同士:77.1%
● 65歳以上同士:63.5%
● 75歳以上同士:35.7%
いずれの年齢の組み合わせも増加傾向にあります。また、同調査では「要介護者等」と「おもな介護者」は45.9%が同居しており、おもな介護者の続柄は、配偶者が22.9%で最も多く、次いで子が16.2%でした。
老老介護が増加している3つの理由
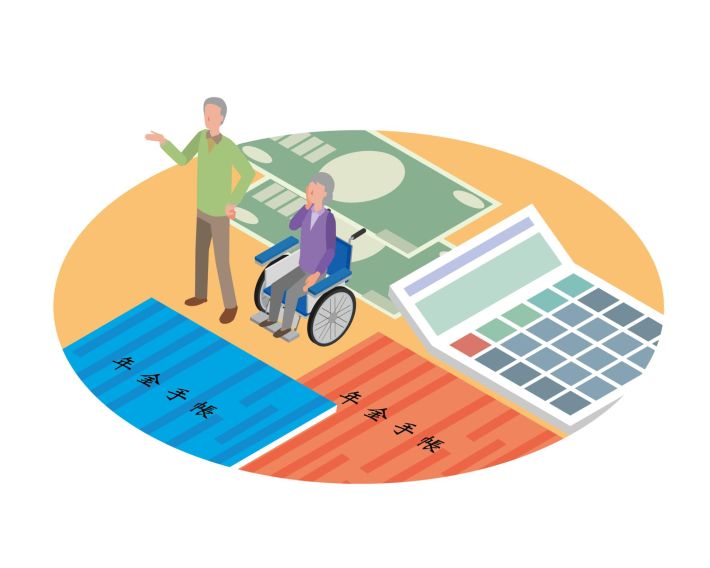
なぜ、老老介護が増加しているのでしょうか。国の統計データをもとに、3つの要因を解説します。
核家族化と単身世帯が増えている
「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によると、65歳以上の方のいる世帯において、全体の半数以上が高齢者のみの世帯です。そのうち単身世帯は31.7%を占めており、2001年の19.4%から増加していることが示されています。
また、夫婦のみの世帯や、夫婦と未婚の子ども世帯も同様に増加しており、核家族化も深刻です。このような世帯では若い世代が同居しておらず、老老介護の要因となります。
また、夫婦のみの世帯や、夫婦と未婚の子ども世帯も同様に増加しており、核家族化も深刻です。このような世帯では若い世代が同居しておらず、老老介護の要因となります。
平均寿命と健康寿命に差がある
「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活を制限されることなく、自立して生活できる期間です。そのため、平均寿命と健康寿命の差は介護が必要になる可能性がある期間ということになります。この差が大きいほど、老老介護になる可能性も高まります。
令和4年時点の平均寿命と健康寿命の差※1は以下のとおりです。
令和4年時点の平均寿命と健康寿命の差※1は以下のとおりです。
|
|
平均寿命 |
健康寿命 |
差 |
|
男性 |
81.05歳 |
72.57歳 |
8.49歳 |
|
女性 |
87.09歳 |
75.45歳 |
11.63歳 |
医療の進歩や生活環境の変化により健康寿命は延伸傾向ですが、平均寿命も延伸しているため、その差はなかなか埋まっていません。今後も平均寿命は延び、令和52年(2070年)には、男性85.89歳、女性91.94歳になると予想されています※2。
※1厚生科学審議会(地域保健健康増進栄養部会)「第4回健康日本21(第三次)推進専門委員会資料」(令和6年) ※令和4年値を掲載
介護サービス費の捻出が経済的に厳しい
経済的に余裕がないことも、老老介護が増加している要因として挙げられます。
内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)」では、65歳以上の方の経済的な暮らし向きを調査しており、「家計にゆとりがなく、多少心配である」「家計が苦しく、非常に心配である」と回答した割合は約30%に上ります。約3人に1人が経済的に余裕がないと感じている状況です。
介護サービスを利用するには一定の自己負担を要しますが、費用を捻出できず、老老介護にならざるを得ない現状が考えられます。
内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)」では、65歳以上の方の経済的な暮らし向きを調査しており、「家計にゆとりがなく、多少心配である」「家計が苦しく、非常に心配である」と回答した割合は約30%に上ります。約3人に1人が経済的に余裕がないと感じている状況です。
介護サービスを利用するには一定の自己負担を要しますが、費用を捻出できず、老老介護にならざるを得ない現状が考えられます。
共倒れのリスクも?老老介護の課題
老老介護には、以下のような課題があります。
● 身体的・精神的に疲弊する
● 社会的なつながりが減る
● 共倒れや介護放棄のおそれがある
それぞれ詳しく解説します。
● 身体的・精神的に疲弊する
● 社会的なつながりが減る
● 共倒れや介護放棄のおそれがある
それぞれ詳しく解説します。
身体的・精神的に疲弊する
老老介護は介護者も高齢であるため、介護の負担が大きく、体力を消耗します。入浴介助などでは、足腰に負荷がかかり、転倒してケガをするリスクもあるでしょう。
また、高齢者は疲れやすく身体の動きも遅いため、介護に時間がかかり、介護者だけでなく要介護者の身体的負担にもつながります。介護の時間が長くなるほど、お互いの精神的負担も増加するでしょう。
また、高齢者は疲れやすく身体の動きも遅いため、介護に時間がかかり、介護者だけでなく要介護者の身体的負担にもつながります。介護の時間が長くなるほど、お互いの精神的負担も増加するでしょう。
社会的なつながりが減る
介護に多くの時間を割くようになると、外出の機会が減り、社会的なつながりが希薄になりがちです。
社会的なつながりが希薄になると、他者との交流も少なくなるため、悩みごとがあっても相談できず一人で問題を抱え込んでしまうリスクがあります。十分な休息を取れず、介護うつになる危険性もあるでしょう。
また、家に引きこもりがちになることで認知症のリスクが高まり、認認介護となるケースもあります。
社会的なつながりが希薄になると、他者との交流も少なくなるため、悩みごとがあっても相談できず一人で問題を抱え込んでしまうリスクがあります。十分な休息を取れず、介護うつになる危険性もあるでしょう。
また、家に引きこもりがちになることで認知症のリスクが高まり、認認介護となるケースもあります。
共倒れや介護放棄のおそれがある
交流や外出が減り、社会から孤立してしまうと、支援の手が届きにくくなります。介護者が身体的・精神的に限界を迎えると、共倒れや介護放棄を招きかねません。
なかには、介護者が要介護者を虐待してしまうケースもあるため、限界を迎える前に対策を講じることが重要です。
なかには、介護者が要介護者を虐待してしまうケースもあるため、限界を迎える前に対策を講じることが重要です。
老老介護を防ぐためにできること

老老介護は介護者、要介護者の双方にとって負担が大きいため、予防や事前の対策が重要です。具体的には、以下のような予防・対策があります。
● 健康な生活を心がける
● 介護教室に参加する
● 民間の介護保険の利用を検討する
● 事前に家族で話し合う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
● 健康な生活を心がける
● 介護教室に参加する
● 民間の介護保険の利用を検討する
● 事前に家族で話し合う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
健康な生活を心がける
まずは、高齢になっても自立した生活が送れるように、健康な生活を心がけることが大切です。
適度な運動や栄養バランスの良い食事、十分な休息などを、無理のない範囲で日常生活に取り入れましょう。
家族とコミュニケーションをとったり、文字の読み書きをしたりといった活動もよいでしょう。
介護が必要となる原因の一つである認知症の予防にもなります。
適度な運動や栄養バランスの良い食事、十分な休息などを、無理のない範囲で日常生活に取り入れましょう。
家族とコミュニケーションをとったり、文字の読み書きをしたりといった活動もよいでしょう。
介護が必要となる原因の一つである認知症の予防にもなります。
介護教室に参加する
自治体が開催している介護教室へ参加し、介護に関する知識を身に着けておくこともおすすめです。
介護の知識がないと、介助に時間を要したり、コミュニケーションエラーが起こったりするおそれがあります。介護が必要になったときに備えて、事前に情報を集めておきましょう。
自治体によって内容は異なりますが、以下のような内容の教室が開催されています。
● 排泄介助
● 腰痛・膝痛予防体操
● 認知症予防のトレーニング
● 公的介護保険制度と費用
● 介護予防のための運動や食事 など
介護教室に参加すれば、健康を維持しながら介護に関する知識を身に付けることができます。
自治体が開催する介護予防の取り組みは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:介護予防で健やかにすごそう |介護予防サービス
介護の知識がないと、介助に時間を要したり、コミュニケーションエラーが起こったりするおそれがあります。介護が必要になったときに備えて、事前に情報を集めておきましょう。
自治体によって内容は異なりますが、以下のような内容の教室が開催されています。
● 排泄介助
● 腰痛・膝痛予防体操
● 認知症予防のトレーニング
● 公的介護保険制度と費用
● 介護予防のための運動や食事 など
介護教室に参加すれば、健康を維持しながら介護に関する知識を身に付けることができます。
自治体が開催する介護予防の取り組みは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:介護予防で健やかにすごそう |介護予防サービス
民間の介護保険の利用を検討する
民間の介護保険に加入することで、介護に関する経済的な負担に備えられます。
生命保険文化センター「令和6年度生命保険に関する全国実態調査」によると、平均介護費用は月額約9万円、平均介護期間は55.0カ月です。
また、月額の介護費用以外にも初期費用がかかる可能性があります。
一時的に必要となった介護費用の平均額は約47万円となっています。
一時的な費用と月額の介護費用を合わせると、総額で約542万円必要となる見込みです。
生命保険文化センター「令和6年度生命保険に関する全国実態調査」によると、平均介護費用は月額約9万円、平均介護期間は55.0カ月です。
また、月額の介護費用以外にも初期費用がかかる可能性があります。
一時的に必要となった介護費用の平均額は約47万円となっています。
一時的な費用と月額の介護費用を合わせると、総額で約542万円必要となる見込みです。
事前に家族で話し合う
家族が要介護状態になった場合を想定して、どのように対応するかを事前に話し合うことも大切です。
介護者にも自分の生活があり、要介護者と考えが異なる可能性もあります。利用できる制度やサービスを調べ、事前に考えを共有しておくことで、いざ介護が必要になっても、不要なトラブルを避けて速やかに対応できるでしょう。
介護者にも自分の生活があり、要介護者と考えが異なる可能性もあります。利用できる制度やサービスを調べ、事前に考えを共有しておくことで、いざ介護が必要になっても、不要なトラブルを避けて速やかに対応できるでしょう。
老老介護の4つの解決策
老老介護を解決するには、介護者の身体的・精神的な負担と経済的な負担の軽減が必要です。具体的な解決策を4つ紹介します。
地域包括支援センターへ相談する
地域包括支援センターとは、地域に住む高齢者の介護や健康、暮らしに関する悩みにワンストップで応じてくれる相談窓口です。
ケアマネジャーや社会福祉士、保健師などの専門家が相談に対応し、必要に応じて利用できるサービスや制度を紹介してくれます。
基本的には地域に住む65歳以上の高齢者や要介護者、その家族などが利用対象ですが、介護や福祉の悩みがあれば誰でも無料で相談できます。
地域包括支援センターについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:地域包括支援センターとは?役割と相談できる内容・利用方法
ケアマネジャーや社会福祉士、保健師などの専門家が相談に対応し、必要に応じて利用できるサービスや制度を紹介してくれます。
基本的には地域に住む65歳以上の高齢者や要介護者、その家族などが利用対象ですが、介護や福祉の悩みがあれば誰でも無料で相談できます。
地域包括支援センターについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:地域包括支援センターとは?役割と相談できる内容・利用方法
介護サービスを利用する
自治体に申請し、要介護(要支援)認定を受けると、要介護度に応じた公的介護保険のサービスを利用できます。利用料の自己負担割合は原則1割です。
介護サービスでは、以下のようなサービスを利用できます。
介護サービスでは、以下のようなサービスを利用できます。
-
自宅で利用できる訪問看護や訪問介護
-
日帰りで施設に通う通所介護や通所リハビリテーション
-
特別養護老人ホームなどの施設への入居
-
介護用品のレンタル・購入費用や、住宅改修工事費用の負担軽減 など
もし、介護サービスの利用で自己負担限度額を超えた場合は、超過分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度を利用できます。費用負担が高額になった場合は申請期間内に忘れずに申請しましょう。
公的介護保険制度で受けられる介護サービスや対象者などは以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:公的介護保険制度とは? 仕組みや対象者・受けられるサービス
公的介護保険制度で受けられる介護サービスや対象者などは以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:公的介護保険制度とは? 仕組みや対象者・受けられるサービス
見守りサービスの利用やご近所関係の構築をする
同居が難しい方や、なかなか様子を見に行けない方は、見守りサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
介護の見守りサービスには、スタッフが自宅を訪問して安否確認を行う「訪問型」や、家電製品やお風呂などにセンサーを設置する「センサー型」、自宅にカメラを設置する「カメラ型」など、さまざまな形態があります。
独自の見守りサービスを展開している自治体もあるため、お住まいの自治体で利用できる見守りサービスがないかを調べてみるとよいでしょう。
また、近所に住む方との人間関係を構築しておくと、万が一のときの安否確認のお願いや相談がしやすくなります。連絡先を交換する・積極的に挨拶するなどして、良好な関係性を築くことをおすすめします。
介護の見守りサービスには、スタッフが自宅を訪問して安否確認を行う「訪問型」や、家電製品やお風呂などにセンサーを設置する「センサー型」、自宅にカメラを設置する「カメラ型」など、さまざまな形態があります。
独自の見守りサービスを展開している自治体もあるため、お住まいの自治体で利用できる見守りサービスがないかを調べてみるとよいでしょう。
また、近所に住む方との人間関係を構築しておくと、万が一のときの安否確認のお願いや相談がしやすくなります。連絡先を交換する・積極的に挨拶するなどして、良好な関係性を築くことをおすすめします。
介護施設に入所する
自宅での介護が難しい場合は、介護施設への入所も選択肢の一つです。
なかでも、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認と、専門家による生活相談サービスを受けられる賃貸住宅です。自由度が高く自宅と同じように生活できるため、人気があります。施設全体がバリアフリー化されていることも、安心して生活を送ることができるポイントのひとつです。
サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。
なかでも、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認と、専門家による生活相談サービスを受けられる賃貸住宅です。自由度が高く自宅と同じように生活できるため、人気があります。施設全体がバリアフリー化されていることも、安心して生活を送ることができるポイントのひとつです。
サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。
-
一般型自立状態あるいは要介護度が軽い方向け。必要に応じて外部の介護サービスを利用できます。
-
介護型要介護度が重い方向け。ケアスタッフが24時間常駐しており、施設のスタッフから介護サービスを受けられます。
一般型の入居条件は、60歳以上で自立している方、または60歳未満で要介護(要支援)認定を受けている方です。同居者として配偶者なども入居が可能です。
施設によっても詳細は異なるため、入居を検討する際には条件を忘れずに確認しましょう。
ここまで、老老介護の解決策を4つ紹介しましたが、ご本人の希望や要介護度などにより適しているサービスは異なります。家族で話し合い、状況に合ったサービスを選択することが重要です。
施設によっても詳細は異なるため、入居を検討する際には条件を忘れずに確認しましょう。
ここまで、老老介護の解決策を4つ紹介しましたが、ご本人の希望や要介護度などにより適しているサービスは異なります。家族で話し合い、状況に合ったサービスを選択することが重要です。
老老介護の不安を軽減するために、介護の現状と制度を知ろう
老老介護状態になっている方々は年々増加傾向にあります。老老介護は、介護者の身体的・精神的な負担が大きく、共倒れや介護放棄を招くリスクもあります。
老老介護を解決する方法としては、介護サービスや見守りサービスの利用、介護施設への入居などが挙げられます。家族の状況に合ったサービスや制度を選びましょう。
また、健康的な生活を心がけたり、介護教室に参加したりと、老老介護にならないための対策を講じることも大切です。介護サービスの利用や介護施設への入居が必要となった場合の経済的な負担に備えて、民間の介護保険に加入することも検討しましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。
公開日:2025年5月14日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




