詳しい資料はこちら
公的介護保険で利用できる介護サービスの種類まとめ
居宅・施設・地域密着型サービス
「もし家族の介護が必要になったら、どのようなサービスを利用できるのか」「公的介護保険で利用できる介護サービスの種類がよくわからない」などの不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
公的介護保険では、要支援・要介護の認定を受けると、訪問介護や施設入所など希望に応じて多様な介護サービスを利用できます。
この記事では、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの3つを中心に、公的介護保険で利用できる介護サービスの種類を一覧でご紹介するとともに、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
詳しい資料はこちら
公的介護保険で利用できる介護サービスとは
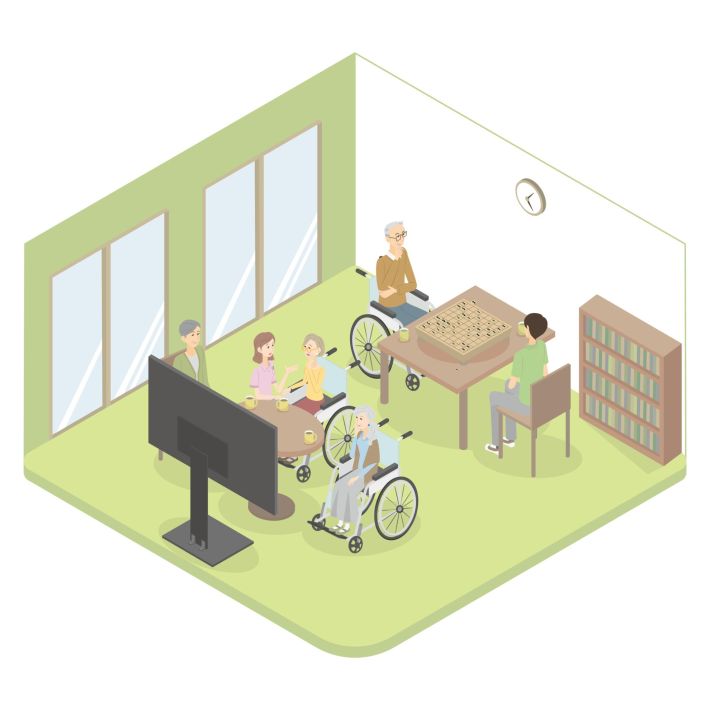
要支援・要介護の認定者数は年々増加しており、2030年には65歳以上の約4人に1人※が該当すると推計されています。
※厚生労働省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」および内閣府「令和6年版高齢社会白書」より当社にて推計
介護サービスが必要になった際、スムーズに利用できるようにするには、利用方法を事前に確認しておくことが大切です。
以下の記事では、公的介護保険について詳しく解説しています。
公的介護保険とは?公的介護保険申請から利用開始まで
【早わかり一覧】介護サービスの種類
|
居宅サービス |
訪問 |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 |
|
通い |
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア) |
|
|
宿泊 |
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護 |
|
|
福祉用具・住宅改修 |
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修 |
|
|
施設サービス |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
|
|
介護老人保健施設(老健) |
||
|
介護医療院 |
||
|
特定施設入居者生活介護 |
介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム) など |
|
|
地域密着型サービス |
訪問 |
夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
|
通い |
認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護 |
|
|
訪問・通い・宿泊の組み合わせ |
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
|
|
施設入所 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特養、地域密着型特定施設入居者生活介護 |
|
居宅サービス|自宅で暮らしながら受けられる支援

サービスは利用者の状態や希望に合わせて柔軟に組み合わせることができ、身体介護だけでなく、生活支援やリハビリテーション、住宅環境の整備も対象になります。
以下では、居宅サービスの代表的な内容を「訪問」「通い」「宿泊」「福祉用具・住宅改修」の4つに分けて紹介します。
より詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:居宅サービスとは?種類や自己負担額・利用開始までの流れ
訪問
|
訪問介護(ホームヘルプ) |
介護職員が自宅を訪問し、要介護者の入浴・排せつ・食事などの身体介護や掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行う |
|
訪問入浴介護 |
専用の浴槽を使用し、要介護者の自宅での入浴を支援 |
|
訪問看護 |
看護師などが自宅を訪問し、要介護者の病状の観察や医師の指示による医療処置を提供 |
|
訪問リハビリテーション |
理学療法士などが自宅で要介護者の機能訓練を行い、身体機能の維持・改善をサポート |
|
居宅療養管理指導 |
医師・薬剤師・管理栄養士などが定期的に自宅を訪問し、要介護者の健康管理や服薬指導を行う |
通い
|
通所介護(デイサービス) |
日中の数時間、要介護者が施設に通って食事・入浴・レクリエーション・機能訓練などを受ける |
|
通所リハビリテーション(デイケア) |
医師の指示に基づき、要介護者の機能回復や日常生活動作の訓練を目的に行われるサービスで、理学療法士・作業療法士などの専門職が支援する |
宿泊
|
短期入所生活介護(ショートステイ) |
要介護者が施設に短期間宿泊して介護を受けるサービス |
|
短期入所療養介護 |
より医療的なニーズに対応した短期宿泊サービスで、医師や看護師の配置がある施設で提供される |
福祉用具・住宅改修
|
福祉用具貸与 |
介護ベッドや車いす、歩行器などをレンタルできる制度 |
|
特定福祉用具販売 |
排せつ用具や入浴用具など、衛生上の理由からレンタルではなく購入が望ましい用具を対象に、費用の一部が支給される |
|
住宅改修 |
手すりの設置・段差の解消・滑り防止床材の施工などを対象に、原則18万円を上限に工事費用の9割(一定所得以上は8割または7割)まで支給される |
施設サービス|施設に入所して受けられる支援
対象となるのは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」などの公的施設と、「特定施設入居者生活介護」に該当する民間施設です。
ここでは、それぞれの施設の特徴や支援内容について紹介します。
また、以下の記事では施設サービスについて詳しく解説しているため、併せて参考にしてください。
関連記事:公的介護保険の施設サービスとは?種類や費用の目安
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
医療機関との連携も進められて終身利用が可能である点が特徴です。家族の介護負担を軽減したい場合や、自宅での生活が難しい方に適しています。
関連記事:特別養護老人ホーム(特養)の費用や入居条件|メリット・デメリット・施設選びのポイントとは?
介護老人保健施設(老健)
要介護1以上の方が対象で、医師・看護師・リハビリテーション職員・介護職員が連携し、日常生活に必要な機能回復訓練などを行います。
入所期間は基本的に3~6ヵ月とされており、短期間で集中的にリハビリテーションに取り組みます。
関連記事:「老健」とは?特徴・利用方法・費用や「特養」との違い
介護医療院
施設内には医師や看護師が常駐しており、病状の管理や必要な医療処置が提供されます。従来の介護療養型医療施設の転換先として創設された背景があり、終末期のケアや長期的な療養生活に対応できる点が特徴です。
特定施設入居者生活介護
施設の種類により設備やサービス内容は異なりますが、要支援1以上の方が対象となっています。入浴や食事などの生活支援に加え、機能訓練なども提供されるのが特徴です。
地域密着型サービス|地域に根差した身近な支援

大規模な施設ではなく、地域に根差した小規模な事業所や施設を通じて、利用者の状態や生活環境に応じたきめ細やかな支援が提供される点が特徴です。
訪問・通所・宿泊を柔軟に組み合わせたサービスや、認知症の方への専門的支援、小規模な施設での入所支援など、その内容は多岐にわたります。
以下では、地域密着型サービスのおもな種類について紹介します。より詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せて参考にしてください。
関連記事:地域密着型サービスとは? サービスの対象者・種類・利用の流れ
訪問
|
夜間対応型訪問介護 |
夜間を中心に訪問介護員が自宅を訪問し、要介護者の排せつ介助や安否確認などを行う |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
1日複数回の定期訪問と、必要に応じて随時の訪問介護・訪問看護を行う24時間体制のサービス |
通い
|
認知症対応型通所介護 |
認知症の高齢者が通える少人数制の施設で、専門的な対応による介護や機能訓練、レクリエーションなどを提供する |
|
地域密着型通所介護 |
定員18名以下の小規模なデイサービスで、要介護者が住み慣れた地域で日常生活を続けられるよう、個別ニーズに応じた介護や機能訓練、レクリエーションを提供 |
訪問・通い・宿泊の組み合わせ
|
小規模多機能型居宅介護 |
訪問・通所・宿泊の3つのサービスを1つの事業所で提供する柔軟な支援 |
|
看護小規模多機能型居宅介護 |
上記の小規模多機能型に「訪問看護」が加わったサービスで、医療ニーズの高い方にも対応できる |
施設入所
|
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら、介護職員による支援を受ける施設 |
|
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) |
従来の特養と同様のサービスを、定員29人以下の小規模施設で提供する形態 |
公的介護保険が適用される介護サービスの種類を知り、状況に応じて活用しよう
公的介護保険では、自宅での生活を支える居宅サービス、入所者に介護や医療的ケアを提供する施設サービス、地域での生活に適した支援を行う地域密着型サービスの3つを軸に、さまざまな介護サービスを提供しています。
要介護度や生活環境、医療ニーズ、家族の介護体制などに応じて柔軟に選択できる仕組みとなっている点が特徴です。各サービスの特徴をあらかじめ把握しておくと、よりスムーズな利用が可能になります。将来の介護に備えるためにも、制度の内容を正しく理解し、自分や家族の状況に応じて上手に活用しましょう。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
赤上 直紀

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士
公開日:2025年9月10日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




