詳しい資料はこちら
認知症の原因とは?認知症の種類と原因
脳の病気や萎縮など、さまざまな原因により脳の機能が低下することで日常生活全般に支障が出る状態を認知症と呼びます。認知症の原因や症状などを知り、いざというときに適切な対処ができるようにしたい方もいるでしょう。
認知症にはアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症などいくつかの種類があり、それぞれ原因や症状、対処法などが異なります。
本記事では認知症の概要と、代表的な認知症の種類、発症する原因、症状、リスクを高める習慣、予防法について解説します。
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
認知症は病気を総称する「症候群」
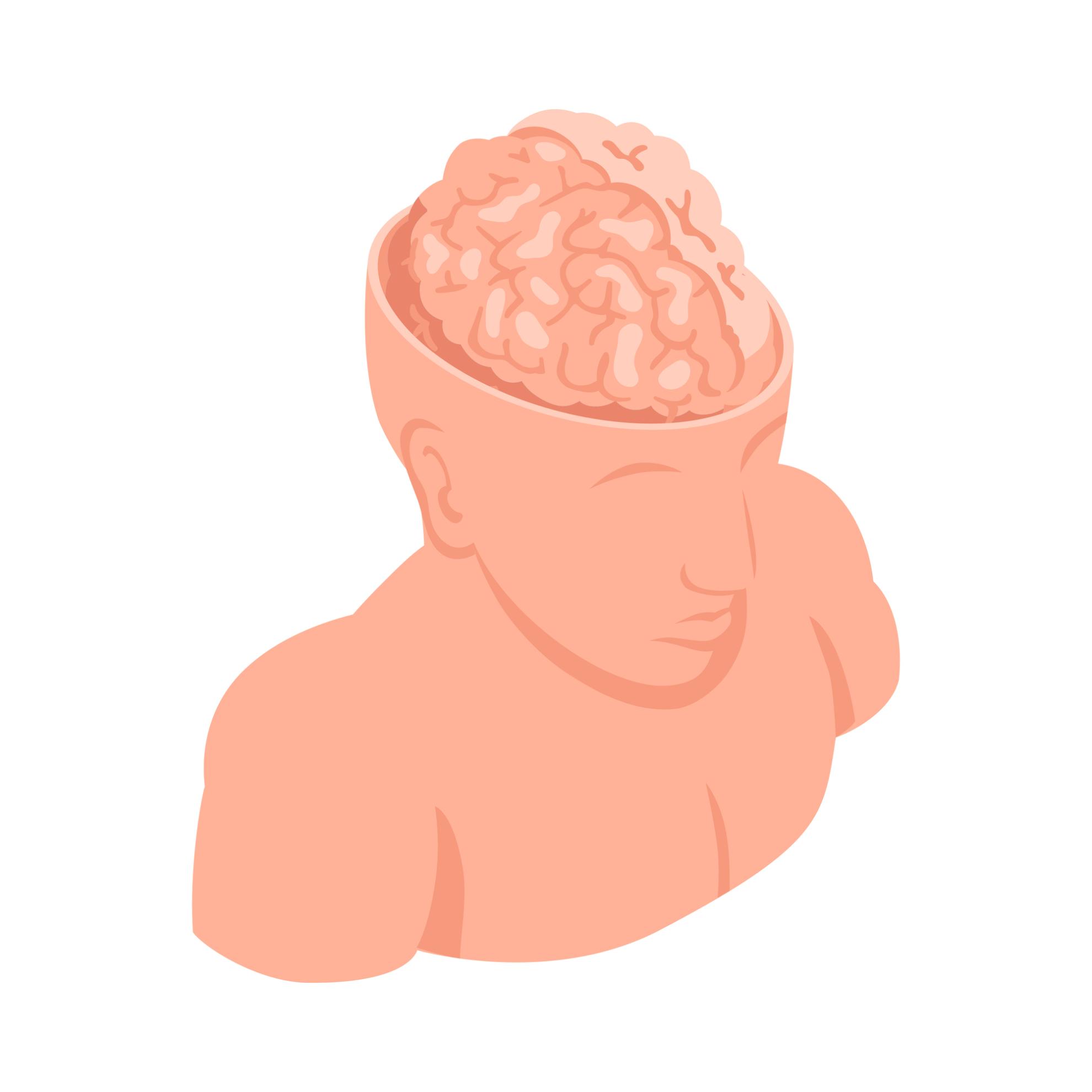
認知症とは特有の症状を示す状態の総称であり、特定の病気をあらわすものではありません。病気や障害により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出ている状態を「認知症」といいます。
認知症は脳細胞の一部が死滅したり、働きが悪くなったりすることによって発症します。発症の原因となる病気は複数あり、原因となる病気によって発生しやすい症状も異なります。
軽度認知障害(MCI)・認知症患者は増加傾向にあり、2030年には65歳以上の約3人に1人に達すると予測されています。※
今後も、高齢化にともなって認知症患者は増えていくことが予想され、認知症は多くの人にとって身近なものになりつつあります。
認知症は脳細胞の一部が死滅したり、働きが悪くなったりすることによって発症します。発症の原因となる病気は複数あり、原因となる病気によって発生しやすい症状も異なります。
軽度認知障害(MCI)・認知症患者は増加傾向にあり、2030年には65歳以上の約3人に1人に達すると予測されています。※
今後も、高齢化にともなって認知症患者は増えていくことが予想され、認知症は多くの人にとって身近なものになりつつあります。
※65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用。
※内閣府「平成29年版高齢社会白書」、首相官邸認知症施策推進関係閣僚会議(第2回)資料、厚生労働省老健局 社会保障審議会 介護保険部会(第92回)「介護保険制度をめぐる最近の動向について」より当社推計
認知症のおもな種類と原因
認知症は、病型・症状によってアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症およびそのほかの疾患を原因とする認知症に大別されます。
厚生労働省の資料によると、認知症の原因となるおもな病気は、アルツハイマー型認知症67.6%、脳血管性認知症19.5%、レビー小体型認知症4.3%、前頭側頭型認知症1.0%です。
厚生労働省の資料によると、認知症の原因となるおもな病気は、アルツハイマー型認知症67.6%、脳血管性認知症19.5%、レビー小体型認知症4.3%、前頭側頭型認知症1.0%です。
各認知症の概要と症状を見ていきましょう。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は脳内にたまったアミロイドβと呼ばれる異常たんぱく質によって脳神経が変性し、脳の一部が萎縮する過程で発症するといわれています。
アルツハイマー型認知症は、記憶障害(もの忘れ)や失語(名前が出てこない)、失認(視覚には問題ないのに見えているものが何かわからない)、失行(動作には問題ないのにどうすれば良いかわからない)などの症状が出ることが特徴的です。
治療法は確立されておらず、早期発見が重要とされていますが、加齢によるもの忘れと区別がつきづらいことから、受診が遅れてしまうケースもあります。アルツハイマー型認知症の原因には諸説あり、現在ではまだ全容が解明されていません。
関連記事:アルツハイマー型認知症とは?原因・症状・治療方法
アルツハイマー型認知症は、記憶障害(もの忘れ)や失語(名前が出てこない)、失認(視覚には問題ないのに見えているものが何かわからない)、失行(動作には問題ないのにどうすれば良いかわからない)などの症状が出ることが特徴的です。
治療法は確立されておらず、早期発見が重要とされていますが、加齢によるもの忘れと区別がつきづらいことから、受診が遅れてしまうケースもあります。アルツハイマー型認知症の原因には諸説あり、現在ではまだ全容が解明されていません。
関連記事:アルツハイマー型認知症とは?原因・症状・治療方法
脳血管性認知症
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって発症する認知症です。血液が不足して神経細胞の機能が失われたり、たまった血液によって脳が圧迫されたりすることによって、さまざまな症状が現れます。
脳血管性認知症では、記憶障害から認知機能障害が少しずつ広がるのが特徴で、抑うつや感情失禁などの症状が出ることもあります。脳血管障害を起こした部位によっても症状は変化し、歩行障害や手足の麻痺などの症状が見られる場合もあります。
関連記事:脳血管性認知症とは?主な症状や進行・原因・診断・治療まで詳しく解説
脳血管性認知症では、記憶障害から認知機能障害が少しずつ広がるのが特徴で、抑うつや感情失禁などの症状が出ることもあります。脳血管障害を起こした部位によっても症状は変化し、歩行障害や手足の麻痺などの症状が見られる場合もあります。
関連記事:脳血管性認知症とは?主な症状や進行・原因・診断・治療まで詳しく解説
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、レビー小体という異常たんぱく質が神経細胞にたまることで発症する認知症です。女性より男性のほうが発症しやすく、ほかの認知症よりも進行が早いという特徴があります。
レビー小体型認知症のおもな症状は、記憶障害や認知機能障害、幻視、歩行等動作障害(パーキンソン症状)などです。夜中に大声で叫んだり身体を大きく動かしたりする(本人は夢を見ているような感覚で覚えていない)などの症状をともなう場合もあります。
レビー小体型認知症は症状の変動が大きいため、症状の特徴を理解したうえでの周囲の支援が必要になります。
関連記事:レビー小体型認知症の原因と症状|初期症状から治療法まで解説
レビー小体型認知症のおもな症状は、記憶障害や認知機能障害、幻視、歩行等動作障害(パーキンソン症状)などです。夜中に大声で叫んだり身体を大きく動かしたりする(本人は夢を見ているような感覚で覚えていない)などの症状をともなう場合もあります。
レビー小体型認知症は症状の変動が大きいため、症状の特徴を理解したうえでの周囲の支援が必要になります。
関連記事:レビー小体型認知症の原因と症状|初期症状から治療法まで解説
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、前頭葉と側頭葉で神経が変性して発症する認知症です。発症には特定のたんぱく質が関与していることはわかっていますが、なぜたんぱく質が変質するかはわかっていません。
理性的な行動ができなくなり、言葉が出なくなるなどの症状が現れたりするほか、穏やかだった人が急に怒りっぽくなるといった性格の変化が起きます。
認知症は高齢になると発症しやすくなりますが、前頭側頭型認知症は50~60代の比較的若い年齢で発症することが多くあります。症状の進行が早いため、前頭側頭型認知症は早期発見が重要です。
関連記事:前頭側頭型認知症とは?発症する原因や症状・関わり方を解説
理性的な行動ができなくなり、言葉が出なくなるなどの症状が現れたりするほか、穏やかだった人が急に怒りっぽくなるといった性格の変化が起きます。
認知症は高齢になると発症しやすくなりますが、前頭側頭型認知症は50~60代の比較的若い年齢で発症することが多くあります。症状の進行が早いため、前頭側頭型認知症は早期発見が重要です。
関連記事:前頭側頭型認知症とは?発症する原因や症状・関わり方を解説
そのほかの原因疾患
上記4種類以外にも、認知症の疾患となる病気があります。
【そのほかの認知症原因疾患】
【そのほかの認知症原因疾患】
-
神経変性疾患(大脳皮質基底核変性症、進行性核上性麻痺など)大脳皮質基底核変性症や進行性核上性麻痺を発症すると、人格変化や意欲低下といった認知症の症状が現れます。進行性核上性麻痺では、声かけに対する反応の遅れも見られます。
-
感染性疾患(クロイツフェルト・ヤコブ病など)クロイツフェルト・ヤコブ病では、急速に進行するもの忘れや、言葉が出にくくなる、意思の疎通が難しくなるといった認知症の症状が見られます。
-
アルコール性疾患(コルサコフ症候群など)コルサコフ症候群で現れやすい認知症の症状は、新しいことを覚えられない記銘力障害や、時間・場所などがわからなくなる見当識障害などです。さらに、失った記憶を補完したり、記憶を誤ってつなぎ合わせたりなどして話を作り上げる、作話の症状が見られる場合もあります。
-
内分泌・代謝性中毒性疾患(ビタミンB12欠乏症、肝性脳症など)ビタミンB12欠乏症で現れる認知症の症状は、記憶障害です。肝性脳症では、記憶力・注意力の低下や判断力の欠如などの症状が見られます。
認知症と間違われやすい疾患
認知症と同じような症状を呈するため、一見認知症と診断されやすい疾患もあります。これらの疾患であれば、身体あるいは精神の原因を取り除くことができれば、症状が回復することがあります。
【認知症と間違われやすい疾患】
●うつ病
●甲状腺機能低下症
●正常圧水頭症
●腫瘍性疾患(脳腫瘍など) など
【認知症と間違われやすい疾患】
●うつ病
●甲状腺機能低下症
●正常圧水頭症
●腫瘍性疾患(脳腫瘍など) など
認知症のおもな2つの症状

認知症の症状は、脳の働きが低下することによって発生する中核症状と、中核症状に周辺環境や患者本人の性格などが影響して発生する周辺症状(行動・心理症状)とに大別されます。
中核症状と周辺症状で起こる症状をそれぞれ見ていきましょう。
中核症状と周辺症状で起こる症状をそれぞれ見ていきましょう。
中核症状:脳の神経細胞の働きが低下して起こる症状
中核症状には記憶障害、実行機能障害、見当識障害などが挙げられます。代表的な中核症状と症状の内容は以下のとおりです。
| 記憶障害 | 何度も同じことを話す。ものの位置や約束を忘れてしまう |
| 実行機能障害 | 計画や段取りを立てられなくなる |
| 見当識障害 | 時間や場所がわからなくなる。季節に合わせた服が選べない |
| 失語 | 言語の理解・表出が難しくなる |
| 失行 | 運動機能に問題はないものの、適切な行動をとれなくなる |
| 失認 | 視覚機能に問題はないものの、目の前のものが何か認識できなくなる |
周辺症状:中核症状によって発生する症状(行動・心理症状)
周辺症状は患者本人の性格や周辺環境によって左右されるため、特徴的な症状が出ない方もいます。おもな周辺症状とその内容は以下のとおりです。
| 抑うつ | 気分が落ち込み食欲不振や不眠などの症状が出る |
| 徘徊 | 今いる場所や行き先がわからなくなり、歩き回る |
| 幻覚・妄想 | ありえないものを現実に感じる、誤った認識を間違いないと思いこむ |
| 暴言・暴力 | 感情のコントロールができず、不満や不安により暴力や暴言が現れる |
| 介護拒否 | 介護の意味を理解できず介護を拒否する |
認知症の原因になりうる6つの習慣

以下の6つは、認知症発症の原因になりうる習慣です。これらに気を付けて生活することは、認知症予防につながります。
偏った食生活
偏った食生活は、認知症の発症リスクを上げる可能性があります。特に、塩分や糖分、脂質の過剰な摂取には注意が必要です。次のような食品を摂りすぎると、認知症の一因となる生活習慣病のリスクが高まります。
-
肉の脂身肉の脂身には飽和脂肪酸が多く含まれ、過剰摂取すると動脈硬化や脳梗塞のリスクが上がります。その結果、脳血管性認知症を発症するリスクも高まります。
-
マーガリンマーガリンに含まれるトランス脂肪酸は、悪玉コレステロール(LDL)を増やす要因です。血中の悪玉コレステロールが増加すると動脈硬化になる可能性が高くなり、脳への血流が悪くなるため、認知症の発症リスクも高まります。
-
菓子パン菓子パンのおもな原材料は、砂糖や小麦などの糖質です。食べすぎると血糖値が急上昇し、高血糖などを引き起こしかねません。この状態が続くと糖尿病から認知症の発症を招く可能性があります。
ほかには、超加工食品の過剰摂取にも注意しなければなりません。超加工食品とは、糖分や塩分、脂肪を多く含み、添加物や保存料などを加えて長期保存を可能とした加工食品のことです。
具体的には、一部のポテトチップスやカップ麺、ケーキ、ドーナツなどが該当します。これらを多く摂取すると、高血圧や糖尿病、肥満などのリスクが高まり、認知症の発症にもつながる可能性があります。
具体的には、一部のポテトチップスやカップ麺、ケーキ、ドーナツなどが該当します。これらを多く摂取すると、高血圧や糖尿病、肥満などのリスクが高まり、認知症の発症にもつながる可能性があります。
飲酒
飲酒も認知症の発症リスクを上げる要因です。アルコールの慢性的な過剰摂取は脳に深刻な影響を与え、特にアルコール依存症の方は脳の萎縮が高い割合で見られます。脳の萎縮は認知機能の低下や脳梗塞のリスクを高めるため、過剰なアルコール摂取は控えることをおすすめします。
アルコールの影響で認知症が発症・進行すると、注意力や記憶力が低下し、感情がコントロールできないといった症状が現れることがあります。
また、アルコールは加齢による記憶能力や学習能力の低下を促進させることもわかっています。さらに、飲酒によってうつ病や頭部外傷、けいれんなどの症状が引き起こされる可能性があり、これらも同様に認知症発症の一因です。
アルコールの影響で認知症が発症・進行すると、注意力や記憶力が低下し、感情がコントロールできないといった症状が現れることがあります。
また、アルコールは加齢による記憶能力や学習能力の低下を促進させることもわかっています。さらに、飲酒によってうつ病や頭部外傷、けいれんなどの症状が引き起こされる可能性があり、これらも同様に認知症発症の一因です。
喫煙
認知症の発症要因のなかで、特にリスクが高いのは喫煙であり、喫煙者は非喫煙者よりも認知症を発症する可能性が2~3倍高いという研究結果もあるほどです。
また、喫煙歴が長いほど認知症の発症リスクが高くなる傾向も見られます。喫煙による酸化ストレスや血流の悪化が原因で、脳のダメージが進行し認知機能の低下につながります。
さらに、脳卒中・糖尿病・心疾患など、認知症の発症リスクを高めるとされる疾患が、喫煙によって引き起こされてしまう可能性もあります。
また、喫煙歴が長いほど認知症の発症リスクが高くなる傾向も見られます。喫煙による酸化ストレスや血流の悪化が原因で、脳のダメージが進行し認知機能の低下につながります。
さらに、脳卒中・糖尿病・心疾患など、認知症の発症リスクを高めるとされる疾患が、喫煙によって引き起こされてしまう可能性もあります。
運動不足
アメリカの研究結果によると、アルツハイマー型認知症の発症リスクを上げる最大の原因は運動不足です。さらに、一日の歩行距離が少ない人は、多い人よりも認知症の発症リスクが約2倍高くなるという研究結果も出ています。
なお、運動だけでなく、家事やガーデニングなどの日常的な身体活動の量も関係しています。近年の研究では、日常的な活動量が多い人は、少ない人よりも認知症の発症リスクが低いことが明らかになりました。
「アミロイドβ」や「タウタンパク質」という物質が過剰に蓄積されると、アルツハイマー病などの認知症疾患の原因になるといわれています。
運動不足の人はこれらの物質が排出されづらい傾向にあるため、運動により脳の血流をよくして老廃物の排出を促すことが大切です。
なお、運動だけでなく、家事やガーデニングなどの日常的な身体活動の量も関係しています。近年の研究では、日常的な活動量が多い人は、少ない人よりも認知症の発症リスクが低いことが明らかになりました。
「アミロイドβ」や「タウタンパク質」という物質が過剰に蓄積されると、アルツハイマー病などの認知症疾患の原因になるといわれています。
運動不足の人はこれらの物質が排出されづらい傾向にあるため、運動により脳の血流をよくして老廃物の排出を促すことが大切です。
脳への刺激が少ない
脳への刺激が少ないと、認知症は急速に進行する可能性があります。特に、コミュニケーションの不足は脳への刺激を減らす大きな要因です。
国立長寿医療研究センターの研究によると、同居家族とのやりとりや、友人および隣人との交流などが多い人は、少ない人より認知症の発症リスクが低いことがわかっています。
また、自分で考える機会が減少することも、脳への刺激不足につながります。そのため、家族が気を遣って、家事や身の回りの世話などをしすぎることには注意が必要です。
国立長寿医療研究センターの研究によると、同居家族とのやりとりや、友人および隣人との交流などが多い人は、少ない人より認知症の発症リスクが低いことがわかっています。
また、自分で考える機会が減少することも、脳への刺激不足につながります。そのため、家族が気を遣って、家事や身の回りの世話などをしすぎることには注意が必要です。
ストレス
ストレスは血行不良や神経細胞へのダメージ、自律神経の乱れなどを引き起こし、認知症の発症リスクを高める可能性があります。
さらに、ストレスにより「コルチゾール」というホルモンが過剰に分泌され、記憶力や学習能力の低下につながるおそれもあります。
また、高齢になると環境の変化や、以前できていたことができなくなるストレスからうつ病になり、その後認知症を発症するというパターンも少なくありません。
さらに、ストレスにより「コルチゾール」というホルモンが過剰に分泌され、記憶力や学習能力の低下につながるおそれもあります。
また、高齢になると環境の変化や、以前できていたことができなくなるストレスからうつ病になり、その後認知症を発症するというパターンも少なくありません。
認知症を予防するには?
認知症の原因の多くは解明されておらず、具体的な予防方法はありません。しかし、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症は生活習慣病と関連があるとされており、生活習慣の改善によって認知症予防につながる可能性があります。
具体的には適度な食事、運動、睡眠を心がけ、生活習慣病にならないように健康的な生活を送ることが大切です。
関連記事:認知症の予防はできる?将来のリスクを減らす生活習慣のポイント
認知症予防に効果的な食べ物とは?
明確な予防法が確立されていない認知症は、早期段階での発見・対応が重要となります。症状に気付いたら、早めにかかりつけ医や保健師など専門家に連絡し、どのように対応すれば良いかを相談しましょう。
関連記事:認知症の治療法とは?症状や治療法、治療を続けるポイント
具体的には適度な食事、運動、睡眠を心がけ、生活習慣病にならないように健康的な生活を送ることが大切です。
関連記事:認知症の予防はできる?将来のリスクを減らす生活習慣のポイント
認知症予防に効果的な食べ物とは?
明確な予防法が確立されていない認知症は、早期段階での発見・対応が重要となります。症状に気付いたら、早めにかかりつけ医や保健師など専門家に連絡し、どのように対応すれば良いかを相談しましょう。
関連記事:認知症の治療法とは?症状や治療法、治療を続けるポイント
認知症を発症する原因を知り、生活習慣を改善しよう
認知症は誰にでも起こりうるものです。認知症にはアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などの種類があり、それぞれ発生する症状に違いがあります。
認知症は予防が難しく、根本的な治療方法も確立されていません。しかし、認知症の原因となりうる習慣に気を付けた生活は、予防につながる可能性があります。
症状の悪化を防ぐためにも、認知症の種類や症状を知り、少しでも気になったら可能な限り早く医師や保健師などに相談しましょう。
朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。
別府 拓紀[医師]

産業医科大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院、市中病院、企業の専属産業医などを経て、現在は市中病院で地域の精神科医療に従事している。
資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など
資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など
公開日:2025年3月10日
介護について知る
介護を予防する
-
-
各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。
介護について考える
-
親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。
公的制度・支援サービス
-
公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。
-
軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。
-
介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。
-
公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。
-
通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
介護の費用
-
介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
-
介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。
介護が始まったら
-
要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。
認知症について知る
認知症とは
-
レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。
-
認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
認知症の予防
-
認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。
-
高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。
もの忘れ・認知症の専門家の
特別コンテンツ
-
認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。
-
初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
-
認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。
生活習慣病について知る
生活習慣病とは
生活習慣病の予防
-
その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。
-
日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。
-
高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。
-
心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。




